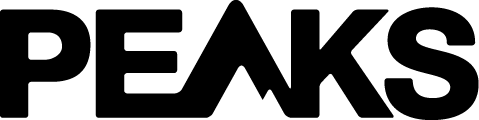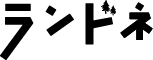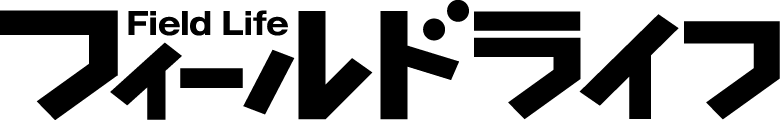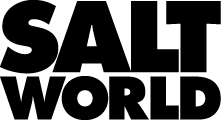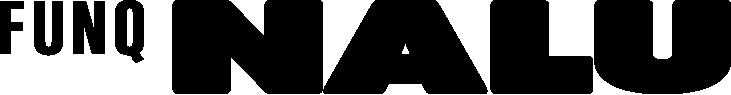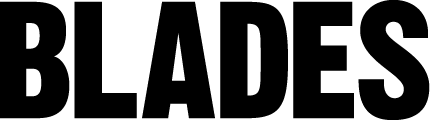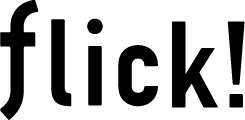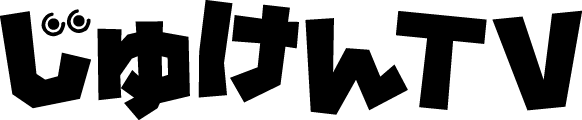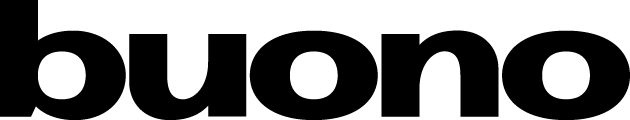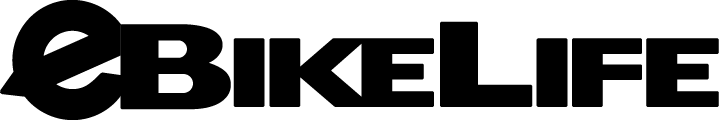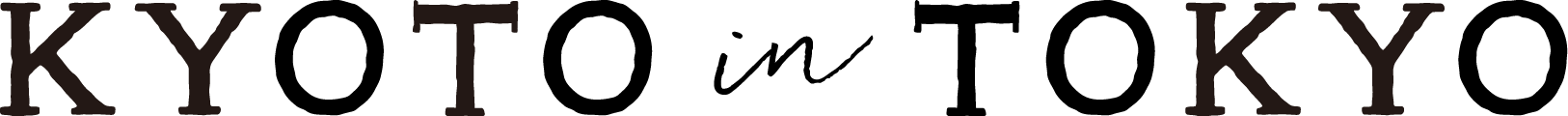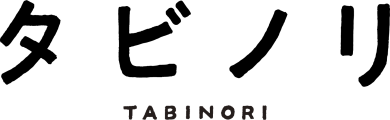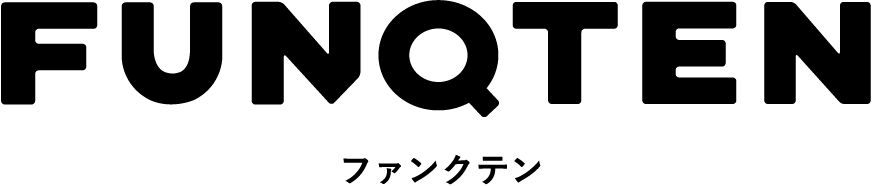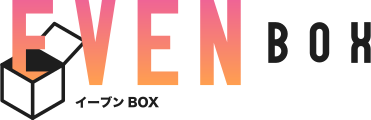ヨーロッパでの体験と、インドを訪れたときの経験をとおして感じた“旅”と“旅行”の違い|劇団EXILE・佐藤寛太の旅手引き #16
佐藤寛太
- 2025年03月17日
自分にとっての“旅”と“旅行”の違いとはなんだろう。2年前にインドを訪れたときの経験と、去年の12月にヨーロッパへ行ったときのことをとおして思うこと。
文・写真◉佐藤寛太
ヨーロッパの国々での体験
昨年の12月、ヨーロッパを訪れた。古くからの建物が残る国、肌の色、目の色、髪の毛の色から癖まで、多くの個性に溢れた街ではファッションがすばらしかった。多くの人が自分のサイズを愛した袖丈で服を着て、個性を活かした色使いをしていた。

立ち寄った美術館でも、人間は芸術を突き詰めるとここまで達成できるのかと、ただただ感嘆し、いまなお放つ作品のパワーに圧倒された。
すばらしい国々で素敵な体験をしたが、今回の体験を言葉で現すなら、“旅”というより、“旅行”だった気がしている。細かい言葉の違いではあるけれど、自分にとってそのふたつの違いはなんなんだろうと思ったとき、現地の人とお金を払うこと以外での交流だと気づいた。

インドで身をもって味わった経験
僕にとって、2年前にインドに行ったことが“旅”を身をもって味わう経験となった。
一泊数百円の宿に泊まり、地元の人に聞いたカレー屋に行き、長距離バスに乗って移動する。もちろん、お金を払って旅をしていたのだけれど、インドには余白があった。こちらがツアーに申し込まなければ、イベントは向こうからやってきた。
長距離バスに乗っていたとき、山岳区域で雨による地滑りが起き、バスが先に進めないということがあった。近くの席に乗っていたバックパッカー数人とローカルの人で、近くの街まで走る臨時のタクシーを拾い、乗せてもらった。現金の持ち合わせがなかった僕は、同乗したバックパッカーに立て替えてもらい、腰の丈まで水につかる道路を小舟さながら揺られるバスに乗り、なんとかその日のうちに近くの街に着くことができた。といってもバスが出発してから街に着くまで24時間は経過していた。

またあるときは、長く泊まっていたホステルから山に向けて出発するとき、仲良くなった青年が片道1時間半かかる道を原付で送ってくれた。インドの人はすぐに“Brother”の意味の“Bro”という呼び方で呼ぶのだが、彼のBroという響きには特別なものを感じ、僕もBroと呼んでいた。帰り際、「気をつけろよ」と、お互いスマートフォンでビデオを撮り合い別れたけれど、彼はガソリン代も含め、決してお金を受け取らなかった。

またあるときは、ひとりで7日間の行程をハイキングしていた際に途中に点在している集落に民泊というかたちで泊まっていたのだが、ある家族の食卓でそこのお母さんと子どもたちといっしょに食事を作った。
その翌日、雨により増水した橋のない川を、数人の登山者で力を合わせて渡りきった。
そしてあるときは、ガンジス川で燃える遺体を階段に座って見つめていたところ、青年がほど近いところに腰を下ろしたので話しかけてみると、いま現在自分が見ていた遺体はその青年のおじいちゃんのもので、意外なことに「君は写真を撮らないのか?」と彼に聞かれた。おどろいた僕は嫌じゃないのかと聞き返すと、ここはそういう場所になっているから自分はとくに複雑な気持ちにはならないといわれ、促されるまま、シャッターを切った。
ガンジス川を歩けば、すぐに物を売りつけようと人に声をかけられ、日本人がめずらしいらしくいっしょに写真を撮ろうと言われ、タクシーもトゥクトゥクも値段交渉のために人がすぐに集まってくる。
お金を求めてきた数人の子どもに、ふざけて返すと“可哀想な子ども”という演技をしていた仮面が徐々に剥がれ、いっしょになってふざける年相応の彼らの素顔が見えてくる。持っていたフルーツを分けて食べ、地域の情報をその子たちをとおして聞いたりした。
知らない土地に行くことで得られること
自分の知らない土地に行き、自分の生活圏では出会えない人々と話し、文化、思想、宗教に触れる。その体験は自分の内面をそのまま写し、多角的に自分の姿が見える鏡になる気がする。
ひとりで登る山には過去を振り返り、人生をシンプルに感じさせてくれる感傷と勇気を。旅先で訪れた人々には自分の目の届く範囲の人を大事にしようという優しさが与えられる。
今年はどんな一年になるだろう。どんな土地へ行き、人に会い、だれとどんなものを食べてすごすのだろう。変わりゆく自分の変化を静かに受け入れ、勉学に励み、身体を鍛え、健康に、日々を大事に生活したいと思う。

日常に余白がありますように。
寛太
SHARE