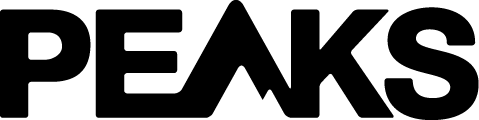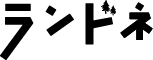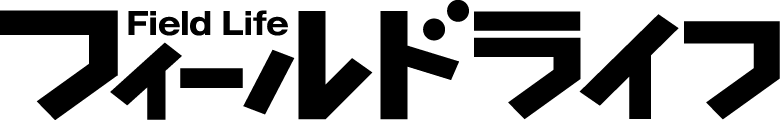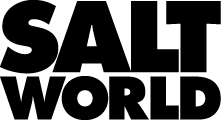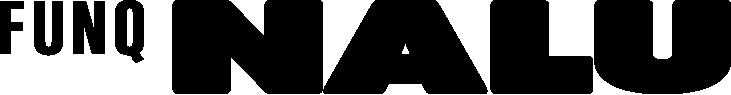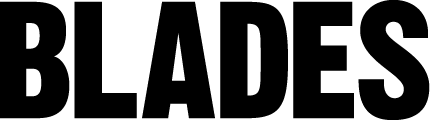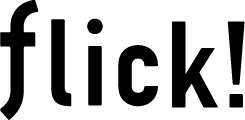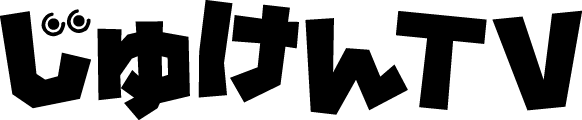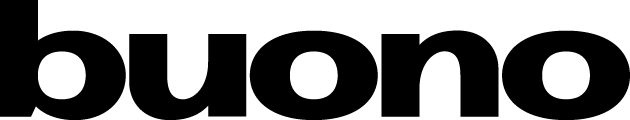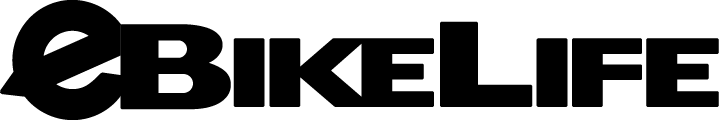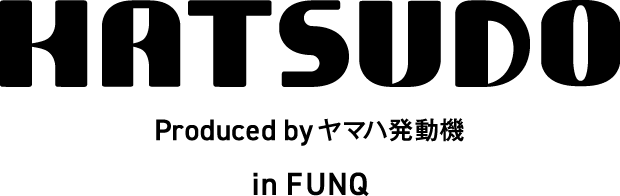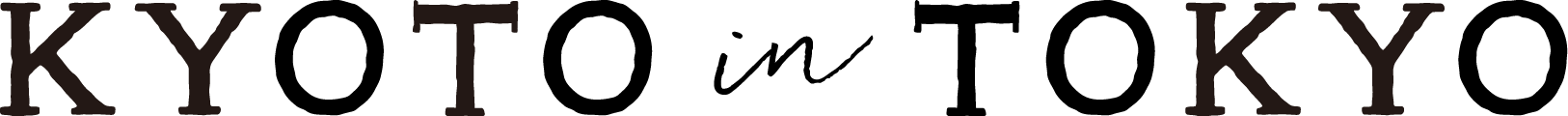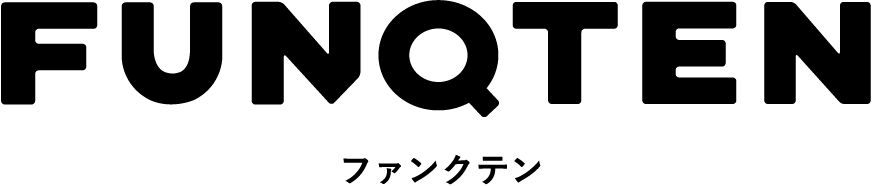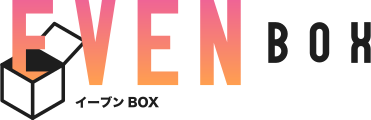町から遠く離れた山小屋に暮らすということ 〜黒部源流にて〜
PEAKS 編集部
- 2020年07月08日
北アルプスの最奥地ともいうべき、黒部源流。そこには、かつて、「山賊」と呼ばれた男たちと肩を組んだ山男が遺した、3つの小屋がある。その小屋のひとつである、三俣山荘を守るのが、伊藤圭さん。幼少期から山小屋ですごした伊藤さんに聞く、山に暮らすこと、そして黒部の魅力とは。

山になじんでいかないと、ぼく自身、生きていけないような気がしています。
「どこでもドア……ではないのですが、分離したふたつの世界みたいで、なかなか結びつかなかったです」
1歳から夏を山小屋で、それもアクセスに2日はかかる、北アルプスの最深部ですごしてきた、伊藤圭さん。父親である伊藤正一さんは、黒部源流を見守るようにたたずむ3つの山小屋、三俣山荘、水晶小屋、雲ノ平山荘などを築きあげ、また「勤労者山岳会(現在の日本勤労者山岳連盟)」を結成するなど、戦後登山文化の発展を担った名物男だ。
「一方で、戦前は物理学者を志すなど文化人的な側面があり、都会人として山に生きろ、なんて言っていたんです」
新宿のど真ん中に育ちながら、夏は北アルプスの山小屋へ。それはどんな感覚かとたずねたところ、返ってきたのが冒頭の言葉だった。
「進んで選び取った人とは違うだろうけど、山はからだに染みついた要素。だから、山になじんでいかないと、ぼく自身も生きていけないような気がしています」
夏祭りもプールも知らなかった少年は、24歳で水晶小屋を受け継ぎ、40歳になったいま、2児の父として、家族とともに三俣山荘を守っている。

「人がいていいのか……そんな印象を持たざるを得ない場ですね」
12度の夏をすごした水晶小屋を、伊藤さんはそう振り返る。ときに石ころが飛び交うという北アルプスでも有数の強風は、2度にわたり、建て直しをはかった小屋を吹き飛ばしていた。
「そのうえ沢がないので、飲み水は雨水頼み。ひとつひとつのことをきちんとやらないと、生きていけないような世界ですね」
当時の小屋は1964年に建てられたプレハブ造り。早い段階の建て直しを考えてはみたものの、どういう素材、設計をとればあの環境に適応できるのか……。その間、下見に向かうため搭乗したヘリが墜落し、自身は無事だったものの同乗の2名は死亡。山に関わるほどにその重みが増してゆく。
「そうして2007年にようやく再建したのが、いまの水晶小屋です」
その思いの一端を、伊藤さんはホームページにこう綴っている。
――風土に対する人間の回答が文化だとすればまさに〝水晶小屋という一つの文化の生成〞に挑戦する機会となりました――
水晶岳には独特の迫りくる磁場のようななにかを感じるけれど、三俣山荘は、ハイマツに守られ、水が豊富で落ち着く。逆に、雲ノ平は楽園すぎて、ぼくはちょっと……と苦笑い。そんな彼の地に惚れこんだ弟の二朗さんが、雲ノ平山荘を引き継いでいる。
「なんだかロマンチックなムードがあって、従業員同士の結婚も多いんです」
そう笑う彼自身、妻・敦子さんとは雲ノ平山荘で知り合っているのだとか。
「わたしは水晶での、がんばって生きていく感じ、が好きですよ」
愛娘を抱いた敦子さんは、にっこりとほほえんだ。
「日常の快適さを山へ」から「山で培った生きる術を日常へ」
長く山と人を見てきた伊藤さんに、近年の変化を聞いてみる。すると、テント泊の若い人が増えたこと、と即答する。
「いまの若い人は、より真摯な感じ。肌身で山を感じたいんじゃないでしょうか」

それに対し、積み重ねてきた知恵や経験ではなく、最新技術を駆使することへの劣等感――真意をはかりかね、のぞきこむ。
「お金を払ってヘリを飛ばし、冷凍食品を飽和状態に抱えている姿はどこか不自然だし、その仕組みは続かない気がするんです」
事実、麓での事業などに比べてリスクの高い山小屋へのヘリ輸送は、避けられ気味な傾向があるのだとか。ならばテント泊登山者のための自炊施設を充実させてもいいし、昔のように、米と味噌だけは持参してもらうという方向もあるだろう。知恵の新旧が問題なのではなく、次代への架け橋たるかを模索する。
「水晶小屋が目指すのは、システムとして完結した小屋、です」
破綻のないバイオトイレ、小屋をまかなえる蓄電環境、そして徹底的な雨水の利用――。
「そういう場をいったんつくり、土壌を築いてから、次の話をしたいという思いがあります」

70年前、父が身を削って作り上げた小屋は、いまなお登山者に愛されている。正一さんの課題は、日常の快適さを稜線上に引き上げること、だった。息子である圭さんは、山から町へ下ろすものがあってもいい、と考えている。
「自然と人間、テクノロジーの限界点ともいうべき水晶小屋で培った生きる術は、町の暮らしや災害時にも役立てると思うんです」
平地でひと家族分の太陽エネルギーを得ることは難しくはないし、条件がそろえば、水を引くこともできるだろう。
「そうした技術が、唯一、ぼくらが提示できるもので、そんなアプローチができるくらいの力は持っていたいと思っています」
そして、それができるのはぼくらだけではないと、ぽつり。
「山を歩くこと、眠ることを通して考えたことって、自ずと生活に反映されると思うんです。いまは流行的でうわっついている面もありますが、山から町に持ち帰るものが、どこかで自然と人をかみ合わせる鍵になる気がします」
父・正一さんの偉大な仕事のひとつに『黒部の山賊』(山と溪谷社)という著書がある。戦後間もない北アルプスの奥地へ入りこみ、山賊と称された男たちと、三俣山荘を切り盛りする物語。そこには、科学の目とユーモアの心で綴られる、魑魅魍魎をはらんだ日常が繰り広げられている。

「親父は話し好きで、お客さんにもそんな物語を聞かせていました。
あんな語り部とともにある種の雰囲気ができあがると思うんです」
そして、父が拓いたものの廃道になった伊藤新道。復興を進める古道は、森と沢が織りなす渓が広がり、濃密な気配をたたえている。
「そんななか、竿を振っていると、川という生き物に触れているという実感があるんです」
かつて、黒部には獣を狩り、イワナを漁すなどる生活があった。そして、獲物を追う男たちは山中での越冬をも辞さなかったという。そうした物語を聞き育った伊藤さんの言葉の端々には、その残り香がうかがえた。饒舌さだけが語り部の条件ではない。若き二代目の話を聞きながら、そんなことを思った。
「スタッフやお客さんを見ていて思うのは、こんなにも人は山や自然を必要としているんだ、ということ。人と自然の交差点としての山小屋を、いつまでも守っていきたいと思っています」
伊藤 圭

1977年生まれ。三俣山荘の経営、運営に奔走。10年前から、より山を感じるために、家族で長野県安曇野市に移住。オフタイムにはバンド「ヒーターズ」を率いて活動中。
SHARE
PROFILE

PEAKS 編集部
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。