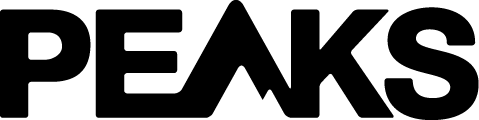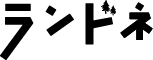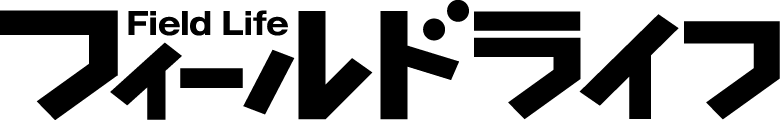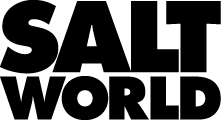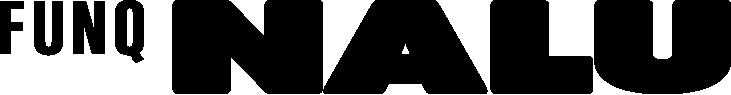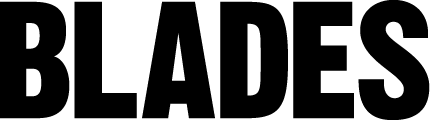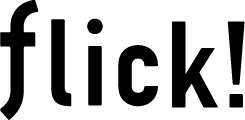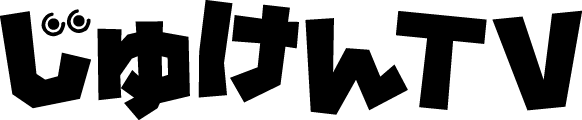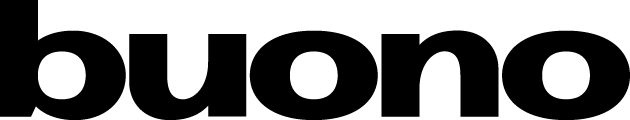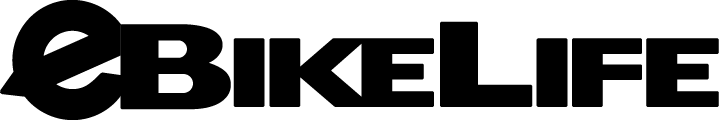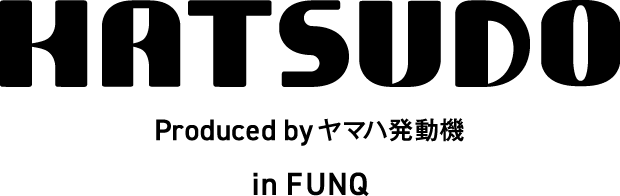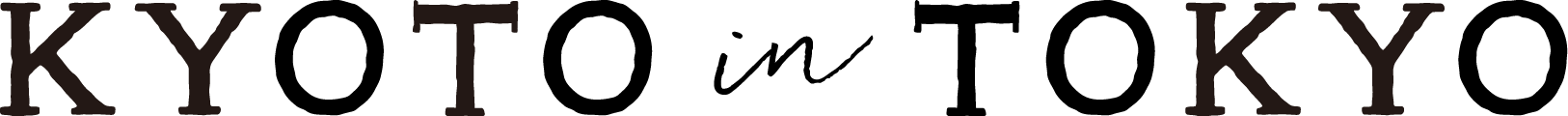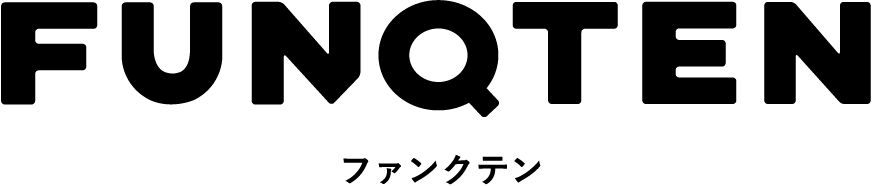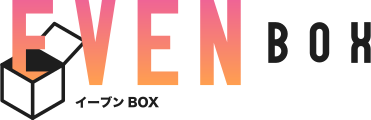大天井岳、燕岳を行く|北アルプスで過ごしたはじめての夏
PEAKS 編集部
- 2020年09月26日
プロドラマーとして数々の有名ロックバンドで活躍する野崎真助さん、野崎真希さん夫妻が発した一言。「じつは、何年も前から登山に憧れていたんですよ」そこから急発展して、僕たちは常念岳から燕岳へと続く稜線に向かった。時期は7月中旬、それは梅雨どきの奇跡的な晴れ間を願っての旅であった。
文◉村石太郎 Text by Taro Muraishi
写真◉松本 茜 Photo by Akane Matsumoto
取材期間:2019年7月16日~18日
出典◉PEAKS 2019年9月号 No.118
「葉っぱが水分を含んで活き活きとしてきている。人も、植物も同じですね」

一ノ沢の登山口から出発して約3時間、それまでパラパラと降っていた雨が本降りになってきた。
「レインジャケットだけ羽織って、バックパックにはカバーを掛けましょうか」
笹原沢との出合で休憩をしていたときだった。僕は、いっしょに歩いていた野崎真助さんと真希さん夫妻にそう告げると、レインジャケットのフードをかぶった。雨足が強くなってきたといっても、森のなかである。レインパンツは履かずに、ふたたび歩き出すことにした。
すぐ脇を流れている一ノ沢は上流に行くにしたがって徐々に水量を減らしていき、登山道の丸太橋を渡って対岸へと向かった。

「わぁ、葉っぱが水分を含んで活き活きとしてきている。人も、植物も同じですね」
真希さんが言ったそんな言葉を聞いて、僕はちょっと安心した。ふたりにとって、今回が初めての登山だった。それなのに雨に降られながら歩かなくてはならなかった。
「登山なんて二度と行かない」といわれてしまわないか、ちょっと恐れていたのだ。野崎夫婦と出会ったのは、わずか1カ月ほど前のことだった。友人たちと餃子を囲んでいた夜に、プロドラマーとして活躍する野崎真助さんが何年も前から登山に興味を抱いていたことを打ち明けてくれたのだ。
真助さんは、5~6年前から本誌PEAKS読者であるとも話した。しかし、今日まで実現できずに、高峰を目指す夢を抱き続けてきたのだという。

意気投合した僕たちはカレンダーのなかから共通の休みを探した。偶然にも、3人の休みが合致した。ふたりと出かけるために考えたプランは、北アルプスの常念岳から燕岳へと至る稜線を歩くというものだった。
穂高連峰と槍ヶ岳を遠景に快適な縦走路を進み、白く輝く砂礫が敷き詰められた燕岳の景色をふたりに見てもらいたい。きっとだれもが、あの景色を見れば登山好きになってくれるだろう。そんな思いがあった。

1泊目は無理をせず、一ノ沢のヒエ平登山口から登りはじめて5時間ほどのところにある常念小屋をキャンプ地とする。翌日は、常念小屋を出発して大天井岳を経由しながら、燕岳から下山しよう。
2日目の行程は約9時間と少し長いので、天候悪化や体力的にキツいときのために3日目を予備日として設けた。大天井岳や燕岳で2泊目をすごすというセカンドプランも用意している。
時期は、7月の中旬。梅雨が明けるか、明けないか微妙ではある。

もしも天候に恵まれなければ登山を中止したり、登山口から常念小屋に往復して帰ってくることも考えていた。それに天候次第ではテントではなくて、山小屋に泊まってもいい。
予定日が近づくに従い、僕の不安は高まっていった。梅雨は明けず、目まぐるしく変わっていく天候は予測不能だった。
出発の前日になると、初日の予報が「曇り、ときどき小雨」から「曇りときどき晴れ」へと変わった。2日目に多少の雨が降りそうだったが風も弱く、最悪の状況は免れそうだ。

「明日からの登山、決行しましょう!」
出発の前日、ふたりにメッセージを送ると「よろしくお願いします!」と返信があった。真助さんは、1週間ほど前からこれまでに揃えたアウトドア道具を取り出して、明日の出発を楽しみにしていたという。そのいっぽうで、不安もあったと打ち明ける。とくに、妻の真希さんが体力的に問題ないか心配していた。
そんな彼に、僕は万が一のオプションも考えていたので、「天候が悪かったり、キツかったら途中で下山してきてもいいので行きましょう」と話したのだった。
一ノ沢を登り詰め、道標に〝胸突八丁〞とある急登を越えていく。

すると、次第に視界が開けてきた。
先ほどまで重く垂れ込めていた雨雲は、さっきまで登ってきた山の斜面下に溜まっていた。最後の休憩で、僕たちはレインジャケットを脱いでバックパックのなかにしまった。
稜線に到着すると、まもなく常念小屋の煉瓦色の屋根が見えてきた。周囲は陽が差し始め、次第に青空が広がってくる。そんな景色を見ていた真助さんは、目に少し涙を浮かべていた。

僕は、キャンプ地利用の受付のため山小屋に向かった。
真希さんたちには山小屋の手前で休憩してもらっていたのだが、陽光に包まれた広場ではふたりが日向ぼっこをしている姿があった。

「はい、ご褒美(笑)」
キンキンに冷えた缶ビールをそういって手渡すと、プルタブを開ける。
明日は、また天候が崩れるのだろうか?
そんな不安を抱いていたけれど、常念岳上空はどこまでも晴れ渡っていて、雨の心配などまったくない。テントを設営し終えると、酒とツマミを手に夏の午後を思う存分堪能するのであった。
「もう、大丈夫じゃない。っていうときが何回もあった(笑)」

翌朝の始まりも、また感動的であった。山並みの彼方から登る朝日をふたりに見せたいと思っていた僕は、起床を午前3時半と伝えていた。午前中の天気予報はまずまずで、午後から雨がぱらつきそうだった。そのため、早朝に出発したいと思っていたのだ。寝ぼけ眼で寝袋から体を抜け出して、テントのジッパーを開ける。

きっと分厚い雲に覆われているのだろう。そんな想像をしながら外を見渡す。すると、雲ひとつない紺碧の空が広がっていた。登山靴を履いてテントから飛び出すと、穂高連峰の横から、満月がひょっこりと顔を出している。僕よりも早くに起きていた真助さんたちも、その景色に見とれていた。
湯を沸かして、簡単な朝食とコーヒーをふたりに手渡すと、出発の準備を始めた。
「今日も、いい日になりそうだ」
そんな期待とは裏腹に、そんなにうまくことが進むわけないよなとも思っていた。午後には雨に降られることも覚悟しながら、午前5時半すぎに出発した。
眩いばかりの朝日に照らされて、朝いちばんの急登を登って高度を上げていく。すると、山の陰に隠れていた槍ヶ岳の姿があらわれた。
穂高連峰の中央に広がる涸沢カールも見えてきた。僕たちはいったん立ち止まり、印象的な景色に目を留めた。

遠景の山肌には、まだ多くの雪渓が残っている。登山道の周囲では、色とりどりの草花が咲き乱れ、チクチクと小鳥の鳴き声がこだまする。斜面の上のほうに目をやると、そこには雷鳥のひなが大慌てで親鳥を探していた。クゥクゥという鳴き声のもとをたどると、すぐ足元に親鳥がいた。
「やった、会えた!」
出発前から、雷鳥をひと目見たいと話していた真希さんの目が輝いた。
どうやら僕たちが歩いてきたことで、登山道の左右に分かれてしまった親子が、おたがいを見失ってしまったようだった。

大天井岳までの道のりは多少の遅れはあったものの、順調に進んできた。ここからはクサリ場のある切通岩まで一気に標高を落としていく。
真希さんが足の痛みを訴えたのは、このときだ。足の小指のつけ根あたりが少し傷むようだ。膝も少し、笑ってきているという。

「いまのうちに、痛み止めにパッチを貼っておきましょうか」
そう話してバックパックから取り出したブリスターパッチを貼って、両膝にはサポーターを巻いた。
「調子はどう?」
少し歩き出したところでの問いかけに、真希さんは「すっごく楽になった」と微笑んだ。
大天井岳からの急降下を終えて、クサリ場もなんなく通過した。時計を見ると、時刻は午前10時半。

ここまで順調に来れば、遅くとも1時すぎには燕山荘に到着するだろう。僕は、このときそんな安心感を抱き始めていた。
しかし、この暑さが堪えた。寒くなることは考えていた。だが、ここまでの晴天に恵まれ、気温が上がることはほとんど考えていなかった。
ときおり吹く、ほてった体を冷やしてくれる微風が、なによりもありがたかった。しかし、登山道が尾根の反対側に回ると風はピタリとやみ、靄に覆われて蒸し風呂に入っているような不快感を覚えた。

ふたりには、頻繁に水を飲むように伝えた。わずか2時間程度の道のりが、とても長く感じる。同時に真希さんの歩みも止まった。
それでも少し休憩すると、「また歩けるかも」と言ってすくっと立ち上がった。僕たちの歩みは緩やかだが、一歩一歩着実に燕山荘と向かっていった。

「もう、大丈夫じゃないっていうときが何回もあった(笑)」
真希さんは、燕山荘に到着する直前にそう白状した。そんな告白に僕たちは大笑いした。そして、「まずは」とビールを注文しに売店へと向かった。
生ビール(大)1000円
生ビール(中)800円
生ビール(小)600円

大、中、小のグラスジョッキが並べられた売店の前で「うーん」と悩んでいた真助さんに、「大、いっちゃいますか」と肩を押す。
すると「そうですね! じゃあ生ビールの大をください」と注文すると、なみなみと注がれた容量1ℓはあろうかという大きなグラスジョッキを手渡された。

そして、揚々とした足取りで山小屋の軒先に置かれたテーブルに向かい、今日一日を振り返るのであった。
真希さんは満面の笑みを浮かべて、「止まったら動けなくなるから、このまま歩こうと思った」と話しはじめた。
「心地いい風が吹いてくると、まだ歩けるかもって思うことができて。またすぐに、やっぱり限界だってなるんですけどね(笑)」
そこに、少し赤ら顔になった真助さんが「思っていたよりもキツかったですよ」と話に加わった。

「でも、同時に思っていた以上に楽しかった。山があんなに連なっている景色は、こういうところに来ないと見られないですもんね。生命力豊かな高山植物とか、なにも草木が生えていない岩肌とか。それに雲の動き。『あぁー』っていちいち感心しながら歩いていましたよ」
「そうそう、雷鳥もすごい可愛かった。もちろん、体はめっちゃきつかったし、明日も不安はあるけど。雲海とか、太陽に近いところから見る朝日とか。来る前はテントに泊まって歩くなんてハードなんじゃないかなとか。テントに泊まることが、あんまり好きじゃないっていう人もいるでしょ? だから少し不安もあったけど、ここに来ないと見られない景色や体験、来ないとわからないこととかがいっぱいあって」
少し不安もあったけど、ここに来ないと見られない景色や体験、わからないことが、いっぱいだった。
一日歩き続けたあとの心地よい疲労感に包まれながら、そんな会話を楽しんでいると背後で山小屋に泊まっていた登山者たちがざわついた。聞くと、自分の影のまわりに光の輪が現れるブロッケン現象が起こっているという。真希さんは、いま知り合ったばかりの登山者に混ざって写真を撮りに行った。
「このあいだ、いっしょに夕食を食べていたときに、ポンッと『山登りに行きませんか?』って誘ってもらったじゃないですか。そのとき、『あっ、この誘われ方は乗ったほうがいいかも』って思ったんですよね(笑)。

以前、米国を旅行したときに現地の人が火を熾してくれて、そこで夕飯を作ってくれたことがあったんですよ。もともとは、そこからアウトドアに興味を持ち始めたんです。
それと、ミュージシャン仲間たちに、アウトドアが趣味だっていうやつが多いんです。仕事中に、スタジオで『あぁ、山行きてぇ』って言っているのもいたりして(笑)。
でも、自分は興味はあるけれど、実践できる知識も、登山の技術もまったくない。そういうやつらの話を聞いたりして『わぁ、いいなぁ』ってずっと思っていたんです」
すでに大ジョッキのビールを飲み終えて、僕たちはすっかりいい気分になっていた。そこへ写真を撮りにいっていた真希さんが戻ってきて、「ふたりとも、だいぶ顔が赤くなってる」と笑った。
そんな彼女に、真助さんは「いやいや、これは日焼けだよ」と微笑んだ。
少し気温が下がり始めたのでジャケットを羽織ると、荷物のなかからガスストーブを取り出した。

そして、オイルサーディンに鷹の爪を加えて着火する。すると、真助さんが「もう一杯だけ、小ビールでいきましょうか?」と言って、まもなく営業を終了する売店の窓口へと向かった。そのジョッキも飲み干すと、今度は持ってきた日本酒の蓋を開けた。まだ周囲は明るく、時間はゆっくりと流れていった。

「歩き終えたあとの、この時間が好きなんですよね」
ふたりにそう話すと、真希さんが「私も好き」と頷き、「さっき言い忘れたけど、こういうところで食べるご飯も山の魅力ですよね」と言った。
「登山に興味はあるけれど、実践できる知識も技術もまったくない。でも、ずっといいなぁって思っていた」

翌日の朝、テントから抜け出して周囲を見渡すと空が真っ赤に染まっていた。時刻は午前4時。眼下に見えるはずの街並みは雲海に遮られていて、その隙間から朝日が昇ろうとしていた。空の上のほうは、まだ薄暗い紺碧色に覆われている。すでに幾人かの登山者が三脚を立てて、その光景を写真に収めようとしている。
ここから下山口とした中房温泉までの道のりは約3時間。だが、夕方から雨との予報が出ていたため、今日も早めに出発しようと昨夜決めていた。朝焼けは天候悪化の兆しだが、梅雨どきにこんな景色が見られるなんて、なんという幸運だ。初日の雨模様から一転しての好天に、翌朝には満月、昨夜はブロッケン現象を見た。そしてこの朝焼けである。

朝食を終えた僕たちは、中房温泉に向けて出発した。真希さんの膝は大丈夫だろうか。
途中の合戦小屋では、名物の冷えたスイカをいただき、少し長めの休憩とした。高度を落としていくにしたがって森が深くなり、木床は苔むしていった。そうこうしていると雨が降り始め、レインジャケットを羽織った。気温も上昇して、蒸し暑さが増していった。
反対側から歩いてきた韓国からのツアー客たちが「アニハセヨ」という挨拶とともにすれ違っていった。もう一度天気予報を確認すると、大きな雨雲が近づき始めている。彼らには申し訳ないが、明日からは雨が降る日が続くようだった。
ようやく中房温泉に到着したのは、午後1時をすぎたころ。雨はすでにやんでいて、また陽が差し始めていた。時間は少し余分にかかったけれど、3人とも無事に歩きとおした。穂高駅までのバスの出発は1時間ほどあとになる。登山靴をサンダルに履き変えて、登山口にあったベンチで休憩をしているとふたたび雨が降り出してきた。急いで屋根の下に移動すると、さらに雨足が強くなってくる。

それから数時間、帰宅までのあいだ雨は降り続いた。翌日も、またその翌日も雨は降り続いた。
「本当に奇跡的でしたね」
後日、そう真助さんたちにメッセージを送ると、「最高の体験でした」と返信をもらった。
そして、「機会を見つけて、また出かけましょう」と約束を交わした。記録的に日照時間が少なかったという今年の7月にすごした休日は、こうして終わるのであった。
はじめての登山には、少しハードだった!?
今回歩いたのは、1泊2日でも十分に歩けるルートだ。しかし、雨のなかを歩くことが予想され、はじめての登山ということもあって予備日を含めた3日間で計画した。結果としては、みんなでなんとか歩ききったという印象であり、少しハードルを上げすぎたのかもしれないことを反省する。ちなみに、膝が痛くなったときに備えて用意したサポーターが本当に役立った。
>>ルートガイドはこちらから
- BRAND :
- PEAKS
- CREDIT :
-
文◉村石太郎 Text by Taro Muraishi
写真◉松本 茜 Photo by Akane Matsumoto
取材期間:2019年7月16日~18日
SHARE
PROFILE

PEAKS 編集部
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。