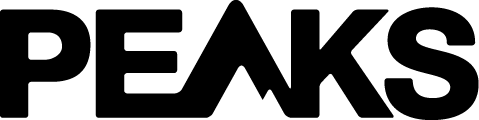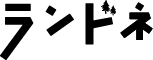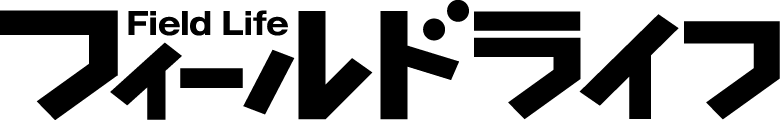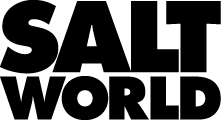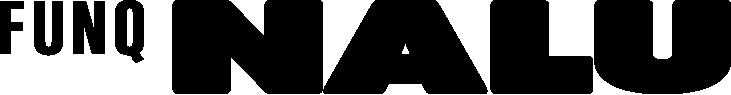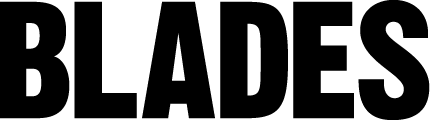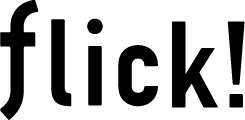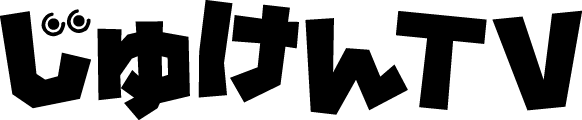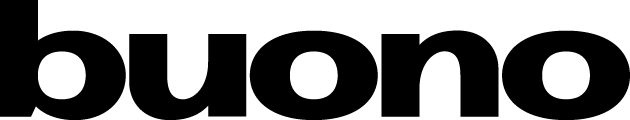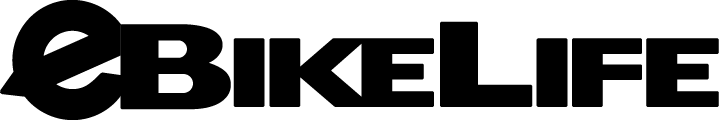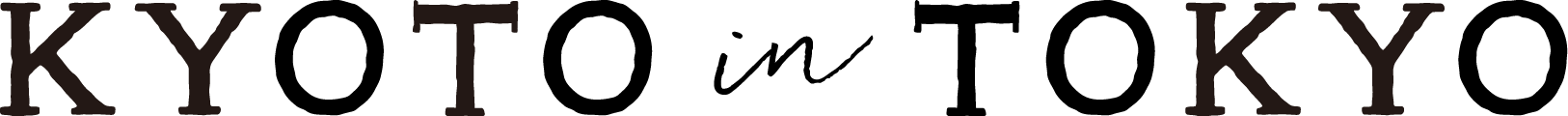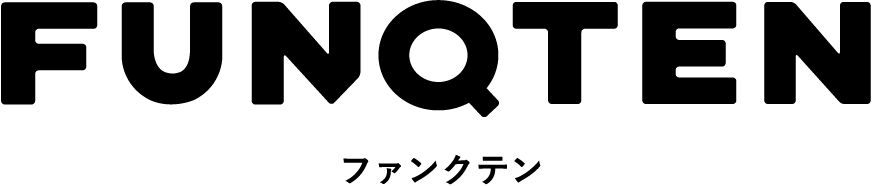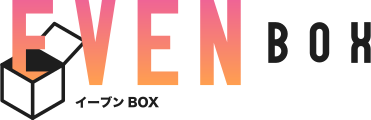「ザイテンの道直しのこと(中編)」|Study to be quiet #5
成田賢二
- 2022年08月08日
INDEX
文◉成田賢ニ Text by Kenji Narita
写真提供◉ハチプロダクション
ハイマツコーナー
その年の「ザイテン」には宮田の懸念の場所があった。最初の崩壊箇所の石組みを終えると、宮田は私をそこへ案内した。
「ここや、ハイマツコーナーって呼んでんねんけど、去年はひとり死んどる。一昨年はふたり、その前もひとりかな。全部下りや。どないやねん。さあて、弁当食おか」
私たちは岩角に腰かけて小屋の女衆が作ってくれた弁当を頬張りながら、その場所をしみじみ眺めた。
梅雨を忘れたような青空でカールのなかは静まり返っている。雪渓からの風が止まると少し暑い。登山者はだれも上がって来ず、岩雲雀が唄いながら雲を追っている。
宮田が「ハイマツコーナー」と呼んだその場所は、ザイテンが涸沢岳側で鋭角に折れ曲がるような形状をしており、50度くらいのスラブ状の岩盤にボルトが埋め込まれ、そこに木材が番線で固定されて足場とされていた。悪いことにそのスラブ全体が奥穂側よりも強く涸沢岳側に、外へねじれるように傾斜しており、重力は明らかにガレ場のほうへと導かれていた。
そしてその重力方向にはなんとなくハイマツが繁茂しており、一見するとさほど危険な場所には見えない。
「人って明らかに危ないとこでは落ちひんのや。なんともないとこで魔が差すんやな。ほれ」
宮田は無造作にジョレンの柄でハイマツを押しのけた。
「ガレ場まで真っ逆さまや。40mくらいは落ちるやろか。まず助からん。お前、どう思う?」
私はその場所をつぶさに観察し、私なりの経験から宮田の目に叶うような改善すべき点を探した。しかしそこはザイテンの致命的な弱点が露呈した場所であった。急峻な岩尾根の両側壁が削り取られた格好は、数万年の氷河の仕業にほかならない。ザイテンが尾根道である以上、道の形状をこれ以上改善させる余地は明らかになかった。
「下界に三年で4人も死ぬ交差点がありゃ改善されるの当たり前や。壁取り払って信号つけて、道路拡幅や。だけどここではそんなことできへん」

無意識の改善
私は仕方なく見た目の悪さを提案した。転落する斜面側にハイマツが落下物を受けるように繁茂しており、登山者の無意識になぜか危険を「感じさせない」ようななにかがあった。
宮田は同感し、ひとまずハイマツを間引くことにした。ボルトと岩角を支点にしたロープに恐る恐るハーネスでぶら下がり、ハイマツに鋸を当てて何本か間引く。これにより見通しが効き、どうやら危ない場所だと認識できるようになった。しかし形状としての危なさに変わりはなく、依然として不安は残る。雨の日などはどう見てもよくない。
私たちは足元のボルトをさらに打ち足して、そこに縛り付ける木材を強く奥穂側に傾けるように改修した。これにより足場はやや歩きにくくなるものの、それにより登山者のスピードが落ち、重心が強く山側に傾くことで、見ている側としてはわずかに気が楽になった。しかし相変わらず、スラブ面全体が、前後との流れのなかでは不自然に涸沢岳側に傾斜してるのは変えようがない。

手すり
「右足、左足、右足やろ、その次の左足がどうにもあかんねん。こりゃダメや、手すり、つけちゃうか?」
午前中の仕事で崩壊箇所の路肩に敷いた木材は、まだ余っている。手すりをつければ根本的に全ての懸念は解決する。しかし当然そのままでは冬を越すことはできず、毎秋にバラして仕舞い、また初夏には付け直さねばならない。
さらにこの場所が安全になったとしても、これより上にはいくらでも似たような箇所は存在する。ここに手すりをつけることで、この先も手すりがあるはずだと誤解する登山者がいないか。さらにいえば、そもそも穂高に手すりは必要なのか。
だとすればこの先も穂高に手すりをかけ続けるのか。
宮田は私の意見を聞きながらも、結局は自分自身に問うように悩んでいた。
「一回つけてみよ。材木あるんやし。オレもうザイテンで死人見たないねん」
私たちは懸念のスラブの谷側に、ドリルで穴を空け自立する杭を打った。そこにツーバイ材を番線で固定した。さらに山側にも同様の加工を施して、手すりとなりそうなロープを強張した。これにより両側に手をかける固定物ができ、ハイマツコーナーは安全になった。

悩み
その晩、宮田は少し荒れた。
山荘のフロントの奥には調理場があり、さらにその南の角に三畳ほどのごく小さなスペースがある。石油ストーブのうしろに狭い入り口があり、小さな長椅子が南北の両壁を背もたれにして置いてある。真ん中に小さな机、棚にはスタッフのマイカップが置かれ、頭の上にも棚があって本がところ狭しと並べられている。
奥に座った人間が出るにはその列の全員が動かないと出られない。奥ほど上座とされているのは雰囲気ですぐに理解でき、宮田が定位置であろう北側の最奥に座り、その対面には現支配人の中林が座って飲んでいた。
私は長椅子の中ほどに座り、ストーブ回りには長椅子に座りきれない若い衆や、あるいは酒やつまみを運ぶ女衆が、調理場の丸椅子を持ち込んで座っていた。私はこの整然と秩序が保たれた小さな長四角の空間で、宮田が吠えるのを聞くのが好きだった。いかにもこの場所はそれに相応しかった。
「この前オレのブログがちょっと炎上してん。アホな装備の登山者を叩いたんやな、そしたらなんやと思う? お前らがそんなとこで商売しとるから行くんやないか、わざわざ苦労して来る客に文句言う資格あるんかいな、やと。匿名や。まあある意味こっちかてぐうの音も出えへん」
宮田は支配人を中林に譲ってからは、客の前に出ることはほとんどなくなっていた。映像制作に集中し、日中は外仕事をしているが、早朝と夕方の斜光が良い日にはカメラを持ってどこかにいった。
実際のところは、山の常識をわきまえない客を玄関先で睨み付けてしまうことがあったため、客から遠ざけられてしまったというのが実情らしい。

中林のこと
私は宮田のいないところでその日あったハイマツコーナーでのことを中林に話した。
中林は学生時代に、若き日の宮田に居酒屋でスカウトされて小屋番に引き込まれたという経緯がある。高校時代はアルペンスキーの選手としてならした。土木現場に精通し、機械にも強い。支配人としての人望厚く、女衆にも若い衆にも慕われている。過去には仕事のことから宮田と掴み合いの喧嘩も何回かしたらしいが、翌朝にはケロっとして飯を食っていたふたりである。
中林には語り口には独特の雰囲気があり、宮田のような芝居じみた名言は決して吐かない。しかしものごとの事情はよくわきまえており、最後には照れ臭そうに含みのあるひとことをボソリと言う人である。言われた側はそのひとことをあとになってから反芻し、この人はこんなことまでわかったうえでこちらの話を聞いていたんだなと気恥ずかしくなる。
中林は一連の話を聞いてから、いつものように照れ臭そうに言った。
「あれやろ、八郎さんの、例によって悩みたいんやろ、小屋番の苦悩みたいな。好きやから、そういうの。そんなんあっても別に言わんでもええやん。だれでもあるよ、悩み。手すり? そんなん、要らんよ、要るわけないやん、穂高に」

SHARE