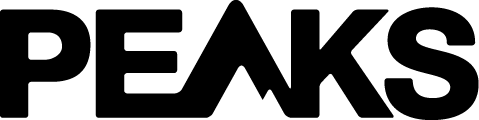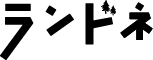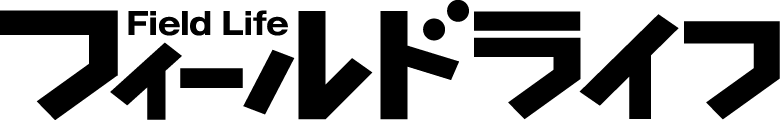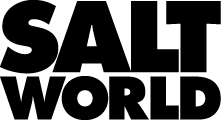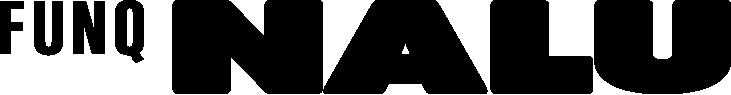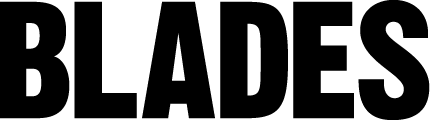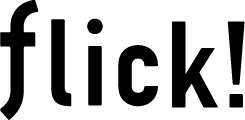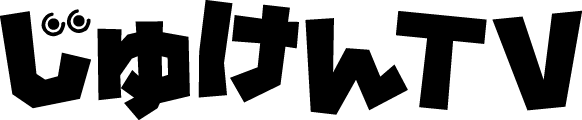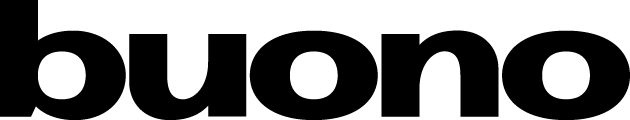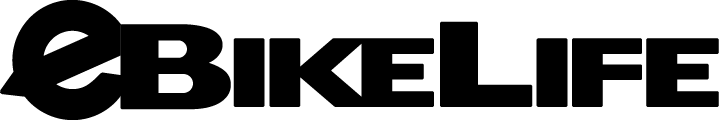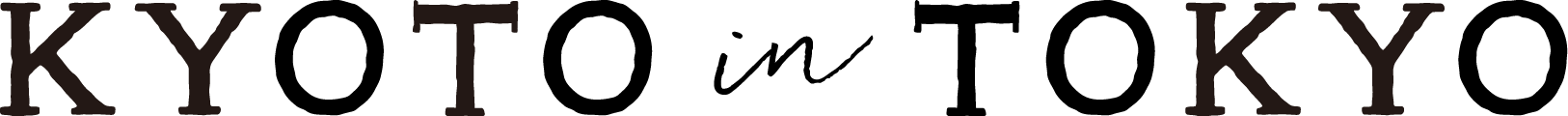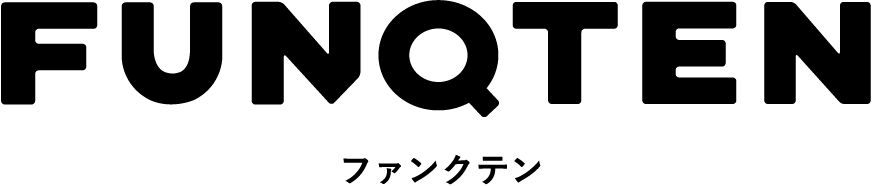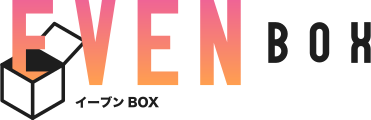忘れられた米子不動での初登攀の記憶|Study to be quiet #10
成田賢二
- 2023年02月07日
INDEX
稀に見る当たり年だった2017年の氷の記憶。あのときの氷を再び見ることは永遠にできない。消えた氷と、クライマーの残像。
文◎成田賢二 Text by Kenji Narita
写真◎宮田八郎 Photo by Hachiro Miyata
写真提供◎ハチプロダクション
氷の追憶
水という液体の凝固点が0℃前後というのは本当に天の配剤だ。なぜそうなったのか、僕はときどき心に問うてみる。この真理がなければ、氷河もないし、たぶん季節がない。世界の陸地のほとんどは海に没してしまうかもしれない。
たとえばこの0℃という気温と人間の性質の関係を考えてみる。0℃をまったく経験しない人々は、細かいモノゴトにこだわらなくなると思う。0℃を通年で体感する人々は、思想について無関心になるだろう。0℃を季節ごとに往来する人々は、たぶん涙もろくなる。実際に春と秋に二度、水盆から静かに水が溢れるように、僕たちの心は涙に満ちる。
登山は水の変態をたどる旅だ。それは雲でもよいし霧でもよい、あるいは額に流れる汗でもいい。晩秋のころ、陽だまりのハイクアップで流れ落ちた汗がベースレイヤーを濡らし、それが突如、稜線の風に吹き当てられて背筋を凍らせる。それは私たちが生きていることの証だ。と同時に、来るべき冬と死へのしみじみとした恐怖でもある。
僕たちが集う陽だまりにある生は、死という濃緑の木陰のすぐ隣にあっていっそう、その在り方を強く知ることができる。僕たちは山にあって、その陽だまりに漂う生を探しているのかもしれない。光と影を明瞭に切り裂く、この痩せた尾根道を歩きながら。
アイスクライミング

アイスクライミングなんていうとずいぶん難しく聞こえる。「クライミング」という言葉を辞書で調べると「手足を使って攀じ登ること」とある。アイスクライミングは手足につけた金属の道具だけを使うから正確にはクライミングではないかもしれない。実際にやってみるとわかるが、きわめて作業的な、仕事的な感じがするだろう。乾いた岩を登るフリークライミングとは相当かけ離れた内容なのがわかる。金属というものは仕事を単調化させ、同時に複層化させる。アイスクライミングは単調で、かつ手順の多い作業だ。フリークライミングでいうところの「ムーブ」や、奥の深い「ジャミング」などの技術はほぼない。重力とせめぎ合ったギリギリのバランスでの繊細な体重移動もない。単調に打撃と、そして爪先での立ち込みを繰り返すだけである。
だから簡単かといわれるとそうでもない。フリークライミングと違って氷の形は毎年変わるし、日々発達したり崩壊もする。気温や湿度により氷質も大きく変わる。そもそも本来なら流動しているはずの物体を登っているわけだから、リスクは大きい。
しかしそれゆえに氷は蒼く美しく儚い。アイスクライミングの魅力はこれに尽きる。もしかしたら、乾いた岩を登るフリークライマーよりは、少しだけ詩的な人間が行なう行為かもしれない。
米子不動

長野県須坂市に米子不動という場所がある。四阿山の北面にある古い爆裂火口であり、高さ100m程度の垂直壁が帯状に数kmにわたって延びている。この壁にかかる氷瀑がアイスクライミングの対象になったのは1984年ごろのことらしい。
夏には当然、氷はなく、名前がついている滝は米子不動の御神体である「不動滝」と「権現滝」だけだ。それ以外の滝は、なんだか少し壁が濡れているなあという程度のただの崖に見える。これが冬になると様相が変わる。標高からくる乾燥と低温、垂直の懸崖、そして適度な水量、これらの条件がちょうどマッチしたのだろう、国内では最大の氷瀑群を形成する。全部で十数本の氷瀑があるが、そのどれもが垂直に迫る傾斜と100m程度の高さを持っており、初級者向けというべきものはひとつもない。
アイスクライミングが少しできるようになっていた僕がこの場所に初めて来たのは2010年ごろだった。初めて「正露丸」(氷瀑の名前)に来たときは、その存在感に圧倒されて、尻尾を巻いて逃げ帰ったものだ。それから数年をかけてこの氷瀑を、なるべく易しそうなやつからひとつひとつ登っていったが、そのどれもが記憶に残る滝、思い出に残るピッチばかりだ。氷の形は毎年異なるものだが、僕はいまでも写真を見ただけでその滝がどの氷瀑なのかがわかる。あのときの強烈なパンプも、すんでのところで落氷を避けたハンギングのビレイ点も思い出すことができる。
味とも右

2017年のシーズンに、若いクライマーのKが僕に声をかけて来た。その年は11月に雨が多く、年明け以降も寒暖差が繰り返して順調な氷の発達を窺わせるシーズンだった。氷は単に寒いだけでは発達しない。適度な寒暖差と、軽く小雨でも降って表面が滑らかになったほうが登りやすい。
K「正月に『味とも』を登ったんですけど、その横になんか変なのができてるんですよ」
一般に米子不動のシーズンは一月中旬以降とされていて、正月ではまだ氷の発達が良くない。「味とも」というのは氷瀑の名前であり、その名前の由来は初登者が「味とも」というふりかけを好んでアルファ米にかけて食べていたから、らしい。
「味とも」は米子不動のなかでは水量が少なく、氷結のタイミングを捉えるのが難しい氷である。その「味とも」を正月に登ろうとする時点でKは相当変わっていた。彼は氷結して繋がっている氷に興味はないらしかった。いわく、登れるとわかっているものは、登る価値がないそうだ。切れ切れの氷で、乾いた岩のセクションをミックスして氷に取り付く妖しげな氷瀑のみが彼の登攀ラインらしい。
僕「なんだ? 変なのって?」
K「いやあ、行けばわかると思います」
Kは、本人も認めているが、ややアスペルガー的なところがある。社会性には欠けるが地形と冬山に関する考察は到底僕が及ばないことが多い。地形図を眺め、気象データの考察をしているだけで一日すごせる人間だ。数学科を出ているらしく数字にものすごく強い。こんなときは多くを尋ねることはせずに、呑気についていくことにしている。針の穴を通すようなことを平然とやる男だ。まさか死ぬようなこともないだろう。
浮かぶ氷
深雪をラッセルして「味とも」の真下に着くと、「味とも」は珍しく薄いながらも完全結氷していた。そしてその右にはたしかに見たことない氷が垂れ下がっている。「味とも」よりもずっと高さがあるらしく、最上段の氷はハングから完全に離れており、空間に浮かんでいると表現した方がしっくりくる。
僕「あれ……かよ!」
K「ですねえ……」
僕「登れんのかよ? 無理でしょ!」
K「『味とも』から見たら、登れそうでしたよ」
僕「マジかよ、カムあんの?」
K「あります」
少なくとも最上段に浮かんでいる氷に取り付くには、7mくらいは乾いた岩をトラバースしなければならないように見えた。岩登り用のプロテクションがなければトラバースできるとは思えない。Kはさっそくにザックからカムやらナッツやらをじゃらじゃらと引き出し、靴下に「貼るホッカイロ」を貼り始めた。
僕「なんじゃそりゃ」
K「コンペ用の靴なんで、インサレーション入ってないんですよ、だから寒いのでホッカイロ貼ります」
僕「そんなのアリかよ!」
K「最初の2ピッチはお任せします、成田さんならいけるでしょう」
コイツはどうも僕の実力まで正確に数値化して測っているらしい。面倒な下段2ピッチは僕に任せて最上段に向けて体力を温存させたいらしかった。
僕「まあ下はなんとかします。上は無理。ダメなら降りましょ」
K「はーい」
スクリューをジャラジャラと鳴らしながら僕は最初のピッチの氷を叩き始めた。薄く広がったスラブ状で、はじめはスクリューさえも決められなかったが、それも登るにつれ徐々に厚みを増していった。安定したテラスのある40m程度でピッチを切りKを迎える。
2ピッチ目、最上段に浮かぶ氷がかかっている大きなハングの下へと導かれる。いくつかの大きな段差を交えた氷で大変登りにくい。しかし氷の形状には少ないながらも弱点が見つけられる。これならいける、しかしぶっ立っているのは間違いない。傾斜を少しでも殺すべく、強傾斜の氷柱を右へ右へとかわしながら上を目指した。ハングの下の厚い氷の染み出しにスクリューを埋めビレイアンカーとする。下からは乗用車くらいに見えた最上段に浮かぶ氷は、ここまできて見上げるとマイクロバスくらいにまで大きくなっていた。遠くにある氷は実際よりずっと小さく見えるのを思い知ることになる。
最上段

Kはビレイ点に来る前にロープにぶら下がってよくよく最上段を観察している。
僕「どうすんのよ……」
K「思ったより離れてますねえ。へっへっへ」
これはあとになってわかったことだが、このKの不適な笑みは彼が心から楽しんでいる証拠である。困難と危険を高次元で精密に分類する能力が彼にはあるらしい。僕にはどう見ても恐ろしげな物体にしか見えない。登るなんてとんでもない。だって離れて岩から浮かんでいるのだから。重量に対して岩への接着面積が小さすぎやしないか。
Kはビレイ点に着くとザックからプロテクション類を取り出してハーネスにかけ始めた。腰にはノミック(ペツル社製のアイスアックス)に変な加工がされてぶら下がっている。あれ? おかしいな、両手にもノミックを持っている。
僕「なんじゃそりゃ?」
K「ノミックですよ」
僕「そんなの知ってる」
K「プロテクションですよ、両手離せないからハーケンなんて打てないですよ」
僕「そりゃそうか、で、そのヒモは?」
K「ショックアブソーバースリングです」
僕「……なるほど」
コイツはどうやらトラバースの中間支点でハーケンを打つのは無理だと読んで、別のアックスをもう一本持ってきて、それに衝撃を吸収するスリングを仕込んでプロテクションにするつもりらしかった。僕はいまのいままでKが腰にぶら下げたアックスの存在にまったく気づいていなかった。
僕「では、やはりいくのね……」
K「行きまーす」
空間の旅
まずKは少しトラバースしたところで青色3番のキャメロットを苔だらけのクラックに捩じ込んだ。これでKが墜落してもふたりもろともすっ飛ぶことはまずないようには感じた。それからさらにトラバース、やや下り気味となりランナウト、ようやく現れた細い凍った草付きに、例のノミックを深々と打ち込んだ。
K「なんか効いてそうに見えますけどね、ふっふっふ」
そこからさらに垂直±5度くらいでトラバース、アックスは岩へのフッキング数手を交えて茶碗ぐらいの苔玉にクランポンを置いたりしながら水平に移動する。ようやくKの右手のアックスが氷に優しく触れた。それは背中よりも2mほど後方であった。「ドゥン!」というあまり聞きたくない響きのある打撃音が私の場所でも感じられる。
Kは徐々に狭くなる氷と岩との間隙を、私のほうを向きながらステミングでせり上がり、氷に肉薄していく。アイスクライミングに立体的ムーブなんてものは存在しない、という僕の思い込みは、僕の拙い実力がつくり出した虚偽の壁であることを悟った。
やがてKは岩へのバックフットを最後にくれてからとうとう岩を離れ、レストを交えながら螺旋状に氷を右上していき、やがて見えなくなった。この間、プロテクションはなにもない。最後のノミックからロープは既に10m近く出ているだろうか。
これから20分間の気持ちをその後に思い出す度に、僕は手に汗が滲む。ロープは徐々に伸びてゆく。スクリューを打つ気配はない。
スクリューを打ったら最後、万が一にも氷が崩壊したならば、落下する数トンの氷とともに我々もお陀仏である。
だからスクリューは打ちたくない。しかしランナウトはまだまだ続くのである。最終的に17、8mくらいロープは出ただろうか。仮にKがフォールした場合とんでもない落下係数のフォールとなる。それをあのノミックと、泥クラックに捩じ込んだキャメロットの3番は止めてくれるのだろうか。仮に止めたとしても下の岩か氷に叩きつけらるのは間違いない。
仮になにごともなくKがトップアウトしたとしたら、当たり前ながら僕もこの恐ろしげなピッチをフォローしなくてはならない。最初は登らないでこの場所で待っていようかと思ったが、どう見てもラインがトラバースしすぎていて、Kが懸垂で降りてきたとしても私のところに着地できる見込みはない。つまりなにがなんでもフォローしなければならないということになる。
フォロー

Kの姿が見えない、しかしロープは確実に伸びていくこの時間は、僕にとってものっぴきならない時間だった。残されている選択肢のどれもが恐ろしい。僕は無心になって状況を虚ろに眺めた。果たして今日はうちに無事に帰れるのだろうか?
やがてロープが止まり、なにやらスクリューを打っているような気配がする。スクリューを打てるほどに氷は安定してきたのだろうか? その後またロープは伸びてようやく「解除」のコールが木霊のように遠くで聞こえた。間をおかずロープは引かれる。
「いっぱい!」
いっぱいなのはロープではなく僕の心であった。意を決してビレイアンカーのスクリューを抜き、トラバースにかかる。ラインが下り気味なのでリードよりフォローのほうがずっと怖い。2本のロープはとんでもなく妖しげな、空間に浮かんだ氷に絡みつくようにして私へと続いている。青のキャメロット、そして例のノミックを回収すると、あたりには安定しているものはなにひとつとしてなくなった。すべてが重力に逆らっている。
「恐ろしい」
Kはミックスクライミングのエキスパートである。僕はクラシックな山屋であり、現代的なプラスチックトレーニングは行なっていない。山は登れるところを探して登ればいい。これは僕のラインではないだろう……。
僕はKの動きを思い出しつつ、ひたすらに夢中でよじ登った。体の動きはどうということでもない、岩登りなら普段からやっている動きだ。しかしそれをこの大空間と、浮かんでいる氷の狭間でやることになるとは……。
恐る恐る氷にたどり着くとほとんど舐めるようにしながらKの打撃痕にアックスを引っ掛け、わずかでも氷に衝撃を与えないように、はち切れんばかりの鼓動を感じながら、静かに、穏やかに登った。クライミングというよりは、実態のない空間を旅するような感覚だった。やがて立体的な氷は終わりを告げ、いつもの垂直と平面の世界に戻った。それにしてもぶっ立ってはいるが、間違いなく落ちないで登れるという見込みがたった。最後のスクリューを回収し、水流がわずかに見えている滝の落口を越えて、ようやく僕はKの待つ潅木にたどり着いた。
K「いやーお疲れさまでした」
僕「大概いままでに氷は登ったつもりだったけど……小便もらしたかもしれない」
K「ふっふっふ」
僕「これ、地面に戻れるんだろうか?」
K「所詮、全体としてはかぶってないですから大丈夫ですよ」
僕たちは先ほど登りきった浮かぶ氷を横目に眺めながら、ギリギリ2回の懸垂下降で地面に降り立った。
取り付きではあとから撮影に来てくれたM氏が、暖かいお茶を用意して僕たちを待ってくれていた。
M氏「やりおったなあ! なんか登っちゃあかんとこ登ってたで!」
ひとまずのところ僕は、仮面みたいな苦笑を浮かべることしかできなかった。
後日
この登攀には後日談がある。
僕「やっぱり初登なんだから、米子不動に相応しい名前をつけたほうがいいだろう、隣がコブラとか龍神とかなんだから」
K「えー、そうですか? 別に名前なんかなくてもいいんじゃないですか?」
僕「いやいやそりゃまずい、『深海』ってのはどうだろう?深海に浮かぶクラゲ。アイツのイメージにぴったりじゃない?」
K「えー、どうでもいいんじゃないですか? じゃあ『味とも右』で」
このラインを見出したのも、実際に核心をリードしたのもKの見識と実力であり、僕にはなにも決める権利がない。
私が小便を漏らしそうになりながら、必死にフォローした浮かんでいる氷は、「味とも右」というおよそ冴えない名前ということになった。おそらく今後もだれからも注目されないだろう。その後も相変わらず米子不動に通っているが、あの年並みに「味とも右」が発達したのは見たことがない。
あの日のクライミングが幻のように思える。しかしその映像と記憶は、たしかに脳裏に残っている。
SHARE