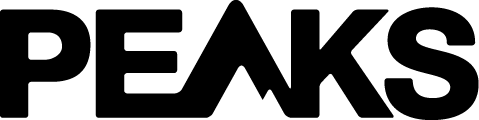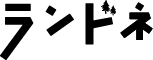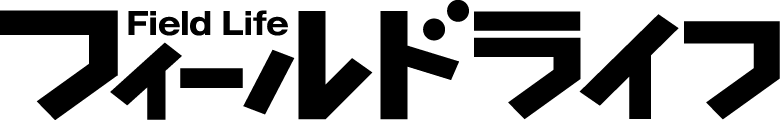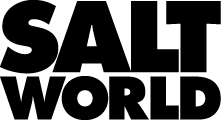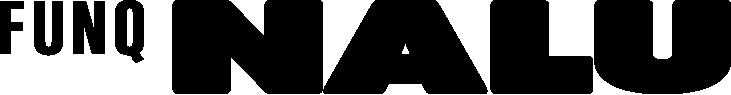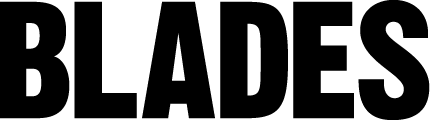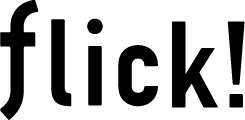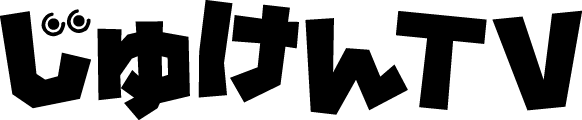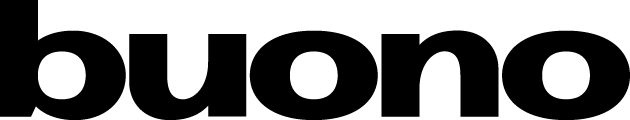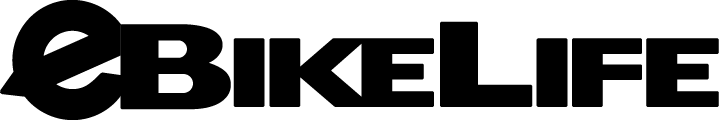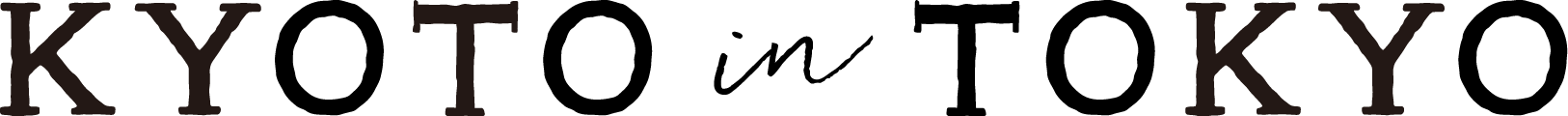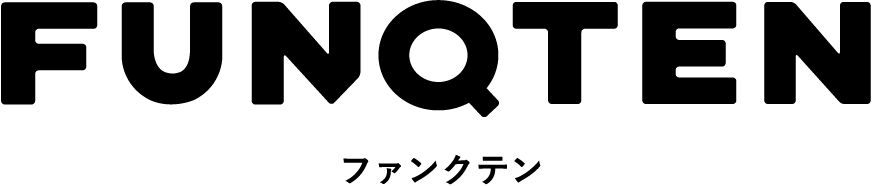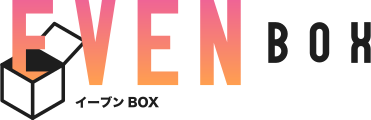谷川岳 幕岩Cフェース「シーラカンス」のこと|Study to be quiet #11
成田賢二
- 2023年03月31日
INDEX
文◎成田賢二
写真◎三苫 育
現象の霧のなかで
雪国の春の谷底を歩いていると、カモシカの亡骸に遭遇することがよくある。場所と状況から考えて、雪崩に流され埋められたものだと思う。私は厳冬の雪山のなかで、彼らがとんでもない急斜面を水平に横切って走っていくのを幾度も見たことがある。あのような深い冬の山で、雪に埋もれた地衣類や苔を食べて生をつなぐ彼らに向けても、自然の摂理はんなんのためらいもなく訪れる。あのカモシカの亡骸は、私の亡骸であってもいささかの矛盾もない。生と死の間にあるのは、紙一重というよりは、なにか霧のようなものが漂っているだけに見える。
登山者とは、その霧のなかで向こう側の死が決して目に見えぬように、堅固な石垣を積み上げる、という類の人ではないと私は信じている。
私はもう少しこの狭い山頂で、夜露に濡れ、寒さに震えながら、その霧を風が払ってゆくのを待ちたい。この星に宿命付けられてしまった現象が、生と死を、寸分の狂いもなく静かに分けてしまう瞬間を、もう少し近くで観察したいと願う。それが登山が持ちうる本当の性質であってほしい。その霧の生態を知ることで私たちは、私たちが築いた社会がつねに忘れさせようと迫る、むせ返るほどに懐かしいはずの「生」を、再び思い直すことができる。
私は垂直の氷に打ち込んだ金属に私の体重のすべてを預けながら、そのことをいつも思う。
ヤマレコより

Kがまた、なにかが凍ってると電話口でゴニョゴニョ言っている。昨日のヤマレコにどこかの登山者がロープウェイから谷川岳に登った記録があり、そこに投稿された一枚の写真の背景に、完全結氷したように見える「シーラカンス」の氷が映っていたらしい。
毎回のことではあるが、Kの考察は微に入り細を穿っている。一体だれがその氷の存在を探して、無数にあるネット上に投稿された写真の背景に、目指す氷の姿を探すだろうか。南国土佐の生まれのこの男は、中学生のころから地形図を見ることを第一の趣味としていたらしい。氷が存在してる谷、その標高、壁の向いている面、それらを全て把握している。間の抜けた私の質問にも、澱みのない答えを持っている。
私「シーラカンス? そういやそんな氷あったなあ。なんだっけシーラカンスって、魚? 爬虫類だっけ?」
K「いやいや、絶滅したと考えられてた魚です。いまもちゃんと生きてます。先週見たときは薄そうでとても登れる状態ではなかったです。ちなみに明後日が高曇りでベストです。もうこれ以上の登攀日は来ないと思います。というか、何年か前から観察してますが、氷がこんなにできているのは見たことないです」
私「えーそうなの? なら行かなきゃなんないじゃん。つーことは明日の夕方には出なきゃならんってことよね……。子どもの迎え頼まれてるがなあ。まあ仕方ない、行くだけ行くか」
深夜

早朝登攀に照準を合わせて、私たちは翌日の深夜から谷川温泉を歩き出した。
当時ドローン撮影に凝っていた仲間のMが、こんな時間からカメラを持って付いてきた。
その途中、暗闇のなかで先頭を歩いていた私の5m先を、イノシシが深雪でモゴモゴしながら走って逃げていった。当時狩猟を始めたばかりだった私は、持っていたアックスを片手にそいつを追いかけたが、もう少しというとこで逃げられ、最後にアックスをイノシシ目がけて放り投げたが当たらなかった。
K「惜しかったですねえ、ふっふっふ」
私「いまのは惜しかった、つーかこんな雪多いとこにイノシシいるのかよ」
二俣で登攀支度を整えていると夜が白んできた。谷川岳を越えてきた風が雪面を吹き抜けて、裸の岳樺を揺らしている。撮影していたMはここでドローンを飛ばすという。ちょっと風が強くて微妙だがまあなんとかなるさと、岳樺の下の穴に待機用の雪洞を掘り始めた。
私とKは夜が明け始めたオジカ沢支流の急峻なルンゼを登り始める。シーラカンスへと続くこのルンゼはとにかく急峻で、よくこんなところに雪が留まっていられるなと思うくらいの傾斜だった。なにかが落ちてきたらおそらく逃げようもなかろうが、とりあえずいちばん右端の岩壁の際を恐る恐る登るしかなかった。500mの標高差を詰めるにつれて、正面にシーラカンス、左に一回り小ぶりな氷瀑、「ピラニア」が見えてきた。
氷の着地点まで登り詰めると、氷の裏側は洞窟状の空洞になっていて大変居心地がよい。
私「さて、さっさと登って早く降りてこよう」
K「初登者は上の雪壁も抜けてます。当時の道具と技術では、おそらく下降できなかったかもしれません。でも残置ボルトも使ってるはずだから下降もできたと思うのですけどね」
幻の氷

1ピッチめはK、傾斜は立ってはいるが凹角もあり、そんなに難しくはなさそうだ。しかしどうみても蒼氷とは呼べない、雪を噛んだ白い氷でよろしくない、まあ急いで登ればなんとかなるかとさっさと取り付く。
強傾斜を越えて右に回り込み、悪氷の氷柱状を2段越える。40mほどロープが出たところでスクリュー2本でビレイ。2ピッチめ私、今度は稲妻型に左上へと、氷柱を縫うように避けて登る。氷質はいよいよ悪くもはやアイスクライミングとは呼び難い。手足四点のどれかが不意に切れたとしても墜落しないような、スタティックな登りが求められる。最後の核心ピッチをKに託したころには完全に日向に入り、サンサンと太陽が照りつけて恐ろしく暑くなってきた。
「全然高曇りじゃねえじゃねえか!」
私はKが不在のビレイ点でさんざん悪態をついたがもう遅い、アンカーにしていたアイススクリューは手で押したらカタカタと動き始めた。おちおち体重を預けてもいられない。
「マジかよ、一刻も早く抜けてくれ!」
そう願っては見たものの、視界にKは見えず、ロープは案外と伸びてゆかない。祈るように何回目かに上を見上げると、なにか金属的なものがロープに誘導されるように私の目の前に落ちてきた。
スクリューがクイックドローとセットでひとつ、ロープにぶら下がっている。一瞬どういう状況なのかが理解できなかった。
「日射でスクリューが抜け落ちてる!」
私はすぐさま私がハンギングしているビレイ点のスクリューの全てを、場所を変えて打ち直したがそれらはわずかな時間稼ぎにすぎなかった。みるみる目の前のスクリューはその自重だけでハンドルを下に向けて私側に倒れてきた。手で引き抜くと恐るべき縦の楕円形の穴が並んだ。
「もう待てない、行くしかない!」
50mほどロープは出た、しかし待てど暮らせどロープは進まない、距離的にはもう抜けてそうなものだが?
私は覚悟を定め、なりふり構わず登り始めた。目の前のロープは当然弛む。それを肩に巻きながらグズグズの氷を登っていると、またしてもヌンチャクとスクリューのセットが金属音を立てて目の前に落ちてきた。
ありえない。この場所にいると間違いなく30分以内に死ぬ。
狂ったようにグズグズの、もはやシャーベットと化した氷をガサガサと登っていく。それにしても傾斜は十分すぎるほどあって、Kはほとんどなんのプロテクションもなく垂直の雪壁を登っていたことになる。いや、あったはずのプロテクションは私のハーネスの前に仲良く並んでいる。実際一度は足元の氷がバカっと崩壊して私は完全に足ブラになった。
「あいつはバカか!」
こんな状況でクライミングを続けるKの神経は確実にイカれている。というか私たちはいま、確実に死の淵にいる。
ようやくロープが引かれ始めた。私は肩にかけたロープをバラしつつ、もはや雪とも氷とも呼べないシャーベットを叩き落としながら、その奥にあるわずかにまともな氷を掘り出してアックスを決めた。滝の落口へとトップアウトして右手を見ると、Kはあまりにもか細い小指くらいの潅木、というかほぼ草みたいなのの下のわずかな足場でロープを手繰っている。
私「それかよ!」
K「支点ないんすよ! どこにも! 敗退も無理!」
下降

たしかにあたりは一面の雪壁で下降に使えるものはなにもない。それでいてこの場所は、どう見ても湿雪雪崩の通り道である。このときになって初めて私たちは、三十数年前の初登者がトップアウト後に幕岩尾根まで雪壁を登り詰めたことの理由を知った。それは考えられないほどの時間のロスだし、全装備を背負って登ることになる。でもそうでもしないことにはこの氷は、当時の技術では下降しにくかっただろう。そして完全にこの雪壁をトップアウトすることが、初登の使命であるという当時のクライマーたちの空気感がまざまざと感じられた。しかし今日の私たちは食糧も水も取り付きに置いてきてしまっていた。そしてこの快晴のなか、南向きの急峻な漏斗状の地形を登るほど、私たちは時代の空気感を背負ってはいなかった。
私「どうするよ!」
K「スクリュー捨てるしかないですね……」
私「捨てりゃあなんとかなるか……」
とりあえずいまいる場所の支点は雪のなかにかすかに良質な氷を探し当てて、2本のスクリューに加えてなんとかまともなV字スレッドを作ることができた。
K「15分くらいなら持ちそうですね、ふっふっふ」
問題は下の段だった。先程まで一刻も早く離れたいと死ぬほど願ったその場所に、私は再び降りて行かざるをえなかった。日射は相変わらずだが、幾分風が出てきて氷が乾き、融解の進行はわずかに時間を稼いでいるように見えた。
「こんなものは捨てちまおう」
私は表層にある使い物にならないグズグズのかき氷を叩き落とし、手元にある切れ味の悪そうなスクリューから4本を選んで、なるたけまともに見える氷に埋めてその全部をスリングで連結した。急げとばかりにふたりが間髪を置かずに取り付きに懸垂で舞い降りた。全てが知らぬ間に許容範囲を越えていた。
K「いやーデンジャラスですね……こいつは」
私は、南に向いている氷は金輪際、決して登るまいと心に誓った。降りてきて気がついたが、首元から入った大量のシャーベットがパンツまで身体を濡らしていた。
夕暮れを待つ

しかしこのままこの急峻なルンゼをノコノコ下って行くと、シーラカンスの大崩壊に巻き込まれる恐れが十分ある。
私「待つしかないべ」
K「陽が落ちるまで待ちましょう」
私たちは先ほどまでの死の恐怖から逃れた安堵感に浸っていた。そして同時に、幕岩がシーラカンスとの間に作った雪の洞窟の端のほうでシーラカンスの崩壊に怯えながら、太陽が通りすぎるのをひたすら待った。
K「この氷の場合、陽が陰る15時以降に登るのが正解ですね、いや、夜間登攀かな。ふっふっふ」
私「もう金輪際、二度と来ないね」
やがて陽が陰り、十分に気温が下がったのを見計らって私たちは速やかにルンゼを駆け降りた。シーラカンスは、高曇りの予報に反して快晴だった今日という日には、ついに崩壊はしなかった。一体コイツの生態のバランスはどうなっているのか。
後日談
この登攀には後日談がある。谷川岳は、登攀日の翌日は天気が悪かった。翌々日朝に撮影された、例のヤマレコの写真には、既にシーラカンスは消えてなくなっていたそうだ。シーラカンスは晴天に耐え、悪天に耐えられなかったらしい。しかし化石と思われていたはずの生態は、あの日にはたしかに悠然と深海を泳いでいた。
初夏になったらだれか私が捨てたスクリューを探しにオジカ沢へ行ってみてほしい。私にはそれを探しに行くだけの気力がない。山に道具を捨てたことだけが心残りである。敬意を表して進呈させていただく。研げばまだまだ使えるはずだ。
SHARE