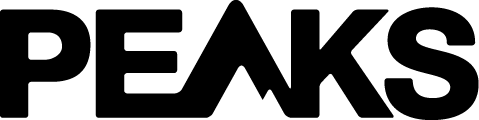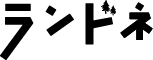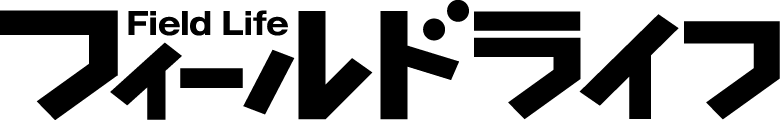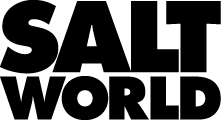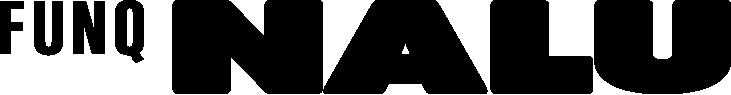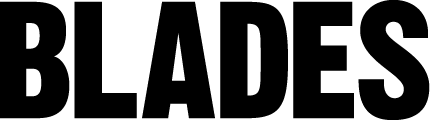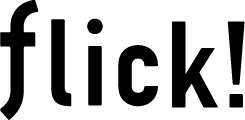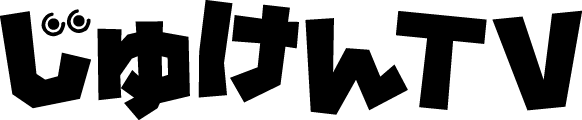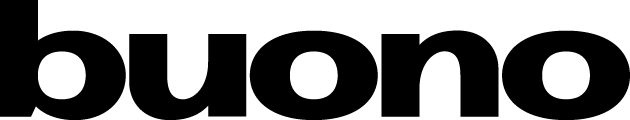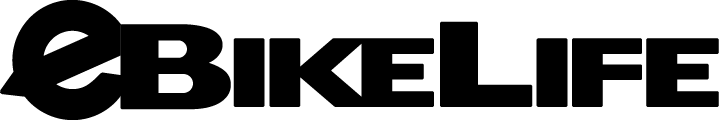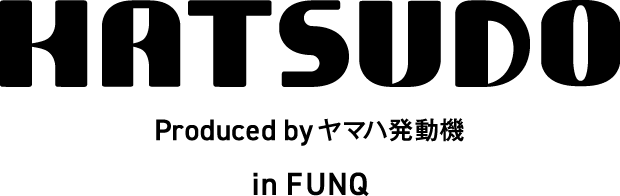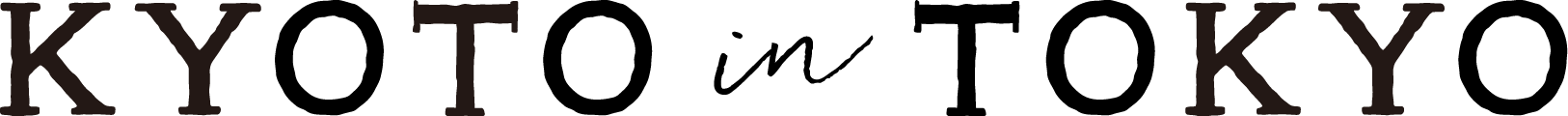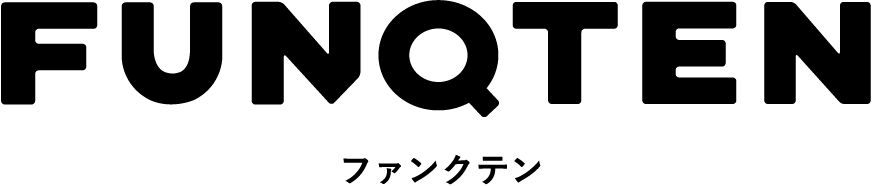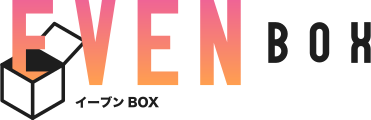奥利根の春、僕たちだけの白いキャンバスを探し求めて|Study to be quiet #12
成田賢二
- 2023年05月15日
INDEX
文・写真◎成田賢二
降雨
僕たちは三国川ダムの麓の公園に前夜集まった。冷たい雨が降り続き、霧がダムを隠していた。公園にあるあずまやで雨宿りをしていると、屋根から流れ落ちる雨だれが、残雪をまだらに溶かしている。
明日はまあ予報どおり晴れるんだろうと話してから、それぞれの車の後部座席で、僕はスキー板と並んで寝袋に潜り込んだ。見慣れたスキー板のデザインと、見慣れたスキー板の傷跡が目の前にあった。僕は静かにその傷跡を撫で、それからスマホの光を最大限に弱くして地形図を眺めた。この雨はどのあたりの標高から湿雪になるだろう、風はどんな風に雪を再分配するだろうか。
夜中も木々のざわめきと、車の屋根を叩く雨音が絶えることはなかった。予想以上の冷え込みで、予定の5時よりも早く寒さで起こされる。車のなかの金属的な冷え込みが身体の表面を覆っていた。慌ててエンジンをかけ、テルモスからぬるくなった湯を飲む。スマホを立ち上げて、前夜まで眺めていた地形図を再びじっくり見つめる。Fの車にも灯りが点った。雨上がりの霧に包まれながら窓越しに会話をする。
F「降っちゃいましたねえ、寒い!」
僕「どの辺から雪かねえ」
F「どうします? 行きます?」
僕「まあ行って考えるしかないよねえ、雪が悪ければ尾根を滑るしかないか」
僕たちはノタノタと起き上がると、霧に煙る濡れた草の上でスキーにシールを貼った。晴天を選んで登山口まで来てみると、それは降雪直後だったということはよくある。幸福と恐れ。降ったばかりの雪への不安、そしてそれと同量の期待がないまぜになって霧に溶ける。
霧氷

デブリで埋められた十字峡への道路を、スキー板を履いてポツポツと歩き始める。対象を持たない茫漠とした恐れが静かに鱗を落とし、雪の匂いを吸った心がしっとりと山に向かっていくのが感じられる。僕たちは山でしか取り戻せない懐かしい感情を山に来ては思い出すのだが、それらは普段、胸の奥底にあって手繰り出せないものらしい。霧が山からゆっくりと離れ始めると、はるか標高の高いところに真っ白になった霧氷が観察できた。山が見せる微かなニュアンスさえも、僕は欺かれることなく読み取ろうとする。
僕「積もった、のか?」
F「なんか霧氷だけな気もしますよね……」
僕「あって20、吹き溜まりで30くらいか」
F「だといいですけど……」

十字峡からの急峻な登山道はまだらに姿を現しており、スキーを背負うことになる。春を告げるスキーの重みが、今年も背中にかかってきたことを感じる。
足下の陽だまりには既にイワウチワが開こうとしている。雪にへし曲げられている蕾をつけたマンサクが、朝日に重荷を解かれて飛び跳ね、僕たちをおどろかせる。日向で惰眠を貪っていたヤマドリが不意の侵入者におどろいて飛び立つ。
振り返れば桑ノ木山、その向こうに巻機山北面の広大なオープンバーンが見えてくる。登山道が完全に雪に埋もれたところでスキーを履いた。高度を上げた陽射しが木々についた霧氷を溶かし始め、サラサラと、乾いた氷のかけらが斜面を流れる。額から流れ落ちる汗がサングラスを濡らして視界をぼやかし、やがて雪面に落ちる。
避難小屋

日向山の直下で霧氷はどうやら積雪に変わっていた。かろうじて雪の姿をして地上に舞い降りることができた彼女たちの変態は早い。
中ノ岳直下で再びスキーを背負いクランポンに履き替える。春をまとった水蒸気はこの辺りから突然に冷気に当てられて結晶化し、僕たちの視界を閉ざす。わずかに雪から頭を出している中ノ岳の標識を見つけると、次は避難小屋を探す。秋の紅葉のときには度々訪れた、見慣れたはずの中ノ岳避難小屋だが、3月にはその姿は全く見えない。
僕「こんなに埋まるもんかなあ」
F「これは見つけるの難しそうですね」
僕「避難小屋だから必ず二階の窓の鍵は開いてると思うんだ」
雪面にトタンの角がわずかにのぞいているのをFが見つけた。少し掘り進めると、軒下の吹き溜まりの裏に空間があることがわかった。私は西側へ、Fは南面を掘り進める。
F「やったー、窓開きそうですー」
僕「まじ! やったじゃん!」
小屋の非常窓はもっとも雪に埋まりにくい南東の角に付けられており、設計者の見識に感服する。Fが開けたその窓は、スコップでの破損を防ぐためにガラスではなく樹脂でできており、乾いた音を立てて軋みながらそのサッシが動き始めた。頭からその窓に潜り込むと小屋のなかには4カ月分の沈黙と停滞がこもっていた。
僕「いや、開いたねえ、どうするよ、一本滑って下の沢床でテント張りたいとこだけど、もはや視界もないことだし、泊まっちゃう?」
F「というかもはや時間的に泊まる以外の選択肢はないですよね」
僕たちは中ノ岳から駒ヶ岳へのスキーでのツーリングを目指していた。駒ヶ岳に行く途中の稜線には檜廊下という針葉樹に覆われた痩せ尾根の樹林帯があり、尾根通しに滑ることはできない。その代わりに南北に連なる中ノ岳と駒ヶ岳の東面には氷河地形と呼ぶべき沢が随所に見られ、それらとその間にある尾根を登り下りして駒ヶ岳まで繋げようという小粋な試みだった。
快適な、しかし真っ暗な小屋のなかにザックを押し込んで小さなテントを張った。小屋に置いてある銀マットをていねいに敷き詰めると、快適な一畳一間が出来上がった。僕たちはきれいな雪を集めて水作りをしながら明日の予定を呑気に話し合った。
僕「太陽ってすごいな、この山の雪全部溶かすのにガス缶何個必要かな」
F「快適すぎてやばいっす、マットなしで寝れそう……」
僕「坂倉沢滑って北に乗越越えて、左岐沢滑って右岐沢登って、乗越越えて滝ハナ沢の左俣滑って中俣にある滝の横を登って、それから駒まで歩いて、オツルミズ滑って駒の小屋で泊まって大チョウナ沢滑って百草池に登り返して白沢滑って銀山平に出れんかなと」
F「……完全に迷路ですね……迷路というかあみだくじ……」
僕「迷路なのよ、すんなり行けるかわかんないけど、なんとかならんかなあ」
F「僕のシール、粘着力持たないかもしれないです……」
僕「オレはグルー張り足してきたからたぶん大丈夫だ」
停滞

翌朝は予報に反して全く視界がなかった。入り口に立てたスキー板にはエビの尻尾がびっしりとついている。
二度寝を決め込み、1時間おきに外に出るがようすは変わらない。午後は暇を持て余して狭いテントの中でマッサージ大会となった。おかげで僕はFの筋肉の量と質についてよく知ることができた。その頼もしさを知ることで、いつもあやしい雪質の急斜面に先頭で切り込んでいくFへの信頼感は少し高まった。下山日を一日延ばすことになり、食事を少し切り詰めることとする。睡眠たっぷりで迎えた翌朝も再び視界はない。
僕「なんだよ! ダメじゃん!」
F「白馬行ってる友だちは昨日から晴れてるって言ってます……」
僕「やはり銀山平はわずかな寒気でもガスが引っかかるねえ……北面は無理ですかなあ」
9時ごろになってもガスは切れない。試しに小屋からアックスを持って北面へ歩いてみるが、随分下まで降りないと吹き溜まりはないらしく、硬い雪が緩む気配はまったくない。とりあえず南面に標高を落とすことにする。
僕「兎まで行ってさ、巻倉滑って大水上に上がって水源碑から深沢滑って丹後山に上がるべし、あの辺はどこでも南向きの急斜面のデブリ以外はスキー場だから大丈夫。君だけのプライベートゲレンデです」
F「視界ないプライベートゲレンデ……」
兎のコルに下り始めると標高1,800mくらいまでは雲がかかっていないらしいことがわかった。どうやら霧に巻かれていたのは僕たちだけだったらしく、朝の2時間を無為にすごした僕は地団駄を踏んだ。コルに着くとガスが流れ中ノ岳がようやく見え始めようとしていた。
僕「これはいいんじゃないか? ほれ、あそこに見えてきた兎の北面オープン、どう思う?」
F「あれはデカいっすね、沢筋だけ新雪ありそうですね、あそこに着くころには緩むと思います!」
僕「どうかなー、あそこ昼の日射角悪いよなー」
兎岳の北東面は北ノ又川源流随一のオープンバーンといえるだろう。しかしいまここから見る限りでは、昼になっても雪が融解と凍結の刃の上を彷徨うように感じた。
スキーアイゼンをガチャガチャと効かせながら兎岳の山頂でシールを剥がす。この山行、3日目にしてようやく最初の滑降なり。
滑降

F「では頂きます!」
僕「やっとなのかー」
ガリガリガリー。
僕「だれだ緩んでるって言ったのは! 見る目なさすぎ!」
F「すみません……ハズレました……暖かくなってきたと思ったんだけどなあ?」
僕「2時間早いな、しゃーない南面に踏み替えるべし」
兎岳の南面では15cmほどの真新しい湿雪が霧混じりの弱い陽射しをじんわりと受けている。真綿から数本の糸を選んで抜いたかのように雪は緩んでおり、密度が高く滑らかで、かつしっかりと下支えの感じられる雪質であった。歓喜の声がスキーヤーから響く。
F「これは最高すぎますね」
僕「やっぱ南面だったか、北アルプスとは違うよなあ、来年は駒から南下することにしようか」
3月の越後のスキー旅は、豪雪が吹き溜められた東面に限る。日々高度を上げる命の息吹を帯びた3月の太陽光。無尽に緩急を繰り返す山の傾斜。遮蔽物となる尾根とそれが織りなす日照率の明暗。それらの因果が矛盾なく雪の表情に応報する。それらを探るために与えられた僕たちの時間はあまりにも短い。

大水上山の南面も同様に濃密な湿雪で、僕たちは奥利根の春を心ゆくまで味わった。そして夕焼けを追いかけるように丹後山の東尾根をハイクアップした。たどり着いた丹後山避難小屋は中ノ岳に比べたら拍子抜けするほどに、小屋は玄関までもが雪の上に出ていた。雪囲いを外してなかに入ると夕焼けに照らされた小屋のなかは暖かい斜光に満ちていた。
僕「昨日までの穴倉生活とはえらい違いだが」
F「これは最高すぎますね」
僕「君はそれしか言えんのか」

奥利根本谷

翌朝はのんびり起きて、お茶を飲みながら雪が緩むのを待つ。越後沢を偵察するか奥利根本谷を見に行くかで迷ったが、今回は奥利根本谷にある大利根滝を見に行くことにした。
僕「何年か前の夏に登ったけど、たしか20mくらいの直瀑だったような。今年雪少ないから埋まってないと思う」
F「そーなんですか、この時期登れるんですかね?」
僕「全くわからん」
朝日を浴びた丹後山東面に歓声を上げたあと、ダケカンバとブナの継ぎ目を注意深く探す。三角形に尾根へと伸びたブナ林のツリーランを見逃さずに味わいながら、ゆっくりと谷へと降りてゆく。標高を落とすにつれ徐々にデブリの爪痕が深まる。そのデブリ斜面に共通した一貫性を僕は探す。丹後コボラ沢の滝壺では小さな釜が口を開けており、最後は両岸切り立ったゴルジュ状になるがスキーのままかろうじて本谷まで下りることができた。下り立ってすぐ左を向けばそれが大利根滝であった。

F「これっすか!」
僕「これか? これ、だなあ。やはり今年は埋まってないんだなあ、近づいてみるべし」
F「なんか右のほう登れそうです!」
そう言いながらFは八割ほど雪に埋もれた大利根滝を、板を担いでスルスルと登っていった。
F「登れちゃいましたね」
僕「いや本来埋まってなきゃならんのですよ」
僕たちは雪に埋もれた奥利根本谷の最源流をカチャカチャとシールを効かせて歩いた。群馬県の最北、南魚沼の雪が一手に吹き溜まる、ポケットのように穏やかに孤立した地形であった。今回のスキーツアーの終着駅はきっとここなんだろう、僕は盆栽のように精巧な枝先を持ったダケカンバの樹形を見上げながら、静かにそう思った。それは全く予定表にはない場所だったが、3月の利根川の最源流には、気持ちに楔を打たせるような穏やかななにかがあった。
僕「いやー奥深い。夏はここまで来るのに沢登りで4日かかるんだけどなあ、スキーだと速いねえ」
F「今回も4日目ですけどね……」
僕「そうだったな……」
再び丹後山に立つと、対岸の大水上山の丸みを帯びた南斜面に、僕たちの昨日のシュプールを望むことができた。濃紺の空の下にくっきりとつけられたそのシュプールからは、いまも彼らの歓声が響いているようだった。僕たちはまた僕たちだけの無垢な白いキャンバスを探しに奥利根へ来るだろうと強く思った。雪は厳寒の孤独に降り積もり、そして春になってもなお温みゆく孤独を耐え続けている。地形の彫刻を眠らせる降雪という現象に、大胆明朗な滑降でスキーヤーが息吹を与える。そしてそのスキーヤーは精緻な観察力を持った、深雪の苦難を少しも厭わぬ本当の快楽主義者であってほしい。僕はその矛盾のなかに自由な旅があるのだと思っている。

SHARE