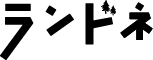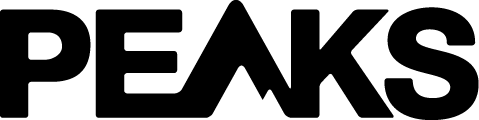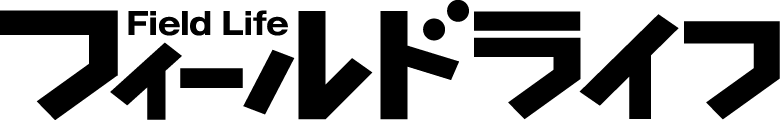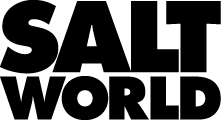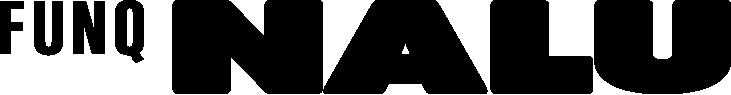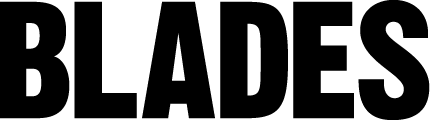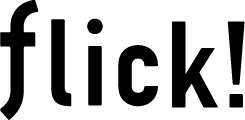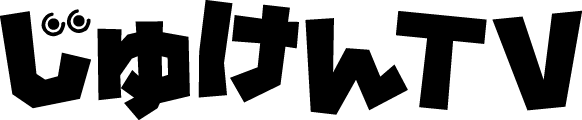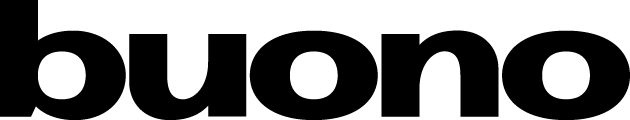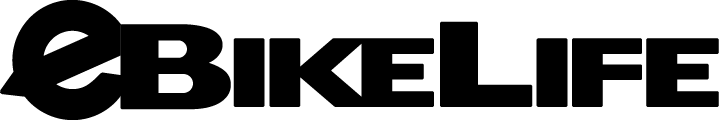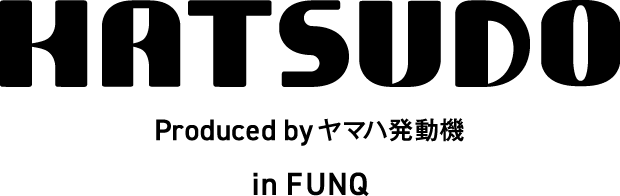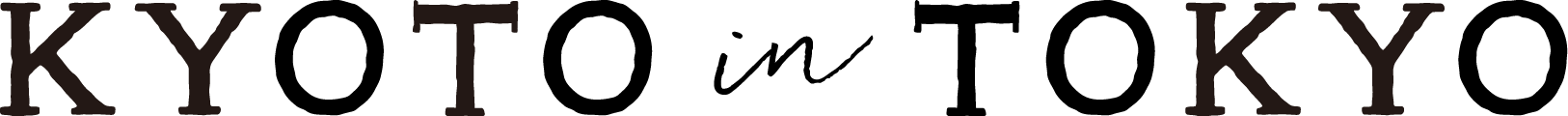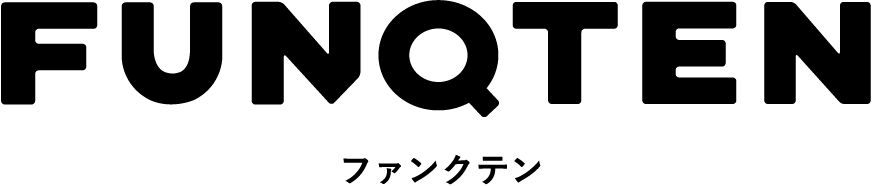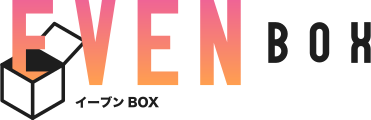明美が、携帯を出して
まわりの杉林の写真を撮り、
それから、私をふり返って言った。
「透子、昔より、少し話しやすくなったかも」
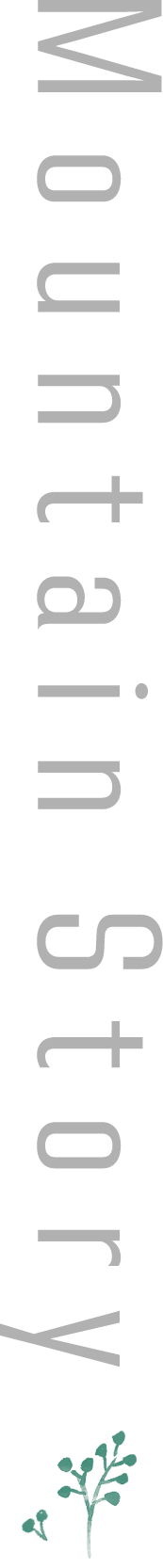
高尾山に向かう中央線で、明美はしゃべり続けていた。
「このニット帽、この春の新作なんですよ」
「へー。落ちついたオレンジ色で、いいね。おしゃれ」
「ですよね。あと、柔らかくて肌触りもいいし、あったかくて」
となりに座る貴子先輩が興味津々に話を聞いている。
ふたりに挟まれている私は、気の利いた言葉が出ないまま、うなずいて笑顔を作っていた。
7年ぶりに明美がイベント企画課に戻ってきた。「歓迎祝いも兼ねて、行く?」と課長の貴子先輩に言われて、「はい」と答えたら、「いつ空いてる? 今度の日曜とか?」と聞かれて、トントン話が進んだ。私としては「そのうち」のつもりだったのだけど、いつも自分の気持ちをはっきり言えないまま、なんとなくまわりが決めたことに乗っかって動いてしまう。
「明美ちゃん、企画書を部長に定期的に出していたでしょ? さすがだよね。こっちに戻ってきてくれて、ほんっと、心強いよ」
先輩が言うと、明美は手をひらひらさせながら「そんなことないですよ」と笑う。
明美と貴子先輩のこのやりとり、もう何度聞いただろう。私はといえば、最近企画が書けていない。ゼロ、だ。アイデアが何も出てこない。この「歓迎会」は貴子先輩が「ふたりともおない年だし、同期だし、これを機に、ね」と言ってくれたのは、つまり私が少しでも明美に追いつくように、明美からいい刺激を受けるように、と気遣ってくれたことがわかるだけに、自分でも情けなくなる。
外の景色は、緑が多くなってきた。
高尾山口駅に着くと、電車からいっせいに、バックパックを背負った人たちがホームに流れ出した。
私たちも階段を下りて、改札に向かおうとしたそのとき、貴子先輩の携帯が鳴った。
「どうしよう」と貴子先輩は携帯の画面を見てから、私と貴子に向かって「ごめん。私、帰るわ」と言った。
「息子が熱を出して、夫もこれから仕事で。ほんとにごめん!」
反対側のホームに電車が滑り込んできた。先輩は「じゃ、ね。ふたりで楽しんでね!」と急いで言うと、カカトを返して階段を駆け上がって行った。
あっけに取られて先輩のうしろ姿を見送る私に、「いこっか」と明美が声をかけてくれた。
ふたりで高尾山、か。
歩き出して、少しのあいだ、私たちは黙って歩いた。
「山のブランド、詳しいんだね」
私が口を開くと、
「今日のために買っただけだよ。これで、先輩との話題がひとつできるじゃん」
明美は、ニット帽を被り直した。縞々のグローブも、白のアウターも、よく見ると全部違うブランドだ。どれだけの時間とお金を、準備にかけたのだろう。私は、山で使うのは機能重視で、色やデザインなんて考えたこともなかった。まして、話題のためなんて……。
「仕事熱心だね」
自分の言葉にドキッとした。嫌味に聞こえただろうか。明美はフッと笑った。
「相手にちょっと合わせるっていうのかな。それも楽しいよ。昔は、あたし、うるさかったでしょ? 自己主張の塊っていうか。ま、あのころは自信もなかったし」
たしかに、あのころ、明美は、声が大きくて。ちょっとうるさかった。7年前、私たちはおなじイベント企画課にいた。当時から私は貴子先輩とチームを組むことが多く、明美は中堅の加藤さんと組んでいた。新入社員の憧れの的だった、加藤さん、だ。30代半ばで、クールで仕事ができて、わからないことがあると親切に教えてくれた。一度、私がひとりで残業していたとき、声をかけてくれたことがあった。「だれも見ていなくても、しっかりがんばっていて。えらいな。無理するなよ」と。温かくて厚みのある声。一語一句、私の耳に残って、それからはずっと、加藤さんと話してみたい、加藤さんに認められたい、いつかいっしょのチームで仕事がしたい、と思っていた。
でも、加藤さんの脇にはいつも明美がいた。キャハハと高い声で笑う明美に、つられるように笑う加藤さん。明美にしか見せない、くだけた表情だ。ふたりに背を向けながら、私はいつまでも残業をしていた。
翌年、明美は営業部へ、加藤さんは総務課へ異動になった。
ふたりがいなくなると、風が止まったように静かになり、私は仕事を覚えて、それなりに前に進んできた。相変わらず、自己主張のできない自分だけれど、だからこそ動いていく仕事も多い。ようやく少しずつ自信のようなものもついてきた。
なのに、まさか、明美が戻ってくるなんて。

山道に入るところで、私は口を開いた。
「あのさ、加藤さんとは、いまでもときどき話してる?」
名前を出すまい、と思っていたのに。聞いてしまった。 明美は目を丸くして私を正面から見た。
「加藤さん? なんで? 話す用ないし、全然だよ」
思いもよらない返答に、私は足を止めた。
「あ、そういえば、加藤さんって、私がいたころ、貴子先輩と付き合ってたよね。最近、別れたみたいだけど」
え……。貴子先輩?
「私さ、じつは加藤さんのことちょっと苦手だったんだよね。あの人よく、ふたりで呑みに行かない? とかコソコソ聞いてくることとかあって。だから私、わざと加藤さんと話すときは声を張るようにしたんだよね。みんなに聞かれてもいいことだけを、話すように、って。それに、貴子先輩と付き合ってたんだよ。不倫、だよね。なのに、私にも声かけてくるって、変じゃん」
あまりに驚いて、私は何も言えなかった。知らなかった。私は、明美のことを、加藤さんの脇にいる厄介な存在、としてしか考えていなかったのに。加藤さんを取られた、とすら思っていたのに。
そっか。でも、あのころ、たしか、貴子先輩って、結婚したばかりじゃなかったっけ……。まぁいい。私には関係ないことだ。
記憶をたどってみると、明美は、いつもまわりを明るくしようと、笑顔をふりまいていた。私の部署内プレゼンのときも、がんばってね! と声をかけてくれていた。なんだか頭の中がごちゃごちゃしてくる。
杉林のなか、上り坂の傾斜がキツくなってきた。息が切れてくる。
やがて道幅が広がり、ベンチが見えた。私と明美はバックパックを下ろして、飲み物を取り出す。まだ肌寒い春先でも、山を登ると汗が止まらない。
明美が、携帯を出して周りの杉林の写真を撮り、それから、私をふり返って言った。
「透子、昔より、少し話しやすくなったかも」
そうかな、と私は言いながら、昔はごめんね、と心のなかで思った。
「よかったらLINE教えてくれない?」
うん! と私は携帯を取り出す。ふたつの携帯を近づけて、友だち登録して「よし、つながったね」と明美が言う。
初めて明美の顔をこんなに近くで見た。うれしそうに、目を細めている。
七年前に、こうできていたらよかったのに。
さっきまで空に広がっていた雲のあいだから、太陽と青空がのぞき始める。
新しい景色が見えてきそう。新しい企画案も出てくるかも。
「このグローブ、弟が買ってくれたんだ」
縞々のグローブをつけた手をパッと広げた。
「三年前バイクで事故って、まだ病院でリハビリがんばってるんだけど。私が山に行くって言ったら、ネットで買ってくれたんだよ。自分で手を動かせるようになって。よくなったらいっしょに行きたいって。だから、今日の登山は下見なんだ」
弟さんが……。そうだったのか。
「山頂でコーヒー淹れようか。と言っても、インスタントのスティックだけど」
明美が言う。
「私も、おにぎりとおいしいクッキーあるんだ。コンビニで買ったんだけど」
私が言い、ふたりでちょっと笑った。
頂上まであと少し。
「ちゃんと下見しないとね。写真もいっぱい撮ろうね」気合を入れて私は、バックパックを背負い直した。
SHARE
PROFILE
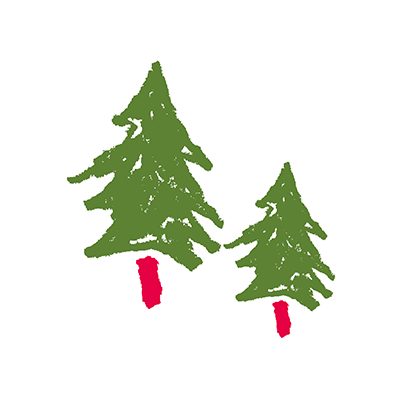
ランドネ 編集部
自然と旅をキーワードに、自分らしいアウトドアの楽しみ方をお届けするメディア。登山やキャンプなど外遊びのノウハウやアイテムを紹介し、それらがもたらす魅力を提案する。
自然と旅をキーワードに、自分らしいアウトドアの楽しみ方をお届けするメディア。登山やキャンプなど外遊びのノウハウやアイテムを紹介し、それらがもたらす魅力を提案する。