OUTDOOR

Mountain Story vol.11 「高尾山へ再び」

クライミングジム「エッジ・アンド・ソファー」での展覧会にて、キャンバスにアクリル絵の具を使った作品を出展|筆とまなざし#371

キャンプ場に将来のシンボルツリーを植えてみた|アウトドアタウンときがわで里山遊び#14

ビーチクリーンの前にお肌クリーンもね【by 九島辰也】

しょうゆ顔な美形キャラ「コバギボウシ」|植物ライター・成清 陽のヤマノハナ手帖 #33

あてもなく郊外の自然を求め、たどりついたのは白一色の雲取山|劇団EXILE・佐藤寛太の旅手引き #14


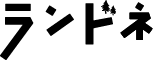
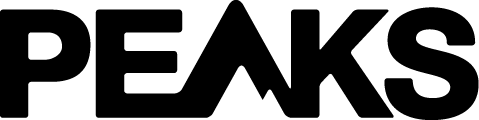
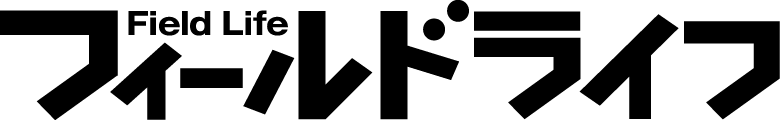
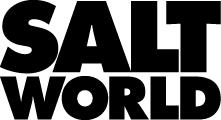
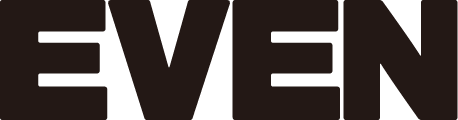

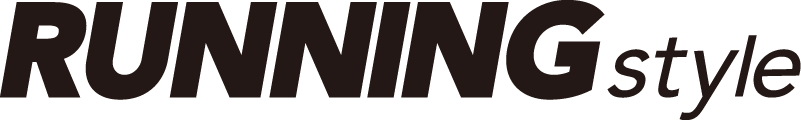
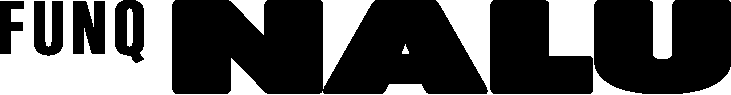
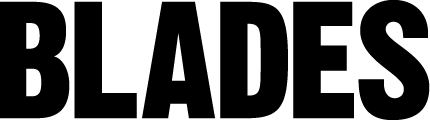
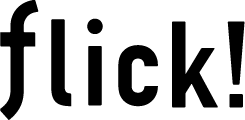
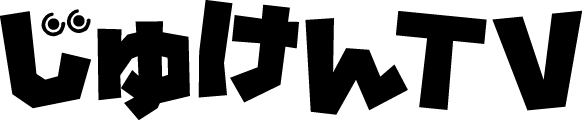
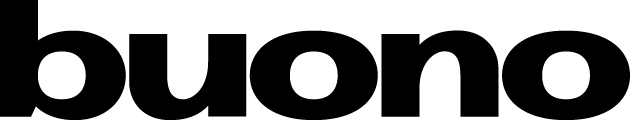
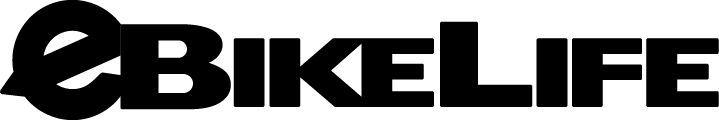
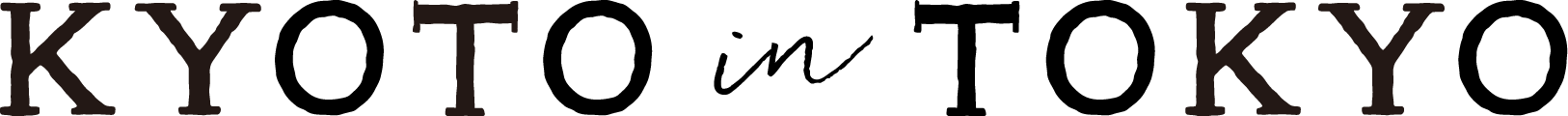
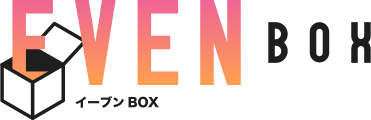


![FUNQ [ ファンク ] 趣味の時代に読むメディア](https://funq.jp/wp-content/themes/funq/assets/img/photo_08_sp.jpg)
![FUNQ [ ファンク ] 趣味の時代に読むメディア](https://funq.jp/wp-content/themes/funq/assets/img/photo_08_pc.jpg)


































