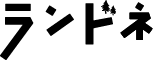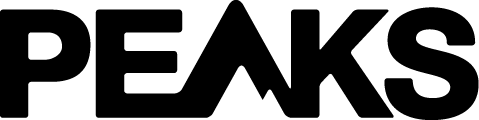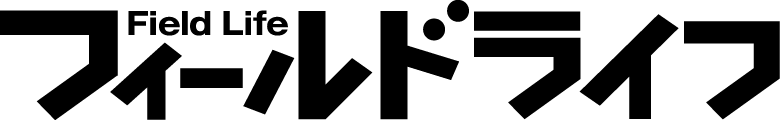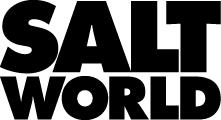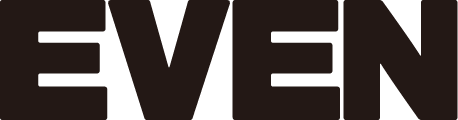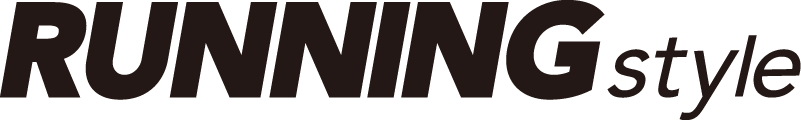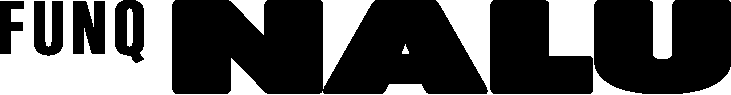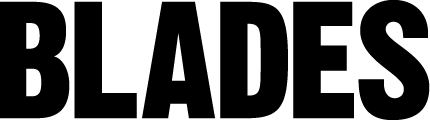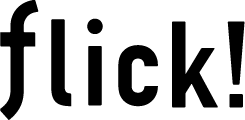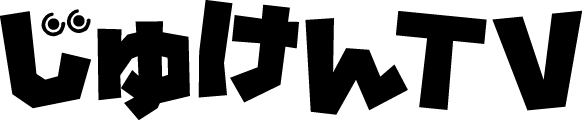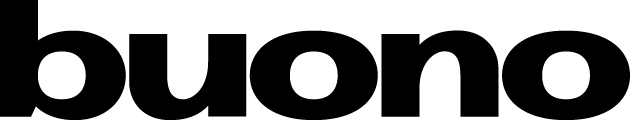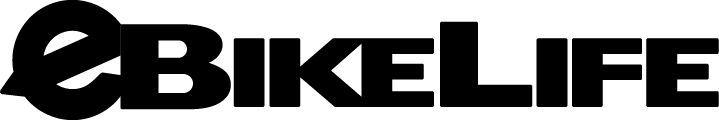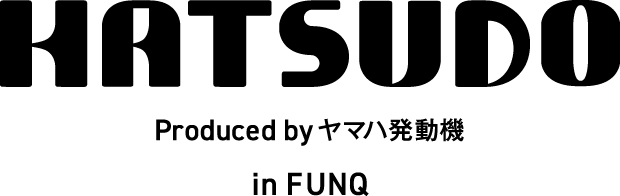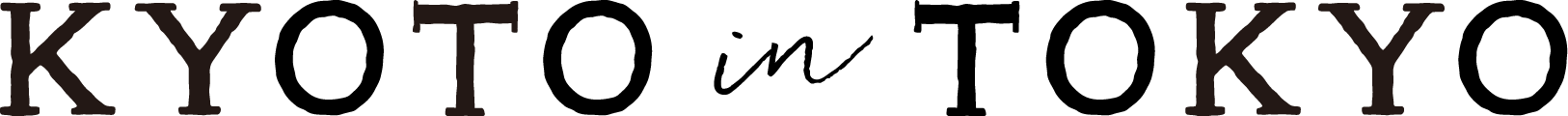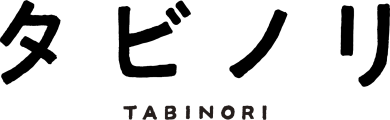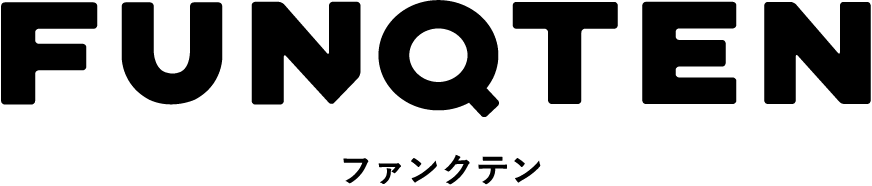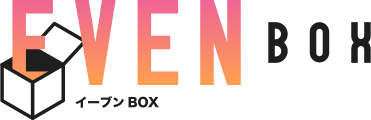100年後もウールを使い続けられる 幸せな社会を目指して。三瓶山のふもとから生まれるKASAGIのウール
ランドネ 編集部
- 2025年04月20日
大山隠岐国立公園にある三瓶山のふもとへ移住し、ヒツジの飼育からウール製品づくりまでに情熱を注ぐ笠木真衣さん。自然豊かな環境でヒツジたちが健康に育つ姿とともに、笠木さんが「ヒツジの幸せ」を探し続けるようすを追いました。

KASAGI
https://k-f-s.jp
https://non-non.farm
Instagram@kasagiwooltextiles
お話を伺ったのは

笠木真衣さん
神奈川県出身。羊毛が紡がれて糸になることに感銘を受けたことをきっかけに、ウール加工の技術を学ぶ。自身が飼育するヒツジの毛を紡ぎ、ウール生地や製品を手がける。ジャパン・テキスタイル・コンテスト2020 グランプリ受賞
一つひとつのウールに宿る
ヒツジたちのあたたかな思い
――あらためて、羊毛を使って生地や製品づくりを始めたきっかけを教えてください。
笠木 2011年に織物の勉強をしているなかで、糸紡ぎ体験の練習材料として羊毛を扱いました。初めて触れたとき、繊維の強さや色、脂、軽さなどに衝撃を受けました。紡いでみると、獣のニオイが広がり、このヒツジはいったいどんなヒツジなんだろうと感じたんです。そのときの感覚が強烈で、夜家に帰っても、お風呂に入っているときでも、「明日も絶対に触りたい」という気持ちが頭から離れませんでした。起きるとまたすぐに触りたくなり、工房に足を運びました。その日から、「明日もやりたい」という思いがずっと続いています。14年間、毎日ウールとともにすごしていますね。
――ヒツジを実際に飼い始めたのはいつですか?
笠木 飼い始めたのは2020年です。初めて羊毛を触ったときから、いつかは飼いたいなと思っていましたが、そのときは群馬に住んでいて定住するわけではなかったので、ヒツジを飼うことはできませんでした。マフラーやショールなどを受注販売するなかで、チーズ牧場や観光牧場、個人のペットとして飼われているヒツジなど、いろんな育ち方をしたヒツジのウールを脂付きのまま1頭分買って、洗って紡いでみました。そうすると、育て方や羊毛の洗い方によってできあがりがまったく違ったんです。お湯の温度や洗剤などを研究するなかで、ヒツジたち自身のことが気になるようになりました。ヒツジがどういう景色を見て一年をすごしていたのかを見てみたいと、思いをめぐらせるようになったんです。それだったら、自分でヒツジを飼って、その羊毛で製品を作りたいなって。そうして、2020年に飼い始めたのが4頭。それが4年で24頭まで増えました。羊毛を手に取ると、どのヒツジの毛なのかがわかるし、ヒツジごとの性格も浮かんでくる。この満足感とか安心感が、私の求めていた価値観なのかなって、やっと思うことができました。


――島根県大田市の三瓶町に移住したのは、ヒツジを飼うためですか?
笠木 そうですね。ヒツジを飼うためというのもありますが、それ以上に私自身の希望として、夜まっ暗になることと、音がしないことが条件でした。さらに、もともと三瓶はウシの放牧地として有名な土地だったみたいで、ヒツジを飼うのにも最適な条件が揃っていたんです。ヒツジは、風とおしが悪いと健康に影響が出てしまうのですが、三瓶は一年をとおして冷涼な風が吹くんです。さらに、曇りがちで紫外線の影響が少ないため、うるおいのある繊維がとれるんです。水が軟水なのもヒツジの毛を洗うのに適していましたね。漬け込んでおくだけで汚れがけっこう落ちるんです。ウールは摩擦や熱に弱いので、ちょっとのお湯と洗剤で洗えることが羊毛の生産に適していました。

――ヒツジにも環境にも優しいですね。具体的に、ヒツジの幸せが見えるための取り組みというのは、どんなことをされているのですか?
笠木 体と心の両面からヒツジたちの幸せを見守っています。まず体の面としては、一年中自由に放牧し、小屋に閉じ込めることがありません。牧草の種類にもこだわり、繊維質が豊富で、消化がゆっくり進む牧草を選んでいます。ヒツジたちの健康状態については、動画や写真で専門の獣医さんとも連携しながら健康管理を行なっています。
――心の幸せについてはどのような取り組みを?
笠木 まずは私がヒツジたちとたくさんコミュニケーションをとることを心がけています。名前をたくさん呼んで、「今日元気ないね」「ジャンプできるようになったんだね」とか、ヒツジたちの変化や成長に対しての声かけをしています。また、三瓶では地域の方々が草刈りをして景観を守っているのですが、ヒツジたちが荒地の草を食べたり、田んぼのあぜ草を食べたりすることで、地域の働き手としてもひと役買っています。そうすることで、「ヒツジたちはいい仕事をするな、かわいいな」と地域の方々が優しい目で見てくださる。すると、ヒツジたちも心理的に安心して暮らせます。私がかわいがるだけ、高い牧草を買ってやるだけでなく、地域のみなさんと連携しながら育てています。


――インスタグラムやnoteなどのSNSでもヒツジがどんな場所で暮らしているのかをたくさん発信していらっしゃいますよね。笠木さんのヒツジへの愛情やどんなヒツジが製品になっているのかがとても伝わります。製品が購入できるのはオンラインショップのみですか?
笠木 そうですね。よくお世話になっている地元のパン屋さんとカフェ、紅茶専門店には商品を置かせていただいているのですが、どんな方がどんな用途で使われたかを知りたいので、基本的には直接販売のかたちをとっています。オンラインショップでの直接販売を通じて、お客さまとつながり、製品に込めた思いを伝えることができるのがうれしいです。



――海外の見本市への出店はどのように決まったのですか?
笠木 KASAGIは、最初から海外での販売を視野に入れてブランドを立ち上げました。イギリスの方に製品を見せると、「おばあちゃんが作っていたものとおなじだ!」と喜んでもらえることが多いんです。それは、炊き立てのご飯を見たときの日本の人とおなじ顔。なので、ウールに親和性が高い人に向けてもKASAGIウールの魅力を届けたいと思いました。海外の見本市では、ハイメゾンのブランドバイヤーにも高く評価していただきました。欧州のブランドにKASAGIの生地を使っていただくのも夢です。

――欧州のブランドとのコラボレーションを目指して出展を重ねたり、新しい生地開発をしたりしているんですね。
笠木 それが私個人の夢ですね。もう少し大きな夢でいえば、どんなヒツジからとれたウールかわかるというのが、新しい選択肢になってほしいと思っています。ウールはいま、繊維全体の1%しか使われていないので、繊維としてより広く使われるようになり、ヒツジたちが育つ環境やその生活をもっと多くの人に知ってもらいたい。100年後も幸せにウールを使い続けられる社会を作りたいです。
SHARE
PROFILE
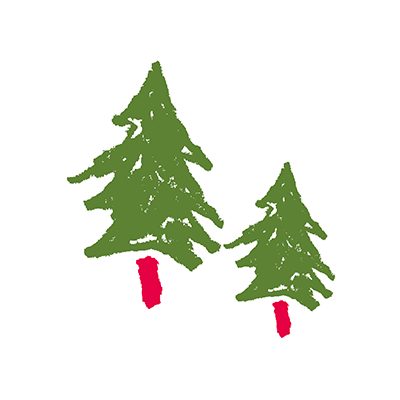
ランドネ 編集部
自然と旅をキーワードに、自分らしいアウトドアの楽しみ方をお届けするメディア。登山やキャンプなど外遊びのノウハウやアイテムを紹介し、それらがもたらす魅力を提案する。
自然と旅をキーワードに、自分らしいアウトドアの楽しみ方をお届けするメディア。登山やキャンプなど外遊びのノウハウやアイテムを紹介し、それらがもたらす魅力を提案する。