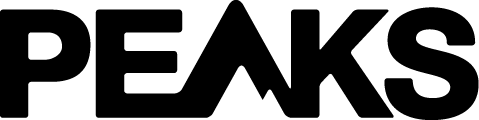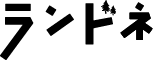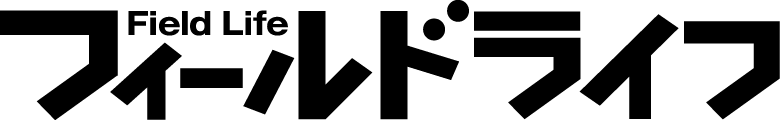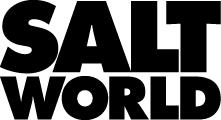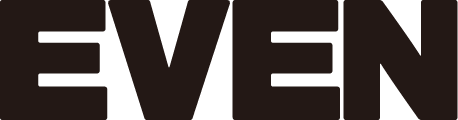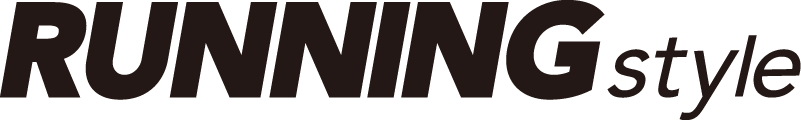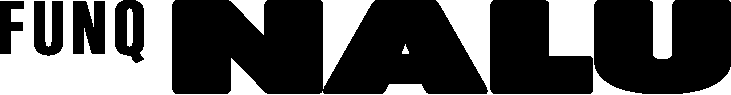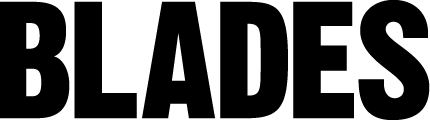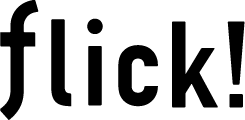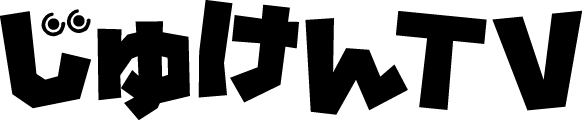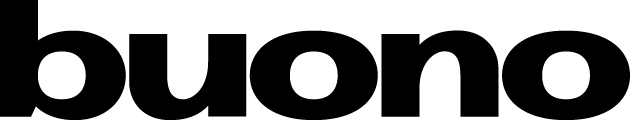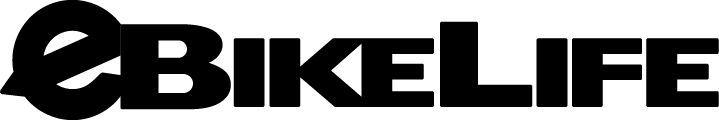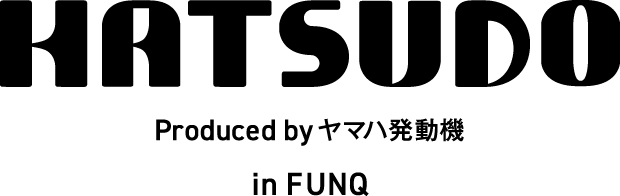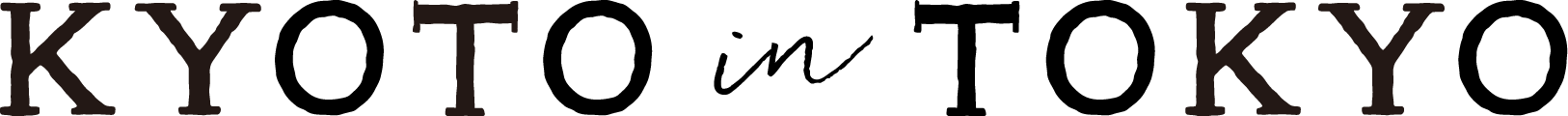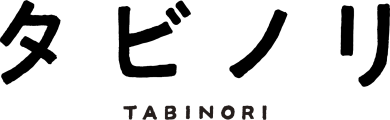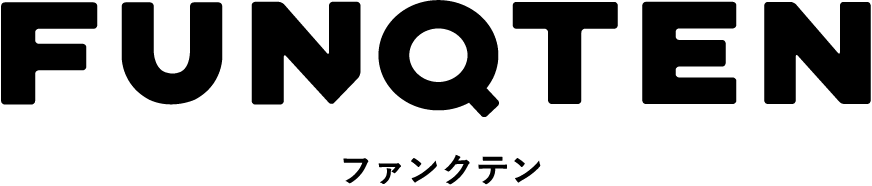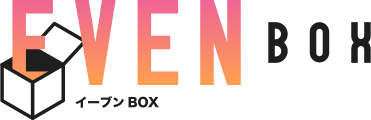ウエストリブ|大いなる山 Mt.デナリ・カシンリッジへの挑戦#8
佐藤勇介
- 2025年04月09日
北米大陸最高峰、デナリ(標高6,190m)。7大陸最高峰のひとつに数えられ、その難易度はエベレスト登山より高いという声もある。
高所登山としての難しさだけでなく、自身による荷揚げ(ポーター不在)、トレイルヘッドからの比高の高さ、北極圏に近い環境など、複合的要素が絡み、登頂成功率(※2023年度)は30%前後。
そんなデナリへ初めて挑んだ、山岳ガイドの山行を振り返る。
文・写真◉佐藤勇介
編集◉PEAKS編集部
\ #7はこちら /
Day 11 ウエストリブ登り返し
昨日の残業の疲れを引きずってゆっくりと目覚める。出発は昼近く。雪はやみ、ガスの切れ間からカシンリッジが見え隠れしている。視界のあるいまなら迷うことなくアプローチできるだろう。諦めのつかない心を理性でなんとか抑え込み、未練を断ち切るように足を山頂に向けて踏み出す。

広々とした雪面に見えるが、ところどころ大きくクレバスが口を開けている。場所によっては数十メートルのセラック(氷塔)になり、唐突に崖となって落ち込んでいる箇所も多い。下から登るぶんにはそのギャップが明らかだが、上から降りてくると直前まで気づくことはできないだろう。昨日のガスのなかでは相当、危険だっただろうし、安全な下降路を見出すことができたのかわからない。広い雪面なので、ホワイトアウトで方向も見失いやすい。

果てしなく続く雪壁を駆け上がる。頭上に見える岩をめがけてアックスを交互に振るい、アイゼンをひたすら蹴り込んでいく。20分ほどでたどり着けるとふんだ岩はいつまでたっても近づかない。あまりに近づかないので、後ろを振り返り、確かにトレースが刻まれていることを確認しないと不安になってしまう。
結局、2時間以上休みなく登り続けて(休める場所はない)岩の基部にようやくたどり着いた。4mほどの岩だと思い込んでいたそれは、二階建ての一軒家ほどの大きさでたたずんでいた。やはり目の錯覚というものは恐ろしい。わかっていても修正のきかないものだ。周囲の山々、風景すべてが圧倒的スケールなのである。

極限の幕営地
大きなロスタイムはないが、あっという間に時はたち、太陽がだいぶ傾いてきた。気温も下がって日陰では凍える寒さである。ぼちぼち幕営地を探しながら登らなければならない。
地形図上ではこのあたりにわずかに平坦な場所がありそうだが……。太雄がリードでロープを伸ばし、フォローでビレイ点に着いて周囲を見渡すと、一面の急斜面だった。

岩の露出も多くなり、雪を掘り下げての整地もままならない。しばらく周囲を探ったがよい場所はなく、お座りビバークの可能性も見えてきた。風も強まり急速に気温も下がり始めている。
そんななかで登っている途中に唯一、可能性のある場所を私は目ざとく見つけていた。先ほどの大岩の上である。ロープいっぱい懸垂下降して確認すると雪が吹き溜まっている部分もあって、雪をかき集めて整地すれば、なんとかテントひと張りはいけそうだった。

ナイフリッジ状だった岩の上の雪を崩して、平らにならす。氷を削って掘り下げる。吹き溜まりから雪を運んでさらに拡張する。尾根から空中に突き出たようにある岩の上に、極上のテン場ができあがった。これまでもっと厳しい環境で何度もテン場を作ってきた経験が役に立った。
もっとも、一歩間違えば遥か眼下の氷河まで一瞬で滑り落ちる場所である。しっかりアンカーを取って万一に備える。一番危険なのはトイレの瞬間に違いない(もちろんセルフビレイ取ります)。

Day 12 ウエストリブ上部
「今日はあわよくば山頂を踏んでキャッシュを埋めてあるハイキャンプまで行きたい」。そんな願望をもちながら登っていく。
しかし、ここではそう簡単に物事は進まない(それは、賢明な読者は即座に予想できるハズ……)。まったくそのとおりで、歩みは遅い。息は切れるし疲れも引きずっている。

幸い天気だけはよく、展望もほしいままにしている。標高は5,000mを超え、血中の酸素濃度が下がっている。そのぶん、パフォーマンスは低下する。
ここまではウエストリブの通常ルートを外れたルートを取っている。バリエーションというほどではないが、記録にないラインをたどるのはやはり楽しい。地形を読みながら最善のルートを見出していく。
一度、休憩時に両足のふくらはぎが猛烈につってしまった。日本の山で足がつることは未だ経験がなかったが、どうやら昨日の長時間トラバースの影響が大きいらしい。高所での脱水も要因のひとつだろう。

幕営地から仰ぎ見ていたクーロアールを登り詰めるとメディカルキャンプからショートカットで登ってきているクライマーのトレースにぶつかった。
ここからは大きな難所はなく頂上稜線にたどり着けるはずである。ウエストリブは山頂付近へダイレクトに伸びているが、厳密には山頂の肩にあたるフットボールフィールドと呼ばれる平坦地に合流する。
最後の雪壁を登るクライマーが見える。蟻のように黒い点が止まっているのかと錯覚するほどゆっくりと進んでいる。ぱっと見は1時間ほどで駆け上がれそうな壁であるが……以下省略。

斜度は45度くらいだろうか、雪面は硬く締まってアイゼンの効きが抜群だが、そのぶん滑落は許されない。腰を下ろすような場所もなく、ひたすら登り続ける。
さらにひたすら登り続ける。先頭を行く太雄は止まる気配がなく、後続のふたりも引きずられるように止まることが許されない。水も飲めないので雪を口に入れて渇きを潤す。
最後の気力を振り絞って歩く。すでに標高は6,000mに近づいている。みんなバテバテ。稜線直下でトラバースしてようやく平坦な場所に出た。広く風の吹き抜ける場所で、フットボールフィールドの下の台地のようだった。

SHARE