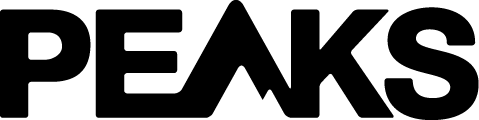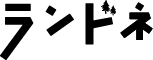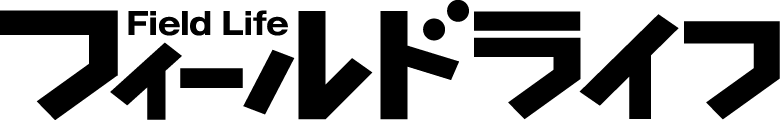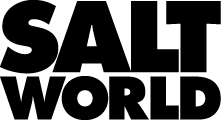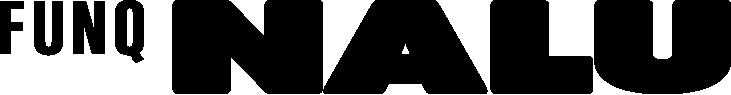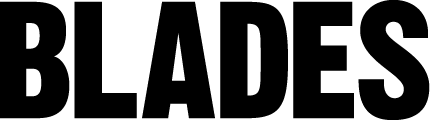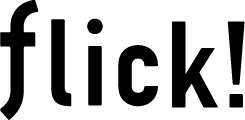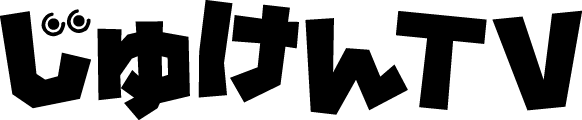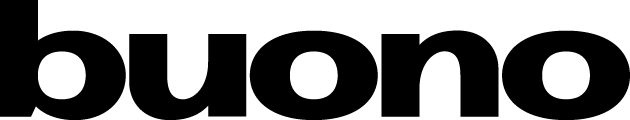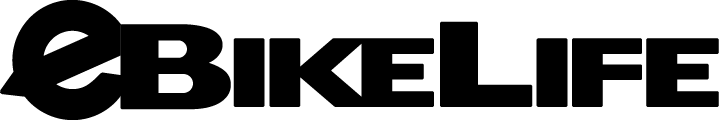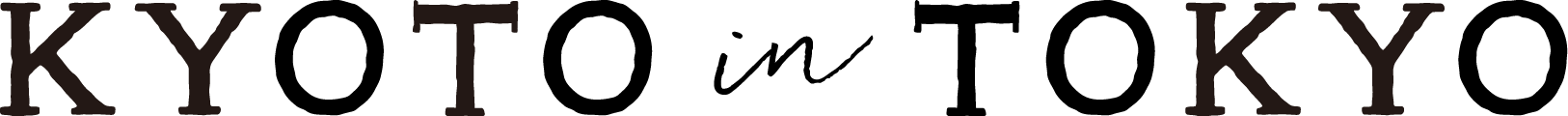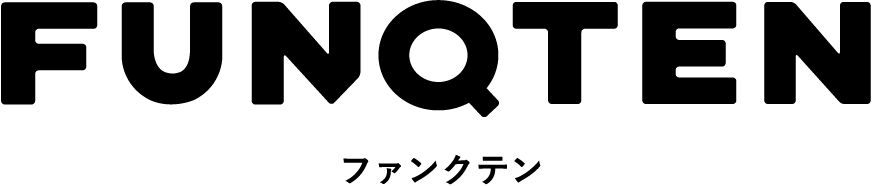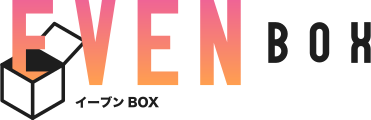「早出川支流杉川 滝を越えたイワナのこと」|Study to be quiet #3
成田賢二
- 2022年06月23日
INDEX
文◎成田賢二 Text by Kenji Narita
写真◎洞 将太 Photo by Shota Hora
「Study to be quiet」は、フライフィッシングを愛した17世紀の英国の随筆家アイザック・ウォルトンの言葉である。
その代表作は「釣魚大全」と訳されているが、原題は「The Complete Angler, or the Contemplative Man’s Recreation」である。どちらも詩を含んだ和訳しにくい英語に思える。
「quiet」でいることは難しい。僕はいつの日も胸が騒ぐ。雪煙を上げる白銀の山を見ても。向こう岸の淵で静かに呟くようなイワナの口元が見えたときも。
胸の高鳴りを押さえるにはひとつだけ良案がある。極端な労苦に身をさらすのがいい。肉体の使役は情動を静めるだろう。雪山なら胸が没するほどのラッセルにもがけばいい。源流であれば密生した藪やゴルジュの泳ぎに苦しめばいい。
高桑氏にいざなわれて。
高桑信一著『源流テンカラ』(山と溪谷社)の早出川支流アカシガラ沢の章には、以下の記述がある。
「だが、この右俣にはとっておきの秘密がある。上部の40m滝を越えた途端に尺物が走るのである。これは私の隠し沢のひとつだが、あえて紹介するのは、ここまで行ける源流の釣り人がそうそういるはずがない、と思うからである。ここまで出かけて、『高桑さんの言ったとおりでしたよ!』という人がいたら、涙を隠して『おめでとう』と言うつもりである。」
この文脈に誘われて何人の釣り人がこの奥深いアカシガラ沢を目指しただろう。
高桑氏は長年にわたり沢の盛衰を見続けてきた。
隠し沢は隠し沢のままでよかったのではないか。その場所の険悪さゆえに、隠すよりもつい口に出してしまった、氏の失言とも言うべきこのくだりには、釣り人へのあたたかい眼差しを感じる。
そして同時に私が思うのは、ここまで行けるほどの釣り人の情熱に悪意はあり得まいという、氏の朗らかな信頼である。
思えば釣り人たるものは、だれでも隠し沢を持つものかもしれない。
私たちと大魚との出逢いはいつも不意に訪れ、不意にすぎ去ってしまう。
先ほどまでこの竿を震わせていた、ラインの先で出遭った何者かの反抗は、そのときの胸の鼓動とともに、私たちの脳裏に、そしてむしろ手元に残り続け、静かに私たちの心を揺さぶる。
泳ぎ、連瀑、そして。

泳ぎ達者のHとクライマーのNとともに杉川に降り立ったのは九月も最後の週で、林道に待ち構える杉川の番人とも呼べる山ヒルたちもさすがに元気がなかった。
おりからの残暑で、まっすぐに南進する杉川の沢床は光り輝いており、日陰のゴルジュと日向の河原が繰り返される渓相だった。

視野のはるか高くまで続くブナの林の裾を、滔々と杉川の大水量が洗っている。
いつものように魚影を見るまでは竿を出さぬ約束で、寡黙なHが安定したルートファインドで先頭を泳ぎを交えつつ越えていく。

目のいいNが最初にエサ待ちして流芯に浮かんでいる魚を見つけ、やがて我慢ができなくなり竿を出し始めた。パーティーで竿一本と決めて先を進むが、やがて一本は二本になりルアーも飛び始めた。
今日の泊まり場となる二本杉はまだか。視界に広がるブナの林には杉のような木は一本もない。わずかに尾根筋にクロベかアスナロの黒木の姿が点々と望めるが、はるかに高く遠い。
本当にこの急峻な河原に杉なんか生えてるのだろうかと思い始めたころに、「ここ、二本杉だよね」という場所が突然現れた。急峻な河原のわずかな間隙をついた、六畳一間ほどの平坦地に、杉の大木が二本生えていた。
この杉は人が植えたものであり、すなわちこの場所に至るゼンマイ採りの杣道があった。かつてこの場所に小屋掛けをしていた人がいたということの証明には違いないのだが、それとはにわかには信じがたい場所であった。

本当に魚がいる。
アカシガラ沢右俣は、地形図を見るからに上部に魚が住むとは思いがたい。
実際にこの場所に行くとわかるが、高桑氏の言う「40m滝」には、正確にいうと語弊がある。私の見たところでは30m程度の滝が3段あった。このうちふたつはロープを出して登るべきもので、当然イワナが遡れるはずがない。それを越えると、渓相が再び変わり、端正なナメ滝が現れる。
この場に立つ人間の苦労を思えば、あらためてここに魚が住むとは信じられなかった。目の前には大きくはない淵が菱型に、静かに横たわっている。稜線上のコルまで標高差にしてわずかに100m。

恐るおそる毛鉤を投げる。いきなり魚の激しいバイトが来た、が、鉤が掛からない。しかし見間違いではない。本当に魚がいる。少し奥に右から細い支流が小滝となって落ちている。その落ち込みにもう一投。今度は先ほどのとは別の、ひと回り大きな尺物が来た。

その後は立て続けに魚が出てきた。全てを丁重に流れに放すと、この場所のさらに上のことが心に浮かび上がってきた。
だが僕たちはここに来て不意に、なぜか熱意を失ってしまった。限られた遺伝子を、このか細い水量を頼りに繋ぐ魚たちの全てを探る熱意を。触れられぬものを持っていたいという感傷であってもいい。
僕たちは釣り人として、最後には端然とした紳士でいたかった。それがルールのような気がした。
滝上のイワナ考。
以下はこの場所に関する考察である。
アカシガラ沢右俣のひとつ南は滝の連なる光来出川であり、西は赤倉川の源流で比較的穏やかではあるが、そのすぐ下にやはり連瀑がある。この場所にゼンマイが生えるかどうかはわからないが、生えたとしてもここまで先人たちがゼンマイ採りに来るとは思いにくい。仮に来られたとしても、ここまで生きた魚を背負ってきて放流することが果たして可能だろうか?
人の手が加わっていないとすれば、魚がどうしてここに住んでいるのかはわからない。実際に我々のような現代のクライマーであっても、登るにも下るにもロープが必要だった。
魚が住んでから滝ができたというのはよくある冗談である。
二俣まで降りた僕たちはその晩、焚き火を前にいつまでもこのイワナの来し方について考え続けた。
サンダルを履き、流れに降りて竿を降れば、無邪気な杉川のイワナはすぐに顔を見せてくれた。
明日はこの長い杉川を再び泳ぎ下らねばならない。
僕はこの豪雪の杉川に住むイワナの自由について考えていた。この狭く強い流れにあって、彼らは全身で流れに逆らい、全力で流下するエサを追い、そして長く閉ざされた冬に耐えるだろう。ひとたび大水が出れば、安定した産卵場を求め、いまいる場所よりもさらに上を目指すだろう。
自由とは、源流に住むイワナのことかもしれないと僕は思う。矢のように水中を疾走する、イワナという自然の摂理を前にして、僕は少しだけ「穏やか」になれる。

SHARE