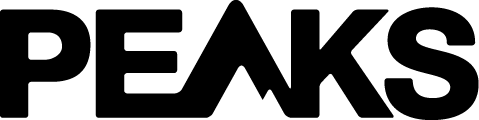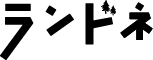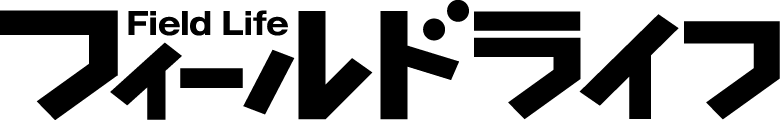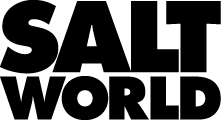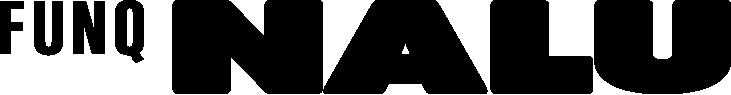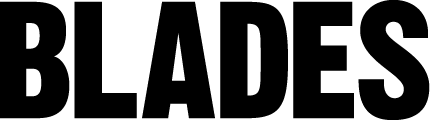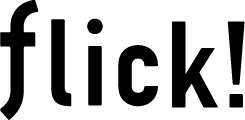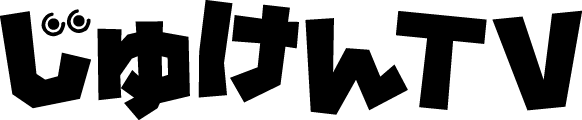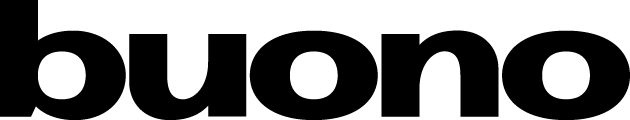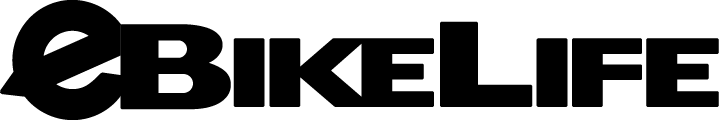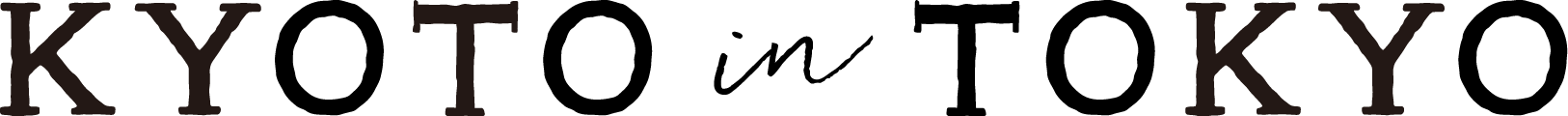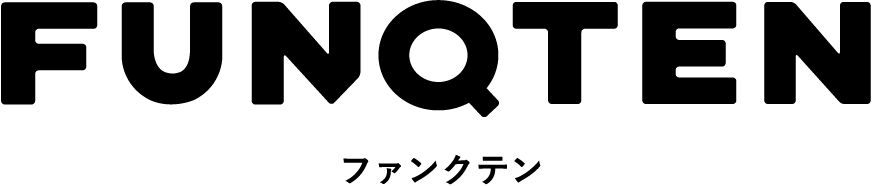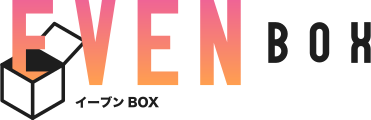「ザイテンの道直しのこと(後編)」|Study to be quiet #6
成田賢二
- 2022年09月19日
INDEX
文◉成田賢ニ Text by Kenji Narita
写真提供◉ハチプロダクション
翌朝

翌朝、ふたたび私たちは資材を背負ってザイテンを下った。人の手が施された登山道はやはり気持ちが良い。雪は日に日に溶け、前穂が落とす影は徐々に濃くなる。夏が近づいていた。
宮田はところどころ、踏み石のガタつきを直しながら下った。とくに石の縁の形状を気にかけ、ときおりタガネで岩の角を叩いて落とした。
「あんまり岩の角が尖っとるとテコの力が働きやすいねん。そんで段々岩が動く、最後には登山者がハネ上げてしまう。動きながら段々きつくしまってくのがいい石組なんやが、回りにあるもんだけでやってるからそうも毎回うまくはいかん」
穂高

私は労働の傍らで穂高という山の不思議を思っていた。地形に険しく、天候は厳しい。しかし稜線には数百人を収容する小屋がある。性格の近い山として剱岳があるが、剱岳の稜線に小屋はない。
ときに風で吹き飛ばされそうになるその稜線の山小屋に、灯火を灯し続けてきたのは紛れもなく人々の叡知とたゆみない労働である。奥穂にせよ北穂にせよ、小屋はなくとも登山は成り立つだろう、しかし、遭難はさらに多くなるのは容易に考えうる。白出のコルの岩塊をひとつずつ動かして均し、この地に定住の根拠を築いた重太郎の慧眼とその生涯を賭けた労働は、山荘の玄関前の石畳の上に立ってはじめて、足元から伝わってくる。
その営みに目を見張りながら、宮田は穂高の地に根を下ろし、小屋番として育まれ、ときにレスキューに血をたぎらせ、そして日々カメラマンとして身を震わせていた。
「ヨーロッパではあれやろ、トンネルでもケーブルカーでもなんでもありやろ、観光客がサンダルで稜線まで行けるらしいやんか。そんでそっから先は全てオウンリスク、自己責任のクライマーだけの世界や。落石かて落とすほうが悪いんやない、当たるとこにいるヤツが悪いねん。まあ山の高さも難しさも全然違うから一概に比較はできへんけどな。西洋流はきっぱりしててええやんな、死ぬ覚悟のあるやつだけが山へ行くねんから。そこへいくと穂高は全部曖昧や、どう見たかて死ぬ覚悟のないおっさんがそこら辺で落っこちて死による。そんでそれをおれらが必死こいてレスキューして、小屋戻ったら血糊ついた手を石鹸で洗って、すぐに同じ手で皿洗いせなあかん。ほんまにおもしろいところや」
覚悟

ハイマツコーナーにつくと、私は番線を取り出して昨日の仕事の仕上げにかかった。取り付けたばかりの木製の手すりは、朝日を浴びて夜露が輝いている。
「立派やけどあれやな、すんごい違和感やなあ」
宮田はしげしげと手すりを眺め、登り降りを繰り返した。
「うーん、エエんやけどなあ、やっぱ要らんよなあ、なんなんこれ? って思うよなあ……。成田よお、やっぱこれ、バラそか。手すりってなんか、保護者がやってるみたいやんか。別におれら、登山者を守ってるわけやないし。励ましてるだけや」
昨日苦労して取り付けたものを今日壊すことになる。私は宮田の迷いの中身をもっと知りたかったので、曖昧な相づちを打った。少なくともその時点、その現場では手すりの存在が正しいのかどうか、私にはわからなかった。この場所で死人を見たくないとはじめに言ったのは宮田であった。
「ここは穂高やから、死ぬかもしれんねん、死ぬ覚悟で来てもらわなあかんねん、そんなかで生きようとする意志だけが光輝くんやろなあ」
私は了解して、昨日締め上げたばかりの番線を切り、手すりを取り外した。結果として、ハイマツコーナーは山側にロープを張るだけの修繕となったが、一見して危険が強調されるようになり、その後、死亡事故は起きていないと聞いている。
重太郎のこと

「穂高にクサリ付けたのはほとんど重太郎さんや。だけど重太郎さんかてお役人の手前、自分で付けたとは決して大声では言えんかったらしい。なんか大勢人夫集めてボッカしてたらそのうちクサリができとった、みたいないい方してたらしい」
「だから穂高には不文律があんねん。重太郎さんが設置したもん以上のものは設置せえへん。その代わりそれが壊れてたら最低限直す。だから山荘の前のハシゴもいまもってひとつだけや。槍みたいにふたつにしたらいいのかもしれんが、ひとつを譲り合うのがちょうどいい頭数ってことなんやろな。にしてもあのクソ重たいクサリにしたって下から人の背中で上げとんねんから半端やない」
「重太郎さんの時代は当然全てボッカや。ヘリなんてあらへん。白出の真ん中に荷継小屋跡があるやろ、あそこまで当時の穂高小屋から降りてって、下から上がってきた荷物受け取んねん。そのボッカが小屋まで上がるのには当然、白出のガレ場を登らなあかんのやが、当時は岩がコトリともいわんかったそうや、そんだけ道がしっかりしとったってことや、いまじゃ考えられんけどな。下のほうなんかいまやただのガレ場や」
「重太郎の仕事の極めつけが地図作りや。穂高のほとんどの尾根から沢から、全部巻き尺使って距離を図らせた。ザイテンも大キレットも、吊尾根もジャンも北尾根も全部や。それを実際やってのけたのが当時の支配人の神さんや。お前、西穂から巻き尺持って距離図りながら来てみいや、頭おかしくなんで。いまでもその地図は山荘にあるぞ、昔はよう売れたらしい」
以上の話はできれば宮田の口から語ってほしかった。しかし宮田は2018年の海難事故により、西伊豆の海で帰らぬ人となった。
宮田八郎

人は自らの成したことについては最後には口を閉ざす。語ったことより語らなかったことに真実があるのは、宮田にも当てはまる。ブログでの発信を積極的に行なってきた宮田だったが、それはある意味でオフィシャルな発言であり、その裏には表象されない葛藤も多かった。むしろその葛藤が宮田そのものであったといえる。
宮田は酒を飲むとしばしば激情した。議論の相手を求め、見せかけの権威や、逃げ腰の愛想笑いには、自ら噛みつくことが多かった。宮田の発言はしばしば劇がかっており、私はその観劇者であった。
「娘が四人おんねん。次は男か次は男かと思ったら全部女や。でもな、それでよかったんかもしれん、こんな狂暴な血を引いた息子がおれば厄介でしゃあない」
私は過去に数回、宮田の深淵にある闇を見たような気がしたが、私風情では宮田の噛ませ犬にすらなれるものではなかった。
宮田が世を去った翌年の夏、私は宮田の足跡をたどるNHKの番組のガイド役を務め、ふたたびザイテングラードを登った。宮田とともに練ったセメントも、ともに動かした大岩も、変わらずにその場所にあった。その大岩のこちら側を私が持ち、向こう側を宮田が抱えて動かしたことも思い出された。ハイマツコーナーのスラブには、乾いた登山者の影が写っていた。
終わりに
山荘に着くと玄関前の登山者の喧騒は、宮田がいるといないに関わらず変わらぬものであった。穂高の稜線にあって穏やかに寛げる場所は唯一ここしかない。それは無理もないことであった。
その喧騒に耐えかねて私は人気のない裏口へ回り、宮田がいつも積んでいた石垣の上に立ち、白出から吹き上げてくる冷たい風で我を静めた。穂高岳山荘ほど、日が昇る信州側と日が沈む飛騨側で違う表情を見せる小屋はない。
そこには宮田の姿はなく、宮田が飽きるほどに眺めていたであろう笠ヶ岳が、夏空と雲海の向こうに佇んでいた。
宮田が世を去ってからさらに、私には宮田の人格が鮮やかさを増して胸に迫ってくる。人は死んでから一層その存在を強くするのはなぜであろう。その晩年の文章に、自らの死を感じさせるような言葉さえ見つけられてしまうのは不思議というほかない。
「レスキューに命賭けようなんて思ったことは一度もないで。でもな、結果的に命懸けになってしまった現場は、しばしばある。しゃあないねん、それしか方法なかったんやから」
ザイテングラードについて語るはずの章であったが、思わず筆者の宮田への追憶が溢れ、読み苦しい末尾になってしまった。ここまで読んでいただいた読者にはどうかご容赦願いたい。
SHARE