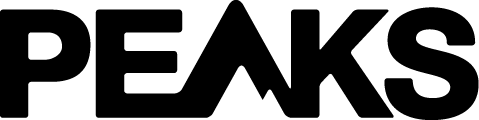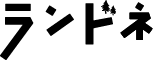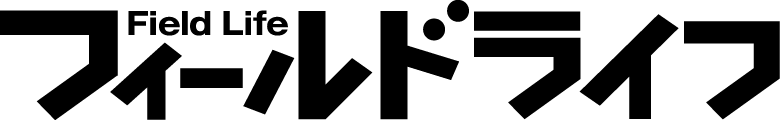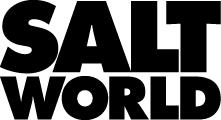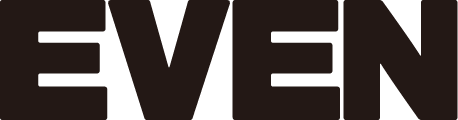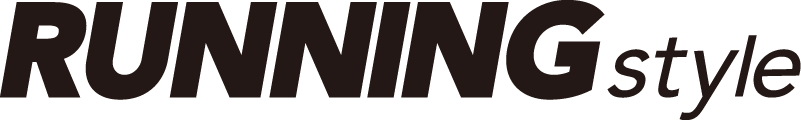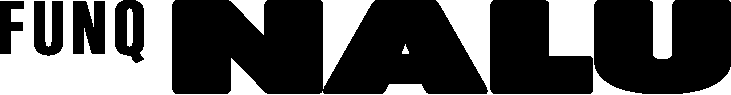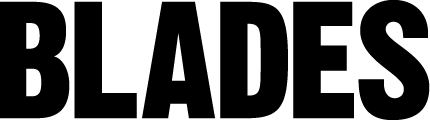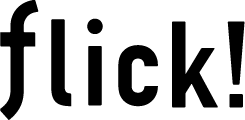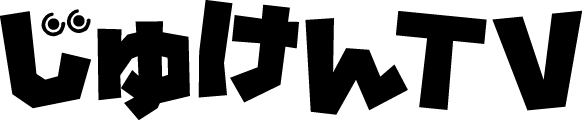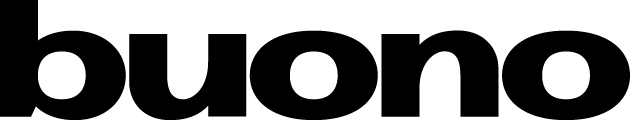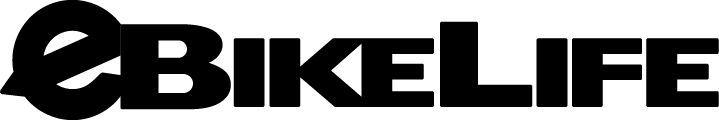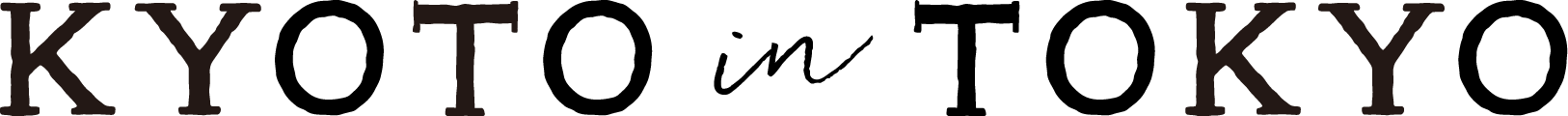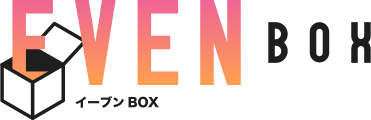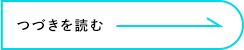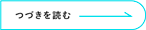シューレースの種類から締め方までを徹底調査!
PEAKS 編集部
- 2020年09月07日
- BRAND :
- PEAKS
- CREDIT :
-
文◉編集部 Text by PEAKS
写真◉荒木優一郎 Photo by Yuichiro Araki
SHARE
PROFILE

PEAKS 編集部
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。