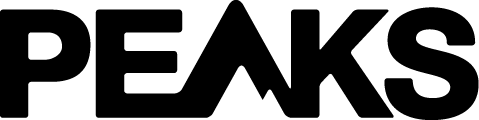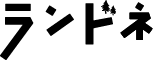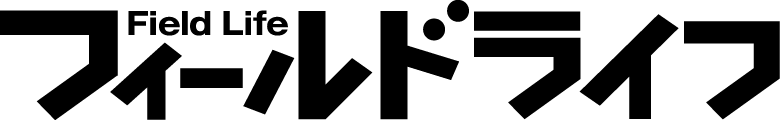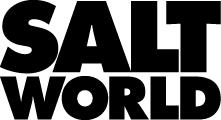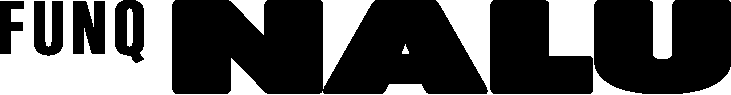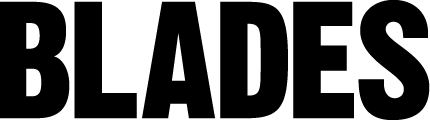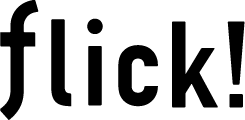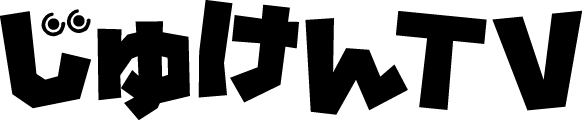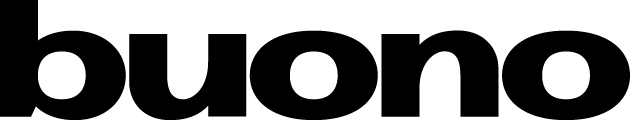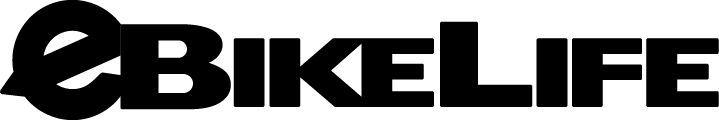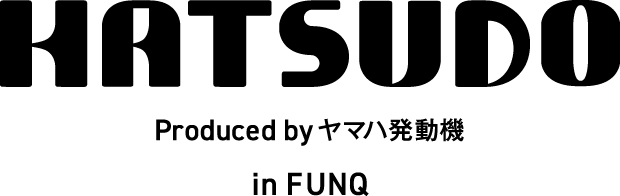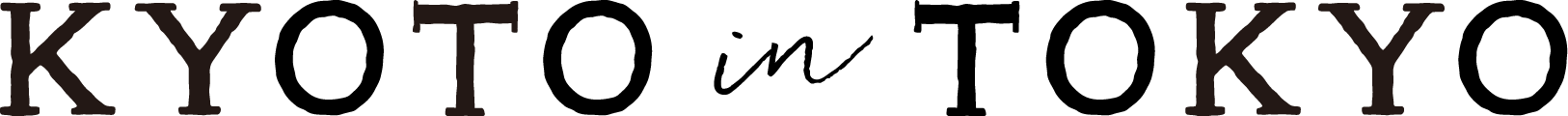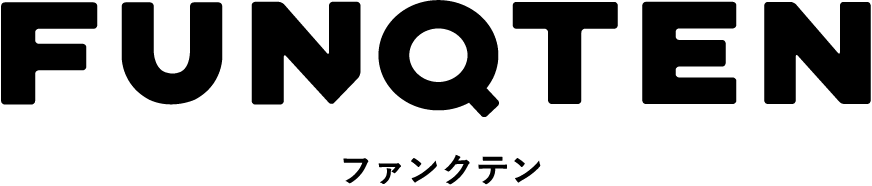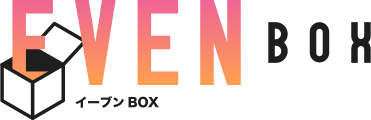正露丸と百草丸、ふたつの丸薬とふたつの氷瀑のこと|Study to be quiet #16
成田賢二
- 2024年03月04日
このまま気候変動が進めば近い将来、本州ではアイスクライミングなどできなくなる。
「昔は登れたんだけどなあ」
過去を語る老人に、すでに私たちはなろうとしている。氷も記憶も、春が来ればすべて萌黄に溶ける。
おそらく次に凍るころには私はそこにはいない。もう登れないだろう氷、しかし、たしかに登ったはずの氷の追憶。
文◉成田賢二
写真◉洞 将太、マウンテンワークス
百草丸、あるはずない氷瀑がそこにあったこと、たぶん今世紀最後
米子不動にある「正露丸」はクライマーの間ではよく知られている。最上段から取り付きまで一直線の傾斜で落ちる、端正な二等辺三角錐の形状をした氷瀑である。
なぜ「正露丸」と呼ばれるようになったかは、初めてこの氷瀑を完登したクライマーが名づけたことによる。登攀前夜、この氷瀑を登ることを想像しただけで胃が痛くなったということから来るらしい。
「正露丸」といえば私は米子不動の氷瀑をすぐに連想するのだが、一般的にはおそらくそうではない。製薬会社の著名なコマーシャルとともにラッパのマークのパッケージを持った胃腸薬のことを指す。もしかしたら若い世代はそのコマーシャルも知らないかもしれない。
「正露丸」は古くは「征露丸」であった。日清戦争において初めて大陸の地で会戦を行なった帝国陸軍は、国内とは異なる不衛生な水源に悩まされた。その後「征露丸」は軍医により生み出され、日露戦争中にチフス菌に対する抑制作用が認められて奉天会戦前後で陸軍に正式採用された。戦後は勝利への祝賀もあって広く国民薬として普及していった。現在の「正露丸」は曲折を経て普通名称化しており、複数の会社から同名の薬が販売されている。

米子不動の話に戻る。正露丸の50mほど右手には別の氷瀑がつねに見えており、この氷瀑はなぜか最下段まで繋がっていたことがない。最上段には完全に垂直な氷瀑を傲然と聳え立たせており、水が硫黄成分を纏っているのか蒼い氷がやや黄色がかって見える。正露丸を末広がりの堂々たる体躯と表現するならば、こちらは尻すぼみの一反木綿と表現するのがしっくりくる。この氷瀑が最下段まで繋がることがない理由はいくつかある。
ひとつは滝の落ち口が幅広なスラブ状になっており、「正露丸」のように流芯が細く定まっていないことである。さらに中段に顕著なオーバーハングが存在するため、ここでも流れが空間に放たれて氷結の筋になりにくい。もうひとつはこの氷瀑の面と露出にある。「正露丸」が深い溝に食い込んで真北を向いているのに対し、すぐ横にあるこの氷瀑は露出感のあるフェースがわずかに(おそらく10度ほど)正露丸より東を向いているために、残念ながら朝日が当たる。2月の初旬ともなれば晴天の朝の1時間ほどはその全身が燦々と朝日に照らされてしまうのである。自然の摂理とはいえ、この根子岳の山体崩壊における岩壁形成のほんの僅かな違いにより不遇の定めを受けた氷といえる。
その怪しいはずの氷瀑は2010年に初めて登られた。私などは同じような時期にこの氷を眺めてはいたはずだが、そもそも登攀の対象とすら捉えていなかったと思う。初登者は氷が存在しない最初のセクションを、氷とは関係ない10mほど離れた右のクラックラインから登った。そのときの記録によると、薄氷の張りつめたクラックを避けて、傾斜の強い乾いたクラックを素手になってハンドジャムで登ったというくだりがある。そして「手は冷えるが心は熱い」との言葉を残した。おそらくこの氷を登るためには横のクラックを登ればいいという発想は複数のクライマーが抱いたかもしれないが、実際にこの場所に岩登りのギアを持ち込んで素手になってそれを行なったことに価値がある。それまでの米子不動で行なわれたアイスクライミングとは一線を画した登攀だったというほかない。
彼らがこの氷につけた名前は「百草丸」。御嶽山麓で江戸時代より伝わる生薬のみを原材料とした健胃薬である。無論、正露丸への韻を踏んだものであるが、その丸薬の由来とクライミングの実感が誠によく調和しており、的を得たネーミングといえるだろう。

米子不動に入るには長い林道をアプローチする必要があるが、この林道は生活道路ではないので基本的に除雪はされない。私たちはこの林道にチェーンを巻いた四輪駆動車で無理をして突っ込んだものだが、毎回スタックするのがつねだった。今回も直前に降った大雪にスタックした車を置き捨てて、重たいギアと幕営具を背負って九十九折りに続く林道を歩き始めた。
<注意>
2024年現在、米子不動に至る車道は冬季の間、閉鎖されている。アイスクライミングを目的とする場合、ゲートより下の林道脇に駐車して入山することになる。
いつものテント場に幕営荷物を置いて、登るべき氷を物色しつつ岩壁下をラッセルしながらトラバースしてゆく。最奥部に近い正露丸らしき氷瀑に近づいてみると、随分と細い氷瀑に出合った。
私「あれ、正露丸、今年はこんな細いのか?」
K「いやいや、これは百草丸ですね、あっちの半分だけ見えてるのが正露丸ですよ。参りましたねえ、これは正露丸なんて登ってる場合ではないですねえ……」
私「これ百草丸か! そうか、これが出だしのクラックか」
K「いやいや、氷が繋がってるじゃないですか。正露丸なんてのはいつでも登れます」
私「これ! 登る! 登っちゃう?」
ふたりして口を開けて上を見上げる。目上げれば自然と口が開くほどに傾斜が強い。
出だしの切れ切れの氷はなんとかうまくこなせそうには見える。しかし2段目は胸元でふたりの人間が両手を回せば抱えられるくらいの太さで岩に張り付いた飛沫の塊に接している。手元には氷登りのギアはあるが、岩を登るためのギアはない。
私「どうしよう? 上はなんとかするけど、中段はどう見ても厳しいよなあ。もし君がやるならビレイはするが、あんまりプロテクションは取れんぞな」
K「いやいやこんなことは滅多にないことですから、登らないという選択肢はないでしょう」
私「しかしどう見てもツララが集まってるだけでちゃんとした氷じゃないけれど」
K「いままで氷で落ちたことはないので、確率からいえば今日も落ちることはないと思いますよ。持久力には自信があります」
私「いや君が落ちなくても氷が落ちたらどうすんの」
K「なんかところどころで壁と接してますから大丈夫なんじゃないですか。そこそこ冷えてますから、少なくとも今日の気温で落ちることはないと思います」
私「しかし相当登らないと敗退もできなさそう、まあお気をつけて。はいスクリュー、全部持ってけ」
K「要らんです、ろくなプロテクションは取れないですから軽くしたい、ある分で足ります。では行ってきまーす」
Kは最下段の飛沫が作ったクラゲの集まりのような氷を優しくアックスを引っ掛けて登りはじめる。私はKをビレイしようにも、確固たるプロテクションがほとんど取れないこの状況ではビレイの意味がなく、ただ漫然とロープを持っているだけである。2段目の核心となる氷柱が壁と接したハング下、僅かのテラスにやっとKはスクリューを埋め、同時にピッチを切った。そこから15mほどは垂直からややハングしたツララの集合体である。研ぎ澄ました集中力で、Kは再びほとんど信用に足るプロテクションは取れずにすぐに視界から消えた。私がハングの真下にいるため、氷を叩く音と大量の落氷が眼前を通りすぎるのみでクライマーのようすは一向にわからない。
ビレイ解除の声が聞こえ、恐る恐るフォローしてみると、いずれも全く信用ならぬ隙間だらけの氷であり、しかも水流をもろに受ける。じっとしていればずぶ濡れになるばかりなのでKはプロテクションがないことも忘れたかの如くにサッサと登ったらしい。いくぶんは太くなった氷のピラーを、帯状の氷のハングを左右に縫いながら弱点を得ていく。これは自分がリードであったら迷うことなく登り切れただろうかと自問しながらフォローする。
雪や氷を登るにおいて、果たしてこれは登って良い状況なのかどうかを悩むことは、私にはしばしばある。「迷ったら不可」、長く雪山を続けるにあたりこれを守りつづければ幸福で平凡な日々を貫いていけるだろう。しかしKには私より数段深く、「迷い」に対する客観的な見極めができているらしい。
「迷ってるということは可能性があるってことですよね? やってみればいいんですよ。迷いの正体に迫って可能性を見つけなきゃ成長はないですね」
ときおりKが私につながるロープを鋭く引く、彼の意志の如くに。
Kは最終ピッチの真に垂直な、あるいはところどころ垂直以上にも見える一反木綿の付け根で、フォローする私を迎え入れた。お膳立ては整ってしまった。どうにも私がこの最後のピッチをリードせざるを得ない。唾を飲み込んで上を見上げる。首が痛い。
「正味ぶったってんな……」
喉が渇きすぎてツララを食べながら登ったこと
私は無言でビレイ点から離れた。たぶんいままでもこれからも、私のアイスクライミングのなかでもっとも長く垂直の氷が続いたのがこのピッチだったように思う。百草丸周辺の岩は、一連の米子不動の険崖のなかでも上部が顕著に張り出しており、もっとも平均傾斜が強い。さらにこのシーズンは氷が発達しすぎて弱点となる凹角を全て埋めてしまったらしい。巨大なまな板のようなフラットな氷を、凄まじい高度感のなかで延々とステミングとレストを繰り返して登った。限りある持久力をできる限り省エネで使用しなければならない。

ところがそこに思わぬ来客が現れた。当時、空撮に凝っていた仲間が、なんと林道から私のすぐ横までドローンを飛ばしてきたのだった。巨大な正露丸を横目に、カラカラとしたドローンの乾いたプロペラ音を聞きながら、私はまな板の最上部で猛烈なパンプに耐えていた。この時の動画が残っているが、私は情けないほどに、アックスを離した片腕を振っているばかりで一向に登っていかない。
片手をレストするだけで片手はみるみるパンプしてゆく。眼前のつららを口に含み喉の渇きを癒す。スクリューを埋めて少しは安堵するが、この場所で耐えていることがなんの進展にもならぬことを思い知り、再び意を決して上へ上へと進んでいく。そして足元はるかに小さくなったスクリューに再び怯えることを繰り返した。私にとっては記憶に残る渾身のピッチであった。スクリューを打ち尽くしてようやく垂直を抜け、最後のスラブをノープロテクションで登り切り、腕ほどの立木にしがみつく。喉がカラカラで再び付近の雪を食べた。60mロープはほとんど出きっているらしい。声は到底届かないので強引に残りのロープを引き上げる。やがてKが鼻歌混じりでフォローしてきた。
K「いやーぶっ立ってますなあ」
私「いやーぶっ立ってましたよ」
三回の懸垂で無事に下降、取付きに立って見上げると、終了点との奥行きの差は2~3mくらいしかないんじゃないかと思われた。氷が氷でいられる臨界点に私たちは遭遇していたとしか思えない。実態のない対象を、実態のない空間をとおして、私たちは本当に登ったのだろうかが疑わしい。しかしこの両腕のパンプには実態があったのは疑えない。
私「これってまた繋がるのかねえ」
K「おそらく今世紀中は無理でしょうね」
私「なんなのかねえ。冷え込みなのか水量なのか」
K「秋に降った雨と今年の寒暖差が絶妙だったんでしょうね」
私「このタイミングでここにいられて良かったねえ」

その後私は何回となく百草丸の下を通ったが、Kの言葉どおり、この氷柱が地面まで繋がったシーズンは私のみる限りではなかった。最上段のまな板のような氷瀑を見るたびに、あのときの前腕の張りが思い出され、今年もあの場所に戻らなければという感覚を抱く。しかしアイスクライミングの装備は年々革新が続けられ、いまではあのころほどのパンプを感じることはなくなってしまった。そして近年の冬の短さを思えば、あの年ほどの結氷はもはや永遠に望めないように思う。登るべき氷は溶けたが、なおも道具は進化する。滑稽の絵柄はすぐそこまできている。

SHARE