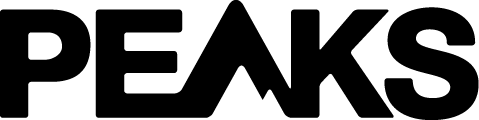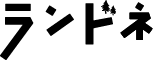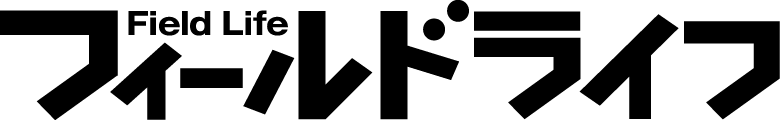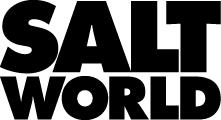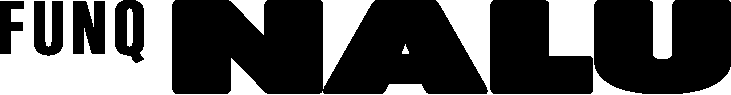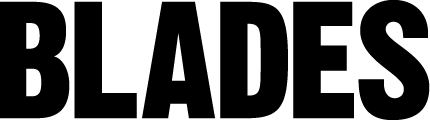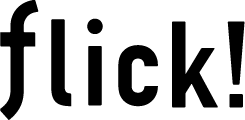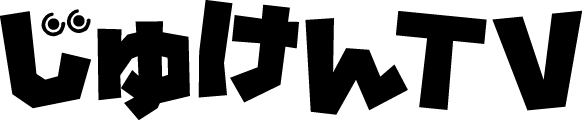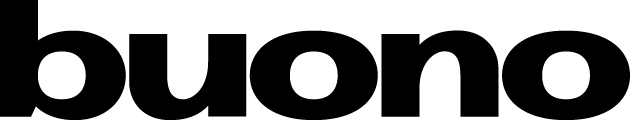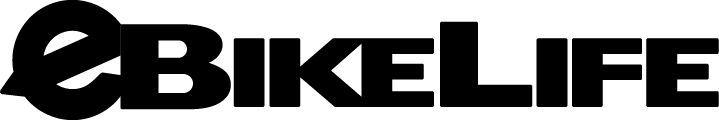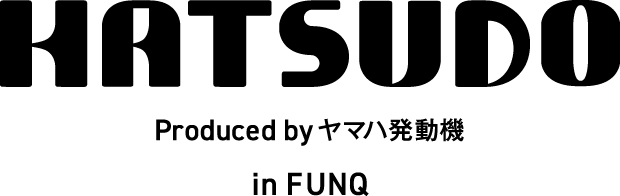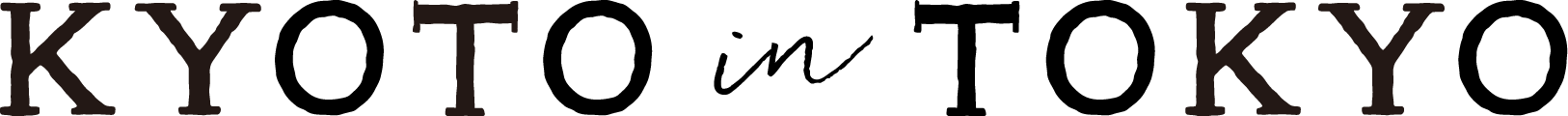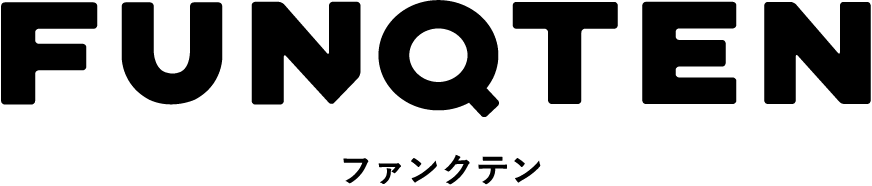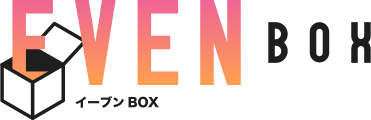トンボを狙うイワナのこと|Study to be quiet #17
成田賢二
- 2024年10月02日
イワナの捕食。これほどに躍動的な生命の発露があるだろうか。私たち哺乳類の捕食は鈍重で強欲すぎる。水という流体に棲む渓魚の宿命。ときに悪食(あくじき)と蔑まれるイワナの真の捕食の姿。
文・写真◉成田賢二
崩壊した林道8kmとそれに守られるS川
S川の中流部まで続く林道が崩壊してすでに数年が経過している。その林道の終点からはD岳へ登山道が伸びているはずなのだが、おそらくその道の草刈りも同じように行なわれなくなっているだろう。この国の林道行政が後退の局面に入ってひさしい。国の衰えは、あたかも人の衰えであるかのように、末端の神経や毛細血管から機能を失ってゆく。轍すらなくなって草木の繁茂した林道の起点に立ち、私は廃村化している最奥の集落を眺めていた。往時の充実した暮らしを偲ばせる大きな板壁の屋敷と土蔵は、草蔓の繁茂に半ば以上覆われていた。
私「やはりこれは無理だな、山を越えるしかないね」
Y「ここから往復するよりそのほうが良さそうですね」
S川の源流で夏のイワナたちの溢れるばかりの旺盛な食欲を目にしたかった私たちは、ひとつ隣のO川の登山口からK乗越を超えてS川の源流に直接降りる道を選ばざるをえなくなった。アプローチとしては迂遠だが、山頂まで抜けてしまえば下山は間違いなく楽になる。
登山口に着くと、イワナと同じように東北の夏を謳歌するアブたちの羽音がバチバチと車の窓ガラスに当たった。すでにアブの最盛期はすぎたはずだが、少なからずの彼らの吸血欲に遭遇するのは覚悟のうえである。
私「残党がまだいらっしゃる」
Y「川の近くにはいますねえ」
2泊分の食材と登攀具、調理用具、わずかな釣具を詰め込んだザックはそれなりの重さである。野営生活を充実したものにするためには少なからずの小道具が必要になる。塩、醤油、ネギ、生姜に至るまでていねいに分担したはずだが、背中の重みに汗が流れ落ちる。K乗越で背負い上げた水を飲みきると、登山道を離れ、一気に藪を潜りながらS川を目指してガレた枝沢を下る。良い釣りをしたいがために山を越える。S川を下ることができない以上、この山を越えるか山頂に達せねば戻ってはこれない。
笹を掴み、倒木を越えながら慎重に藪沢を下る。どうやら滝はなさそうだ、傾斜が落ちたところで小魚の魚影を見る。これでこの先に滝がないことが確定した。たどり着いた待望のS川の源流は、花崗岩の川床に水量豊富な河原の渓相でトンボが飛び交っていた。Yが小さな淵に火照った頭を漬けている。

河原の日陰に座るに良さそうな岩を探して腰を下ろし、ゆっくり休むのももどかしく、まずは竿を継ぐ。まだ下がらぬ心拍数が手元のカーボンロッドのピースを震わせてモタモタする。川に足を浸しつつ泰然と構えるべきか。あらまほしきフライフィッシャーにはほど遠い自らの無様にひとり苦笑する。
ロッドのティップにラインを通し終わって12番のパラシュートを結ぶころには、すでにルアーロッドを持ったYがスプーンを投げ始めていた。
Y「さっそく来たー! しかもけっこうデカい!」
Yがさほど深くもない淵から手繰り寄せたのはちょうど尺くらいと思われるオスのイワナであった。
私「これきっとアベレージだろな」
Y「いくつか追ってきましたけどどれもおんなじサイズでしたよ」
その後はフライ先行、ルアー後攻でジワリと進む。真夏の陽射しに花崗岩の河原がきらめく。私は左岸にだけある日陰を繋ぎ歩きながらていねいにオフショルダーでパラシュートを投じる。魚が静かに体を寄せてきては迷うことなくフライとその周囲の水ごとを吸い込む。どうやらS川の魚は激しいアタックではなく静かに吸い寄せるような捕食をするらしい。
水面に浮かぶフライの動きに目を凝らしたままで、私はもうひとつの目で俯瞰して川面の流れを見ていた。リーダーを長く取ることでフライは水流の影響を受けずに長い時間を自然に流れる。しかしそのぶんだけ手元のラインは弛むため、アワセを効かせるためには急いでラインを手繰り寄せねばならない。
思いどおりにフライがラインより先行して魚の食い筋に入る。魚がやや遅れてそれに気づき身体を流れに平行させて身を寄せ、速力をあげたかと思うと翻ってフライを抑え込む。そのごく短い時間にさえ流れは複雑に、そして一瞬とも同じではないかたちで流れる。水という流体、川という重力、生まれながらに流体に棲むイワナの捕食のシークエンスに私は見惚れる。矢のような疾走ときらめきのような旋回。そしてこの川面にフライを浮かべる人間は、一年におそらくひとりかふたりではあるまいか。

あれほどに釣りに来たいと願っていた場所にとうとう来てみたが、その釣欲を足元のS川がゆったりと洗い流してゆくのがわかった。長時間の運転と寝不足、照りつける夏の陽射しに疲れを覚え、私はテン場を探す。
私「もうここらでいいか、眠すぎる。テン場作っとくから楽しんできて。今日は夕立もないのでは」
Y「私も眠いです、とりあえず整地して休みますか」
荷を下ろし、河原にふたりだけがかろうじて横になれるスペースを整地し、タープを張って陽射しを避ける。薪はすぐ横に流木が溜まっている。増水にはとても耐えられない場所だが、それはそのときが来たら考えればよい。
傾いた陽射しがようやく山の端に隠れるころ、Yが戻ってくる気配で目が覚めた。少しだけ魚を持ち帰ってきたらしく流れに生簀を作っている。尺をゆうに越えるイワナのオスが2匹、浅瀬の生簀のネットに収まっていた。
私「でかいなあ」
Y「小さいのがほとんどいないです、メスは全部離しました。夕方テンカラであっちの支流も見てきますよ」
私の心はYの話を聞いただけでさらに満ち足りてしまった。焚き火を起こし、タープに補強を加え、いよいよこの場所に泊まる気を強くする。薪を切り揃えると、その日はもう竿を持たなかった。その代わり私の巻いたフライを数個、Yに持たせてある。
軽量化を期して酒も持たず、夕立に怯える夜であった。会話も聞き取りにくいほどにS川の流れが近い。吊るしたライトには各種のカワゲラ、トビケラが飛び込んでくる。羽音は鬱陶しいが悪さをすることはない愛すべき水生昆虫たちである。昆虫の多さが知らせてくれるS川の豊穣に胸が高鳴る。
源流ではアラームはかけない。だれが決めたわけでもないがそれは仲間内でもルールのようになっていた。前夜、何時に起きるかという山登りでは当然行なわれるべき会話も行なわれない。
翌朝はYが熾火を再び起こそうとする音で目が覚めた。下流に見える尾根の最上部を染めた朝日がタープの端から僅かに見える。ここから見える空の面積は全体の5%ほどにすぎないが、どうやら晴れているらしい。熾火を強く煽ぐと乾いた流木はすぐに炎を吹き返した。
サンダル履きのまま、昨夜から繋いだままの竿を手にしてフライを流す。さっそく魚がフライを追う。寝起きの私の左手がラインの回収に追いつかない。フッキングし損なったイワナは不審な顔をしながら流れに消えた。私だけがひとり笑みを浮かべる。
見たこともないイワナのライズが起きたこと
パッキングを終えて流れを遡る。河原はすぐに終わりを告げゴルジュ状になる。さっそく、深く大きな淵。流れは弱いのでYは竿を濡らさぬよう口に咥えながら犬掻きで泳ぎ進む。同様の淵をいくつか同様にして越える。ルアーを追う魚影はあるものの、不思議とバイトには至らない。これまでより風格ある放射状に開けた大淵に出る。ここはフライに先行させてほしいとYに頼んでラインのトラブルを直していると、なにかが水面に飛び込むような音がして淵を見る。
私「カエル飛び込んだ?」
Y「ですかね……?」
ふたりして訝しみながら川を見ていると大淵の奥のほうで再び音がする、カエルではない、魚がボチャン! とライズしているではないか。それも魚体が完全に空中に飛び出すほどの見たこともないライズである。
Y「軽く三魚身は出てますよ!」
私「サバ、なのか?」
事実、ちょうど日光のあたり始めたその煌めくようなドルフィンライズはイワナのものとは思えないサバのようで、その音は海の浅瀬で飛ぶボラのように聞こえた。やがて淵のど真ん中や、私たちの目の前でもサバは飛び上がった。明らかに尺(約30cm)はゆうに超えている。なかには飛びすぎて180度回転し、背中から水面に落ちるものもいるではないか。このような大胆なイワナの捕食はいまだかつて見たことがない。
Y「トンボか! 飛んでるトンボ食ってんのか!」
私「水中から空中のトンボ食えるか?」
淵と魚にばかり気を取られていたが、晩夏のS川にはあたり一面といえるほどのアキアカネが飛び交っている。それ以外に水面に浮かんでいる水生昆虫がこのライズの数ほどいるとは思えない。いたとしても水面を静かに流れているものを捕食するのにあれほどのライズが必要とは思われない。せいぜい静かに口を出すだけでいい。しかし水中にいるイワナが、相応の速さで空を飛んでいるトンボを食べることができるだろうか。そもそも食べようとするだろうか?

私は慌てて12番のカディスを淵の中心に投じた。なにも起きない。それどころか違う場所で同じライズが起きている。
私「なぜ食わない!」
私のフライボックスには蜻蛉のフライなど存在しない。最大限に大きい8番フックの特大カディスを投じる。昨晩あれほど大型のトビケラが光に集まってきたから今度こそ効くはずだ。しかしなにごとも起きない。相変わらずライズは続いている。
私「ダメだ、選手交代」
Yが5gのスプーンを投じる。数投してアタリがきた。明らかに重そうな引きで、淵を目いっぱい使って左右に走る。ドラグが僅かに鳴ったがそれが十分とは思えなかった。
私「ドラグ緩めろ!」
じつはYはルアーロッドを買ったばかりでリールの操作に慣れてはいない。慌ててドラグを緩めるとリールはいい具合に鳴いて、そいつはさらに淵の奥に帰ろうとする。
私「でも岩には潜り込ますな!」
その瞬間、私の目にはスプーンを咥えて走り回るおそらく40cmに迫るであろう大物を、「どうした?」とでもいうような顔をしてゆったりと追ってきた、さらにもう一回り大きな50cmオーバーの影が映った。
数分にわたるファイトを経てようやくくたびれた大物が浅瀬に上がってきた。明らかに40cmは超えている。竿をしならせてYがそいつを取り込もうとするが軽量化のため魚を掬うネットも持っていない、かつ竿の長さが頭に入っていないためリールを巻きすぎていた。
その瞬間スプーンが外れて40cmは「なにが起きた?」というような顔をして片膝をついたYの足元で止まった。水の反射でYからはそれが見えないらしい。
私「足元!」
気づいたYが静かに両手を水中に差し伸べて掴もうとするがその瞬間、魚は飛ぶように淵に消えていった。
Y「ぐあー!」
私「そりゃそうだわなー」
40cmが淵中で大騒動したおかげでサバのライズはようやく収まった。私たちはどれくらいの時間、この淵にいただろう。実際のところ、昨日捌いたイワナの胃袋にはトンボやバッタが入っていた。目の前で起こった不可思議な光景の余韻に浸りたいが、私たちは明らかに時間を使いすぎている。今日は魚止滝を越えて、さらに延々と続く連瀑帯を登攀して稜線に迫らねばならない。
同じようなトンボのライズが魚止滝まで続いていたらどうしようか? という私たちの心配は杞憂に終わった。次の淵ではそもそもライズは起きておらず、おまけに竿を持ちながら強引に泳いだYのロッドの先端はしっかりと折れていた。
私「終わったな、フライではこの淵は勝負にならん、小物釣ってもしょうがない」
Y「終わりましたね……時間もやばいっす」

とうとう私たちはS川の大本命である魚止滝で竿を出すことができなかった。未練には違いなかったが、それより手前のあの淵で私たちは釣欲を使い果たしていた。魚を止めたS川は滝の上で一旦河原になり、「まだ魚、棲めるのでは?」というフリを見せたあと、容赦なく連瀑をかけ始めた。微妙な高巻き、空身のクライミングと荷揚げを幾度繰り返したことだろう。想定内の雪渓潜りも連続したが、昔の記録と比較してみると、この時期としてはかなり雪は少ないといえる。


その日は稜線に近いガレ場の石を敷石に並べて寝床とし、僅かな流木を薪にしてなんとか炊事をすることができた。ふたりで小さな炎を眺めながら、朝の狂乱したイワナが繰り広げた光景を反芻した。産卵時に水面に尾を付けるトンボを狙ったのではないか、水中を透過する光の屈折率を織り込んで飛ぶのではないか、そもそも魚眼には光の屈折は関係ないのか、はなから闇雲に飛んでたのではないか……。実際にあのイワナがトンボをキャッチしたようには見えなかったし、枝先に止まって羽を休めているトンボならまだしも、空中を飛ぶトンボの動体視力を上回ってイワナがトンボを捉えられるだろうか。空中に身を晒したイワナが、水中でのあの煌びやかな方向転換をできるはずがない。答えのない議論と登攀の疲れは眠気を誘い、非常に寝心地の悪い岩の寝床にも関わらず私たちはすぐに眠りに落ちた。

稜線に近いために夜半に風が吹き、タープがはためく音で目を覚ました。曇ってはいるもののほのかに明るい。月が出ているようだがタープの下からはそれを見ることができない。耳にはいまだにあのイワナのライズの音が残っている。明日はさらに登攀を続けて山頂を越え、長い稜線を歩かねばならない。細くなったS川最源流の水音を聞きながら、月明かりに照らされて流れてゆく淡い雲を眺め続けた。
SHARE