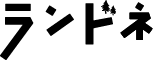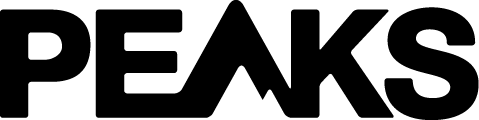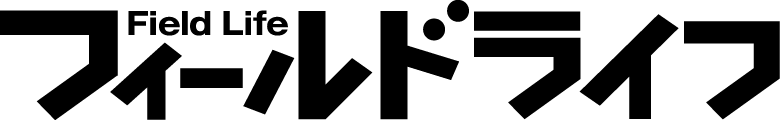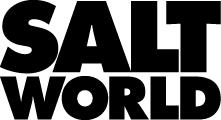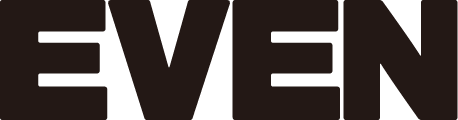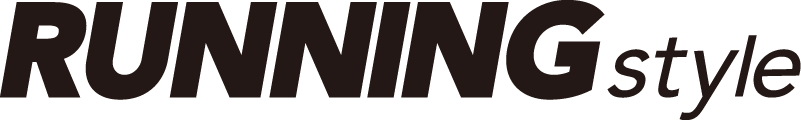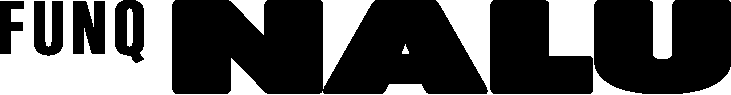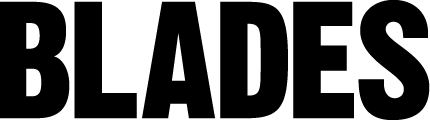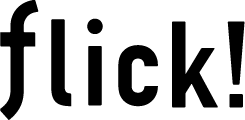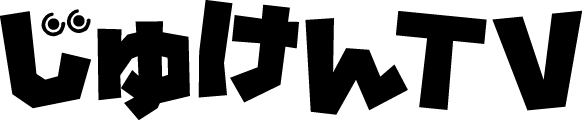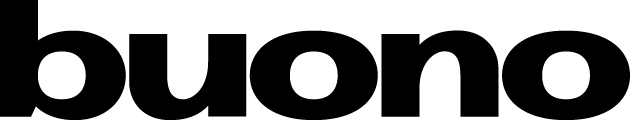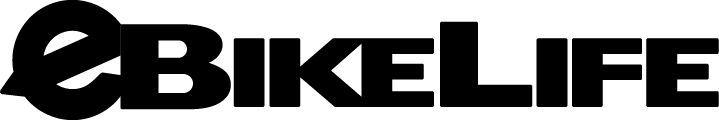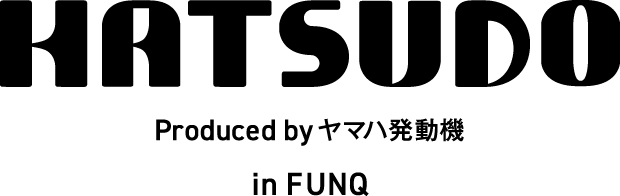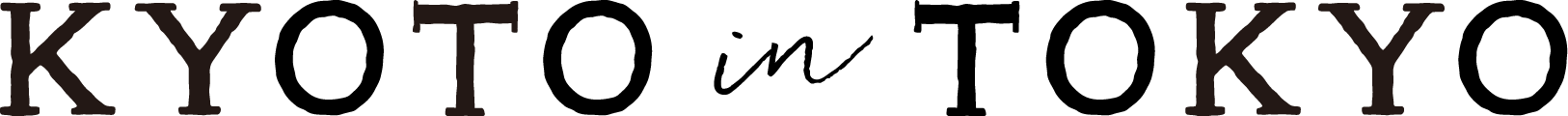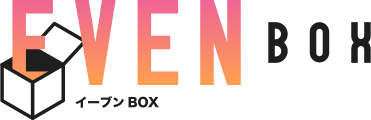レース後半のスタミナ切れを克服する方法! 終盤でタレないための走り方のコツ
Bicycle Club編集部
- 2021年12月29日
レースに参加する限り、誰しも終盤の勝負どころまで残りたいと思うはず。ところが序盤は調子よく走れていても、疲れが溜まりレース後半には失速してしまうという人も多いだろう。そこで今回は、ツール・ド・おきなわ市民210㎞チャンピオンの紺野元汰さんにトレーニングのコツとスキルを伝授してもらう。
レースの後半まで脚を残しておくためのスキルとトレーニングのコツ

レース後半、集団のペースについていけなくなって千切れてしまうこともある。レース初級者にありがちな、トレーニングの落とし穴と体力温存のためのスキルをみていこう。
乗る習慣をつけてベースを高める

「ロードレースで早々にメイン集団から離脱してしまうのは、絶対的なトレーニング不足が原因です。トレーニングの習慣がない人は、まずは3日間連続して乗ることを目標にしましょう。以降は3日乗って、1日休息を入れて、ふたたび3日乗るというように、トレーニングを習慣化していきましょう」(紺野さん)
継続は力なり! 紺野元汰おススメの週間トレーニングメニュー

効率を求めるのはベースを作ってからでOK
「ロードレースを小手先のテクニックだけで最後まで走り切ることは簡単ではありません。たしかにスキルの習得も大切ですが、やはり最低限のベーストレーニングは必要です。また、トレーニングに効率を求めることは、トレーニングを習慣化してボリュームを増やしてからで大丈夫です」
いかにして省エネで走れるかを考える
ロードレースで結果を残すためには、終盤の勝負どころまでいかに省エネで走れるかがポイントになる。アマチュアロードレースでも時速30~40㎞台の集団走行が基本になるため、エアロフォームで空気抵抗を極力抑えることは重要。エアロフォームに変えるだけで、時速30㎞走行時にノーマルフォームと比較して、エアロフォームでは出力(パワー)を20%以上抑えることが可能だ。レース中は、つねにエアロフォームで走り続けるのではなく、3つのフォームを使い分けることが大切だ。
ノーマルフォーム

エアロフォームを取らないときの通常のフォーム。視線を高く保つことができ、上体をリラックスできるため、レース序盤など集団内にいるときに有効。

セミエアロフォーム

ノーマルフォームと同じくハンドルのブラケット部分を握った状態で、エアロ姿勢をとるフォーム。ヒジを曲げて、やや脇を締めるように意識する。

エアロフォーム

ハンドルのドロップ部分を握り、上体を下げて前面投影面積を最大限減らす。

上り坂をライバルよりもラクして上る

ライバルよりも省エネで走ることが勝敗に影響するロードレース。そこで使えるテクニックのひとつが、登坂区間の走り方だ。坂を集団の前方で上り始め、坂のピークに向けて集団の後方まで下がりながら走る。これによりライバルよりも省エネで登坂区間をクリアできる。ピークで集団の後方につけるように、登坂区間を最大限に使って出力を抑える意識が大切だ。なお、登坂の直前に急激にポジションを上げるような走りは、集団の秩序を乱すためやめたい。
集団を利用した登坂の省エネな走り方
登坂区間では集団が活性化することが多いため、集団の最後尾で登坂に入ると集団が伸びてムダ脚を使うこともあるので注意。先頭で登坂に入って省エネでクリアする場合も、早い段階で集団最後尾にポジションを落とすのではなく、集団の動きを把握しながら省エネで坂道を消化していきたい。

教えてくれた人

グランフォンド プロサイクリスト
紺野元汰
高校時代から競技を始め、実業団国内トップカテゴリーで活躍。2018年、ツール・ド・おきなわ市民210㎞優勝。2019年、UCIグランフォンド世界選手権3位。
※この記事はBiCYCLE CLUB別冊「ロードバイクのトラブル解決マニュアル」からの転載であり、記載の内容は誌面掲載時のままとなっております。
SHARE
PROFILE

Bicycle Club編集部
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。