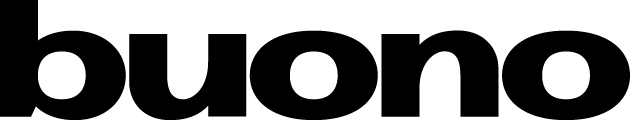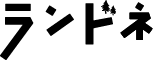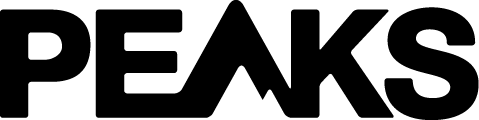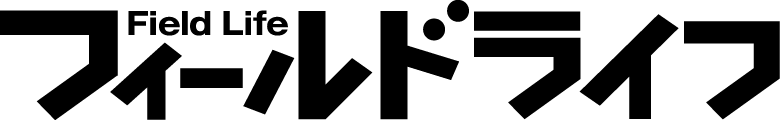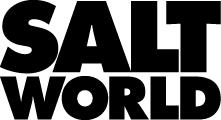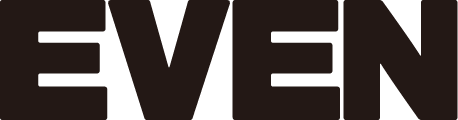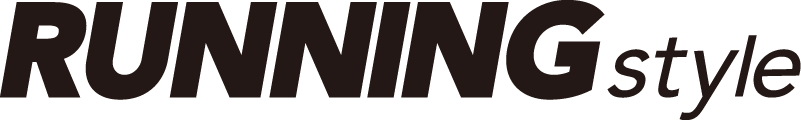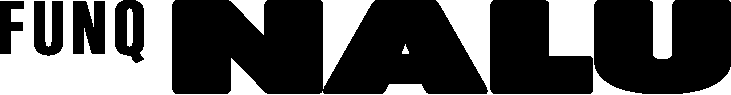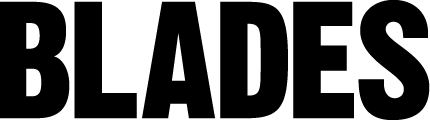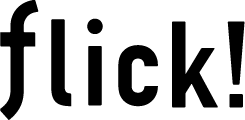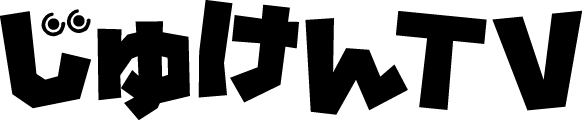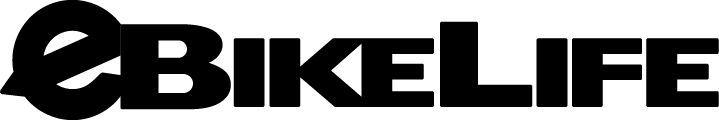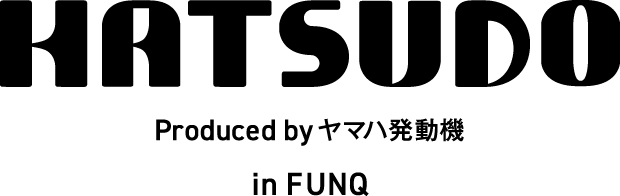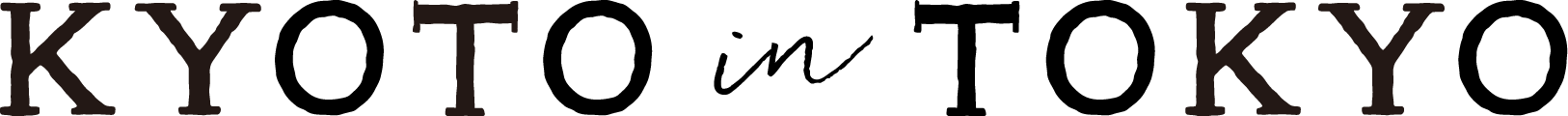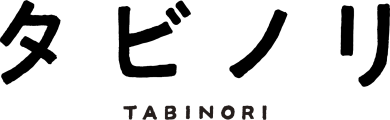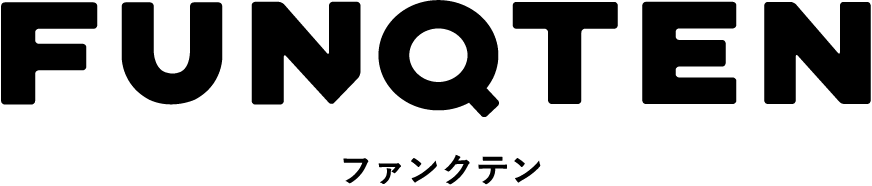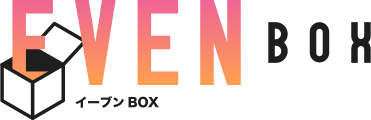どの器で呑む?酒の味わいをがらりと変える酒器の奥深さ 『大塚 はなおか』
buono 編集部
- 2016年10月03日
酒の味をがらりと変える酒器の存在
この世に酒は数あれど、日本酒ほど多彩な酒器が揃う酒はないだろう。陶器やガラス、漆器といった素材の豊かさ、はたまた形状の違い。それは日本酒をより旨く味わうための先人たちの知恵の結晶でもある。 東京・大塚にある『大塚 はなおか』の店主である花岡賢さんは、日本酒好きが集まる大塚界隈でも名の知れた日本酒通。酒の状態や料理との相性だけでなく、酒を注ぐ酒器にも細やかな気配りを欠かさない。扱う日本酒は約40種類だ。 「何度も蔵に通い顔を見て、これぞ、という酒を選んでいます。“蔵元の人生を飲む”という意識ですね」 酒器は、酒の味をも変えてしまうほど重要な存在。素材や形状が持つ特徴を知れば、日本酒の飲み方も変わってくるはずだ。
酒器の形で変化する味と香り
ワイングラスに様々な形があるように、ぐい呑みなどの酒器の形も多彩だ。酒器の形によって、酒の味わいが変わることをご存じだろうか。
酒器の形状と日本酒との相性を探り、香りや味の違いを楽しむ飲み方をしてもいいじゃないか、と生まれたのが、岐阜県にある「カネコ小兵製陶所」製の「一献盃」だ。日本酒をもっと身近に楽しんでもらいたいという思いから、4種の形状の盃を製作。素材は、もっとも酒への影響が少ないとされる磁器を使用している。1つの日本酒を4つの器で飲み比べ、味や香りの違いを楽しむのもいいだろう。はたまた、1つの日本酒に対して最適な酒器はどれなのか、選び抜く作業も面白い。

ストレート:口径が小さいので細長く直線的に酒が口の中に入る。「すっきり、さっぱり」感じられる。

つぼみ:味わいは中間くらい。口径が小さく、くくっているので、香りに鼻を突っ込みながらチビチビと舌先で舐めているような味わい方になる。

ボウル:ある程度の口径があり腰が張っているため、舌の真ん中に酒が多めに入る。酒の旨味、甘み、味わいをしっかり長時間、感じられる。

ラッパ:他の3つとは異なり、味を見る分析系の酒器。酒が喉に至るまでの間に、口腔から鼻に抜ける香りを十分に感じ、複雑に味わうことができる。
目と耳でも味わえる酒注を選ぶ
日本酒は本来、樽から枡で計って徳利などの容器に分ける。酒注(さけつぎ)には、持ち運ぶための大徳利から、酒盃に酒を分け注ぐための徳利や片口、燗酒のためのチロリなど様々な種類がある。素材も陶磁器、金属、ガラスなど多様だ。 中でももっともポピュラーなのは徳利だろう。鎌倉時代頃までは瓶子が使われていたが、次第に使い勝手のいい形とサイズの徳利に変わっていった。注いだ時に「トクトク」と音がするものが好まれるが、その音は酒好きにとってはたまらない。舌や目で楽しむだけでなく、耳でも酒を味わえるオツな酒注ぎだ。徳利は陶磁器を中心に形や色柄が多種揃い、酒盃と共にコレクションする人も多い。 一方、チロリは金属製の燗酒の専用酒器。銅、錫、ステンレスなど素材によって味わいに大きな変化をもたらす魔法の酒注だ。
DATA
大塚 はなおか(おおつか はなおか)
住所/東京都豊島区南大塚1-51-18 高橋ビル1F
TEL/03-5395-6707
営業/17:00~23:30(最終入店22:00)
休み/不定休
http://nihonsyuhanaoka.wixsite.com/nihonsyuhanaoka
SHARE
PROFILE

buono 編集部
使う道具や食材にこだわり、一歩進んだ料理で誰かをよろこばせたい。そんな料理ギークな男性に向けた、斬新な視点で食の楽しさを提案するフードエンターテイメントマガジン。
使う道具や食材にこだわり、一歩進んだ料理で誰かをよろこばせたい。そんな料理ギークな男性に向けた、斬新な視点で食の楽しさを提案するフードエンターテイメントマガジン。