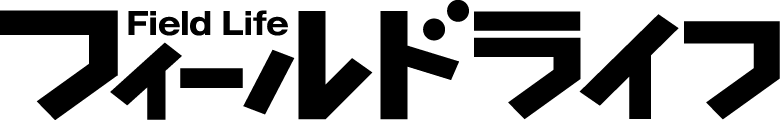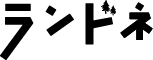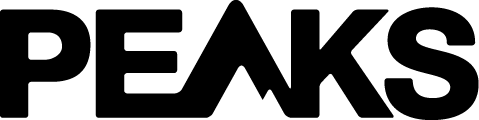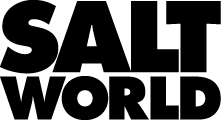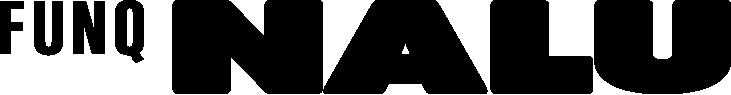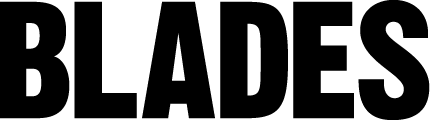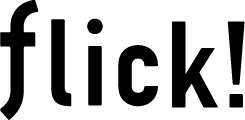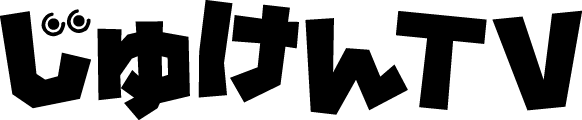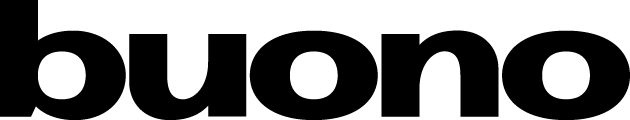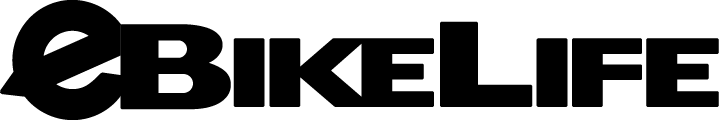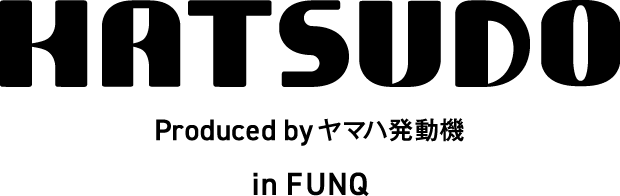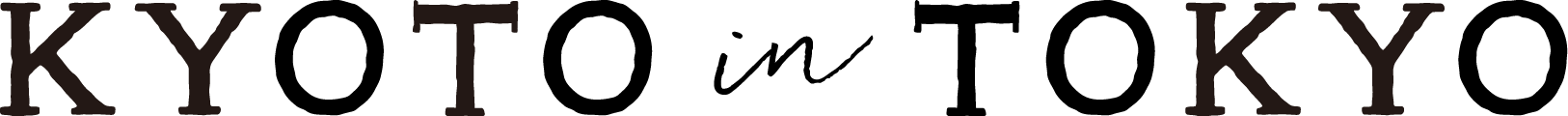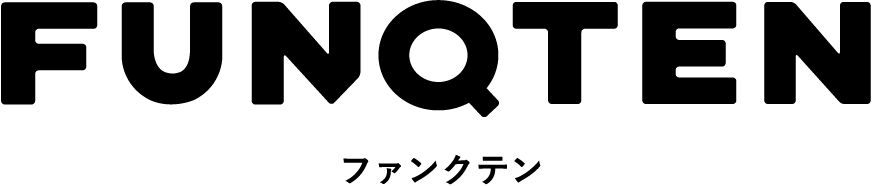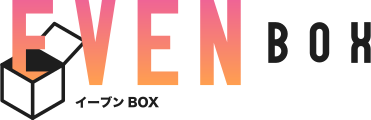野田知佑さんが下る千曲川
フィールドライフ 編集部
- 2020年11月22日
カヤックという遊びと“アウトドア”という真の意味を日本に根付かせ、
78歳になったいまでも現役で国内外の川をめぐるアウトドア界のレジェンド・野田知佑。15年連続で下り続けている信州の大河に、今年も犬とともにやってきた。
文◎森山伸也 Text by Shinya Moriyama
写真◎大森千歳 Photo by Chitose Omori
出典◎フィールドライフ No.53 2016 秋号
遊んでなんぼのジンセイがあることを、ぼくらに教えてくれた。

カヌーイストであり作家の野田知佑さんは、おそらく外遊びをやる若者の人生にもっとも影響を与えた男である。自分の好きなことをして、遊んで食べている大人がいるという事実だけで、悶々とした20代には世界が明るく見えたものだ。

かくいうぼくも野田さんの本に感化され「やりたいことをやって生きていこう」とカヤックを買い、世界を放浪し、定職につかず、遊んでいるうちにアウトドアライターになり田舎へ引っ越した。
野田さんに出会わなかったらいまごろ、暗い顔して窓際族になっていたかもしれない。ありがとう、野田さん。
このような人間がぼくの周りにはたくさんいる。
78歳になった野田さんがここ15年間、毎年カヤックで下っている川がある。日本一長い千曲川だ。

今年も9月10日、野田さんが千曲川の河原にやってきた。長野県飯山市にある自然体験型宿泊施設「なべくら高原・森の家」が主催するツーリングイベントで、今年で記念すべき15回目を迎えた。

33名のカヤッカーが北は北海道、南は沖縄西表島から集結。子ども連れの家族から独身女性、犬を連れたアラフォー男、定年間近の夫婦まで、野田さんが年齢性別を問わず老若男女から慕われていることが参加者の面々でわかる。

「天気もいいしいっぱい沈しよう」。野田さんのかけ声でスタッフ合わせて39挺のカヤックが川面に浮かんだ。パドルをわしわし動かすことなく、風景に身をまかせゆったりと下っていく。
野田さんが初めて千曲川を下ったのは、いまから約35年前の9月中旬。まさに夏が終わろうとしているいまごろの時期だった。

デビュー作である『日本の川を旅する』(新潮文庫)にそのときのようすをこう綴っている。「朝四時か五時に起きて、川が一番気持のいい時に釣りをし、本を読み、ゆっくり時間をかけて十時頃出発。川の上に出ても移り変わる景色の一つ一つに参加しながら下る。決して急がない」

川、山、空、風……すべてひっくるめた森羅万象を身構えることなく自然体でのんびり味わうスタイルはいまも変わっていない。ウィスキーはビールに変わったけれど。

谷間に轟々と響く2級の瀬が近づいてきた。デッキをざぶんざぶんと波が洗い、流芯が「く」の字にカーブしている。

だれかが隠れ岩に弾かれ、沈をした。あちこちから笑いと拍手が生まれる。通常生まれるだろう悲壮感がそこにはない。ここでは沈した人がヒーローになれるのだ。

JR飯山線替佐駅から14㎞下って、今日のキャンプ地、飯山カヌーポートに上陸した。野田さんと愛犬アレックスが乗っていたダブル艇を覗いてみると、座席が乾いている。さすがである。

みんなで焚き火を囲むと野田さんがハーモニカで唱歌「故郷(ふるさと)」を奏でた。その横でアレックスが火の粉に飛びつき、ハナは足元で寝ている。この「故郷」は今日下ってきた旧豊田村の千曲川流域をモデルにして作られた歌だ。
弦月が雲の間から顔をのぞかせ、ススキをやんわり照らした。

「ニュージーランドはいいぞ。民度が高い。レンタカーを運転していたら交通違反で警察に捕まったんだ。『いつ来たんだ?』『昨日だ』って返したら『ならしょうがない。行ってよし。よい旅を』っていうんだ。組織の底辺にいる警官が自分の意思で判断している。あそこはすばらしい国だよ。みんな行ったらいい」
野田さんの話はカヤックの旅にとどまらず、国際情勢、プロ野球、西部劇、幼少期の思い出など多岐にわたる。これがおもしろい。78年間、野田知佑という自由人のなかに積み上げられてきたバックボーンについて話を聞けるのもこのイベントの醍醐味だ。
そんなこんなで野田さんと焚き火を囲む宴は、25時半まで続いた。野田さん、元気すぎます。

2日目は、おもだった瀬もなく艇を寄せあい話しながら12㎞を下った。
「森山、田舎の生活はどうだ、望んだものになっているか?」
野田さんはいつも後輩のぼくらのことを気にかけてくれる。「おれは43歳でようやく人生の進む方向が定まって、食えるようになった。アセることはないよ」
閉会式をする横でひとりの小学生が川に浸かってプカプカ浮いていた。野田さんはずっとニコニコしながら彼を見守っていた。

先輩ヅラをせず、大人ヅラもしない。ただただその人の個性と自主性を楽しむように、重んじる。
野田さんはつくづく人間が好きなのだ。川を旅するのも、その流域に人が住んでいるから。人間による習慣や文化が根付いているから。著書を何度も読み返すたびにその憶測は確信へと変わっていく。
そして千曲川に通うのも、そこにみんなが待っているから。

「来年もやりましょう。もっと沈できるイベントを考えような」
今回が最後かも? と心配している参加者やスタッフは、毎年このセリフを聞いて安堵し、顔を見合わせ笑うのである。
- BRAND :
- フィールドライフ
- CREDIT :
-
文◎森山伸也 Text by Shinya Moriyama
写真◎大森千歳 Photo by Chitose Omori
SHARE
PROFILE

フィールドライフ 編集部
2003年創刊のアウトドアフリーマガジン。アウトドアアクティビティを始めたいと思っている初心者層から、その魅力を知り尽くしたコア層まで、 あらゆるフィールドでの遊び方を紹介。
2003年創刊のアウトドアフリーマガジン。アウトドアアクティビティを始めたいと思っている初心者層から、その魅力を知り尽くしたコア層まで、 あらゆるフィールドでの遊び方を紹介。