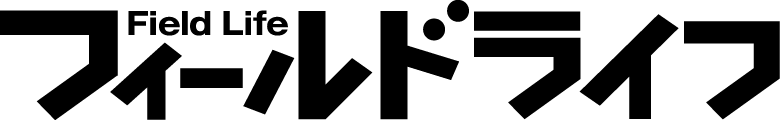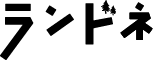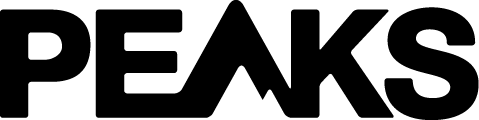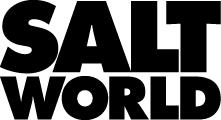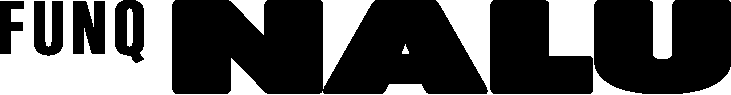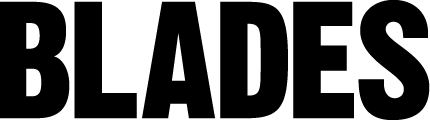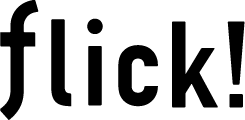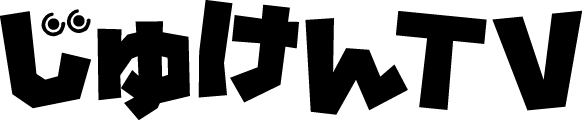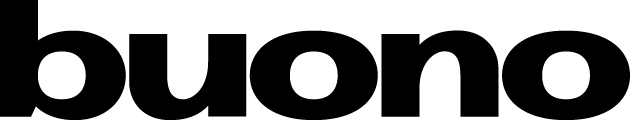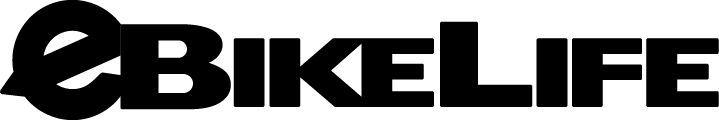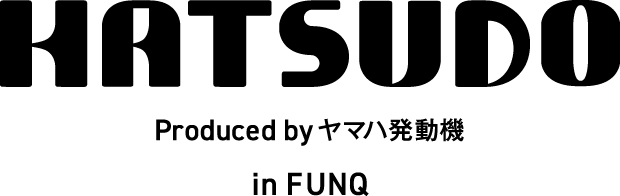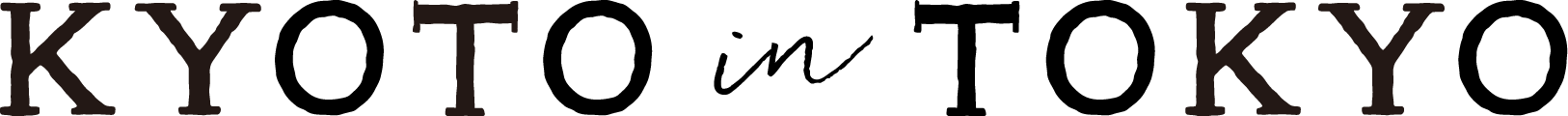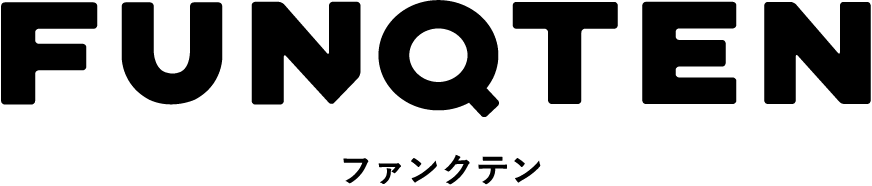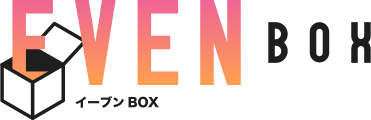犬と歩くひみつの渓谷|ホーボージュンの全天候型放浪記
フィールドライフ 編集部
- 2021年06月05日
犬と歩くひみつの渓谷
短かった冬が終わりにさしかかり、あちこちで春が囁かれ始めたころ僕は愛犬のラナを連れ、だれもいない渓谷へ旅に出た。ラナとはこの14年間、日本中の山、川、海を旅してきたけど、こうしていっしょに野宿ができるのも、たぶん、あともう少しだ。僕は半分泣き顔で、だけど幸福を噛みしめながら、かけがえのない時をすごした。
文◎ホーボージュン Text by HOBOJUN
写真◎大森千歳 Photo by Chitose Omori
出典◎フィールドライフ No.67 2020 春号
奇跡のような美しい川でキャンプを張った。

だれもいない渓谷をラナは楽しそうに進んでいく。背中に背負ったバックパックが左右に揺れ、リードを通してその喜びが僕の手にも伝わってくる。
こんなふうに歩く姿を見るのはひさしぶりだ。歌うように振られるシッポを見るだけで、目の奥がツンとする。それがシアワセのせいなのか、それとも悲しみや寂しさからくるものなのか、僕にはもうわからない。
モリコはそんなラナを追い立てるようにグイグイと突進している。さすがにまだ若いだけあり、四肢の動きに躍動感がある。クライミングロープで作ったリードを引きちぎらんばかりの勢いだ。
「こら! モリコ!」。森山伸也が叱りつける。普段は飼い主に絶対服従のモリコだが、今日ばかりは言うことを聞かない。ひさしぶりに会うラナと遊びたくって仕方ないのだ。
3月の上旬、僕はアウトドアライターの森山と彼の愛犬モリコを誘い、とある渓谷をトレッキングしていた。本当はバックカントリーに滑りに行こうと思っていたが、あまりの暖冬に諦めたのだ。
「ひさしぶりに犬と旅しようぜ」。そう誘うとふたつ返事でOKがきた。森山もまた今年の雪の少なさに辟易し、退屈な冬をすごしていたところだった。

こうしてすぐ日程は決まったが、どこの山に行くかについては少々悩んだ。登山者でごった返すような有名エリアは避けたかった。余計な軋轢を生みたくないからだ。
これには森山も同意見だった。いま森山は新潟の山奥に住んでいるが、そこに引っ越したのは都会の窮屈さと犬への偏見にうんざりしたからでもある。先日、森山はこんなツイートをしていた。
「15年住んだ東京は息苦しかった。犬を放せば怒られるし、裸足で外を歩けば白い目で見られ、焚き火をしたら通報される。だからぼくは山奥へ移り住んだ。自然にもまれて生きてきた集落の人は、なにに対しても寛容で僕の存在をおもしろがっている。多様性をおもしろがる田舎は生きやすい」
そんな僕らは場所が特定できるような有名スポットを避け、だれも知らない山域を旅先に選んだ。こんなに美しい写真を見せておいて申し訳ないが、今回の場所はここには書けない。この川の名前は「ひみつ川」、この山の名前は「ひみつ山」だ。

初日にキャンプを設営したのは、腰が抜けるほど美しい場所だった。川は目の奥が痛くなるほど青く、水はまるで真空管のようで、ガラスのように凪いだ川面から中を覗き込むと、信じられないほど巨大なアマゴが(僕は最初コイかと思ったほどだ)悠々と流れを下っていくのが見えた。
「すごいところだなあ……」「奇跡の川ですね、ここは」。あまりの美しさに固唾を呑む。僕も森山も四万十川や仁淀川、尻別川など全国の清流を旅してきたが、これほど美しい川はそうそうない。しかも完全に無人。あまりのシアワセに怖くなるほどだ。

「ワン!ワン!」。リードを外してフリーにしてやると犬たちは大喜びで走り回った。この二頭は同じ犬舎の出身だ。
いまから8年前、僕は犬ぞりの旅に出るためにラナをしばらく森山に預けていたのだが、森山はそのときの暮らしがよっぽど楽しかったらしく「俺もボーダーコリーを飼う!」と言い出し、モリコを迎えた。だからモリコにとってラナは母か姉のような存在なのだ。
人間が一番と思ったらそれは大間違いだ

翌日は渓谷の支流を突き詰めた先にある「ひみつ山」に登ってみることにした。小型パックに簡単な装備を詰め込み、沢で汲んだ水をナルゲンに入れて歩き始める。
犬たちにもバックパックを装着した。自分の水や行動食は自分で運ばせるのが僕らのルールだ。ラナは生後10カ月で南アルプス縦走を果たし、その後も3000m峰や厳冬期の雪山など、ガチな登山を経験してきた。でもそういったハードな登山はもう止めさせようと僕は考えていた。
じつは先月、燧ヶ岳のバックカントリーにラナを連れて行ったのだが、山のなかでまったく歩けなくなってしまい、抱きかかえて下山する事態になった。本人にはそれが相当ショックだったようで、その後1週間ぐらい落ち込んでいたが、僕にとってもそれは同じ。年老いた母の姿を見てしまったような、複雑でなんともやるせない気持ちになったばかりだ。
でもそれは仕方のないことだった。ラナはもう14歳である。ニンゲンでいえば98歳のおばあちゃんなのだ。飼い主のわがままに突き合わせるわけにはいかない。だから、今日はあまり無理をせず、稜線歩きを主体にした日帰りハイキングを楽しむことにした。

「ラナ!ツケ!」「モリコ!アトへ!」
二頭の犬にコマンド(命令)を出し、整列して歩かせる。ボーダーコリーという犬種は飼い主の命令に従って働くことを生き甲斐としている。だからグイグイと前進しているときにも耳はつねに後を向いている。
「ラナ!左!」。僕の声でラナが左を向く。ハッハッハッハッと短く息をしているのはそれを喜んでいる証拠だ。
知らない人の前でこれをすると「右」とか「左」とかの実態のない「概念」を犬が理解することに驚かれるが、じつはラナはもっと賢く「左へ大きく回り込め」とか「ゆっくりと間隔を空けて付いてこい」というような複雑なコマンドもこなすことができる。
ちなみにかつて『ナショナルジオグラフィック』に「天才犬」として取り上げられたベッツィというボーダーコリーは、大型類人猿よりも言葉の覚えが速く、340語もの単語を理解し、少なくとも15人の名前と顔を覚えて、写真と実物を結びつけることができた。

「動物の知力」と題されたこの特集は世界中に衝撃を与えたが、すでにボーダーコリーと暮らしていた僕はそれほど驚かなかった。当時ラナはまだ4歳の若犬だったが「○○くんのお父さん呼んできて」と言えば間違いなく呼びに行ったし、散歩からアパートに帰ると風呂場に貯めた水で足を洗い、バスマットの上をグルグルと回って肉球を乾かしてから部屋に入ったからだ。
犬の潜在能力というのは僕らの想像を遙かに上回る。人間が賢いだなんて思っていると、とんでもない恥をかくことになる。
ヒメシャラの森を抜けてひみつ山の稜線を歩く

ひみつ山の中腹にはヒメシャラの森が広がっていた。樹皮がスベスベしていて猿ですら滑り落ちることからサルナメリとかサルスベリとも呼ばれる。小さな葉が涼しげな木陰を作り、夏になると椿に似た小さな白い花をつける。
僕は昔住んでいたアパートの庭にヒメシャラの若木を植えていた。ラナは幼犬のころよくその木の下で遊んでいた。それを思い出すのか、それともひさしぶりの山が楽しくて仕方ないのか、さっきから口角をあげて笑っている。犬が笑うというのは本当のことだ。

「ラナ、元気になってよかったですよね」。楽しそうなようすを見て森山がしみじみと言う。じつは去年の春にラナは大病を患った。急性腎炎という犬にとっては致命的な病気にかかり、一時はほんとうに危なかった。
ありがたいことにラナはなんとかもちこたえ、徐々に体力を回復し始めた。その後僕はブータン王国へ旅に出ることになり、留守の間ラナは森山のところでリハビリ生活を送っていた。だから彼はラナの健康状態をよく知っているのだ。

トレイルは快適で、歩きやすかった。それでもところどころに倒木や石段などの障害物があり、老犬の行く手を阻んだ。そんなときラナは「クーン」と鼻を鳴らして僕に助けを求めた。
「しょうがねえなあ。お前もすっかりポンコツだよな」。そんな悪態をつきながら、僕はハーネスでラナを釣り上げ、障害物を越えさせてやる。なるべく身体に負担がないように。そしてなるべく彼女の自尊心を傷つけないように。
「ドッグイヤー」という言葉があるとおり、犬はニンゲンの7倍ものスピードで歳を取っていく。赤ん坊だったラナがぐんぐん大きくなり、たくましい若犬となり、やがて知恵と勇気と体力を備えた立派な成犬になるのを、僕はタイムラプスの映像を見るように見守った。
やがて僕と同じ歳になり、あっという間に母親の歳になり、いまは本当に遠くまでいってしまった。かつては僕があちこち連れて歩いたが、いまは彼女の後ろ姿を見失わないように必死で歩いている気がする。
焚き火と酒と犬が教えてくれること

キャンプサイトに戻った僕らは流木を集め、焚き火を熾した。あいかわらずだれもいない。そしてあいかわらず川は美しかった。
今回の3泊4日の旅の間、食事はすべて焚き火で作った。といっても鍋もフライパンも持ってきていなかったので、担ぎ上げた食材を焚き火で炙って喰うだけの原始的なメシだった。
そのかわり酒だけは浴びるほどあった。それは僕にとっても森山にとっても、これ以上ないご馳走だった。

ソーセージを炙ってビールをグビグビ。ベーコンを炙ってバーボンをチビチビ。焚き火を眺めながらいつのまにかウトウト。犬に起こされ千鳥足で川へフラフラ。冷たい水で顔を洗い、小便をして焚き火に薪をくべ直す。
こんな幸せな夜があるか。これ以上の夜があってたまるか。

こいぬ座のプロキオンがテントの真上に登るころ、犬たちはアクビを連発し始め、僕も観念してテントに入った。長毛のラナは焚き火の煙にとことん燻され、まるで燻製みたいな臭いがしている。
「おまえ、焚き火くせーよ」。そういって寝袋に包まったけど、僕もラナと同じ臭いがした。ラナが若いころはいつもテントの前室で眠らせていた。夜中に食糧を狙ってやってくるネズミやタヌキやキタキツネを追い払わせるためだった。

でももういいや。寒い思いをさせたくない。テントに入れて自分の寝袋をかけてやった。
ラナは僕の胸元に鼻先を入れると、クークーと寝息をたて始めた。それを聴きながら、僕はボロボロと涙が止まらない。いかんいかん。調子に乗って飲みすぎたかも。
これまで数え切れないほどの夜をラナといっしょにすごした。そんな旅のなかでラナが教えてくれた一番のことは「いまを生きる」ということだ。
アウトドアを旅することは、いまを生きるということだ。大自然のなかでは一秒一秒が意味をもつ。過去や未来はどうでもいい。いまをどうすごすか、どう生きるかにすべてが集約されている。

僕らニンゲンはバカだから、普段はその感覚を失ってしまっている。それを思い出すのはアウトドアに出て、厳しい状況に晒されたときぐらいだ。でも犬たちは、ずっとそれを知っている。だから毎日毎日、一秒一秒を全力で生きているのだ。

ラナはもう14歳の老犬だ。ぜんぜん無理が効かなくなったし、この先いつまで歩けるかわからない。でもトレイルを駆けながら嬉しそうに笑う口元は、そしてじっと僕を見つめるまっすぐな瞳は、いっしょに山を歩き始めたころからぜんぜん変わっていない。ラナ。愛しのラナ。いつまでもこうして旅をしよう。
- BRAND :
- フィールドライフ
- CREDIT :
-
文◎ホーボージュン Text by HOBOJUN
写真◎大森千歳 Photo by Chitose Omori
SHARE
PROFILE

フィールドライフ 編集部
2003年創刊のアウトドアフリーマガジン。アウトドアアクティビティを始めたいと思っている初心者層から、その魅力を知り尽くしたコア層まで、 あらゆるフィールドでの遊び方を紹介。
2003年創刊のアウトドアフリーマガジン。アウトドアアクティビティを始めたいと思っている初心者層から、その魅力を知り尽くしたコア層まで、 あらゆるフィールドでの遊び方を紹介。