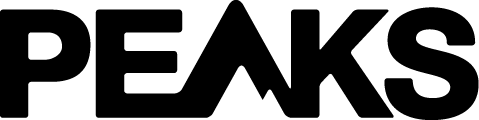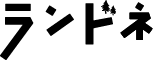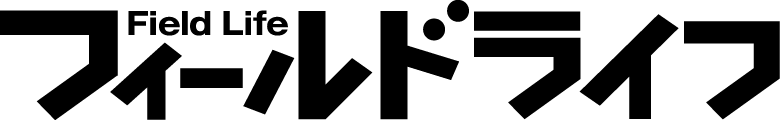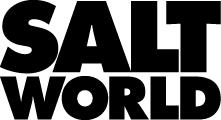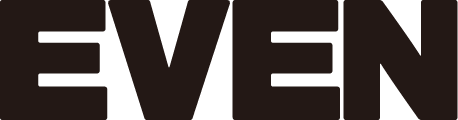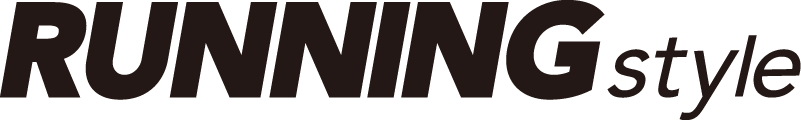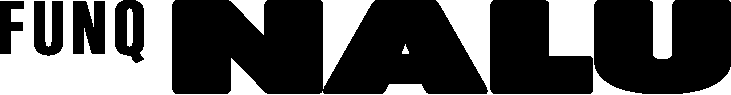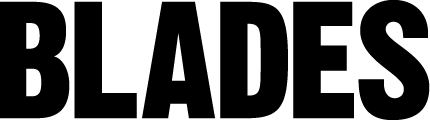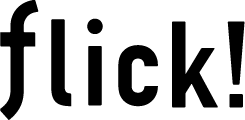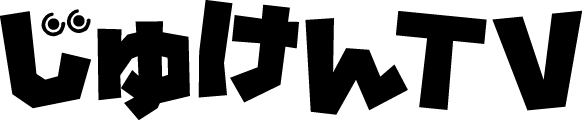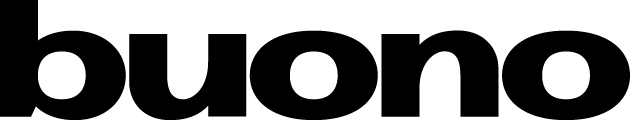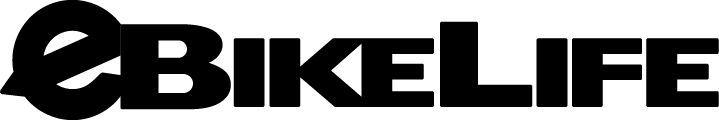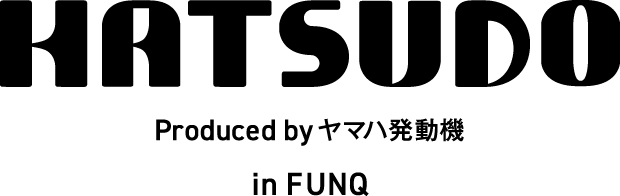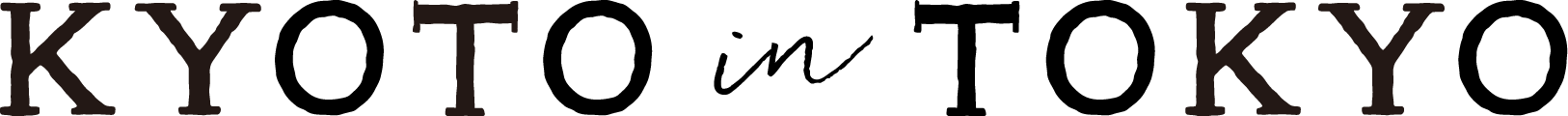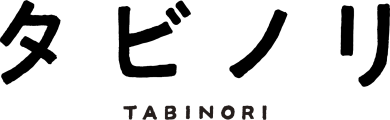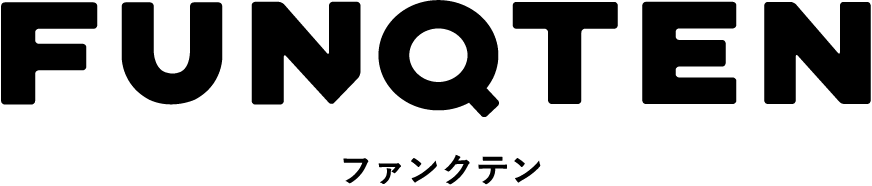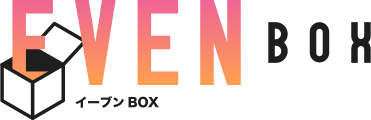【日帰り登山】島旅で登りたい山!4ルート|(PEAKS 2024年3月号 今年登りたい日帰りの山58)
PEAKS 編集部
- 2025年04月25日
3,000m級の山々を擁する日本は魅力的な山がたくさん。
そこで、「餅は餅屋」の言葉にちなみアウトドアを仕事としている全国の登山愛好家に今年登るべき日帰り登山におすすめの山を聞きました!
***
海の上に浮かぶ魅惑の頂。
海を渡り、本土とは違った独特の風土を楽しめるのが島旅の魅力。
さらにその島にある山に登ることで、より深くその土地の自然を堪能できるだろう。
①利尻島・利尻山【北海道】
・歩行時間:7時間30分
・距離:約13km
・撮影時期:8月
■大海原に浮かぶ「利尻富士」。
いわゆる〝郷土富士〞のひとつで、「利尻富士」とも呼ばれるのが、利尻山(りしりざん)。たしかに富士山のように裾野が延び、とくに海上から見る姿は美しい。だが、実際は本家の富士山よりも起伏に富んで荒々しく、山頂を中心に明瞭な尾根と谷が幾重にも刻まれている。
そのなかでも鴛泊(おしどまり)コースがある北稜の登山道は最高!森を抜けてから現れる第1/第2見晴台はもちろんのこと、山頂までつねに絶景を楽しみながら歩き続けることができる。そして、それ以上に山頂からの眺めがすばらしいのである。
山頂付近は崩落がひどく、最高地点の本峰には立つことはできなくて、登れるのはそのすぐ手前の北峰まで。だから山頂からは360度の眺望……とはいえず、南側に北峰よりも3mだけ高い本峰が見えるというのもおもしろい。
だが、そんな眺望を味わえるのは、やはり晴天時。僕は悪天候時に登って、なにも見えないどころか強風・強雨で避難小屋に逃げ込んだことがある。寒くてツラかった……。
利尻島は道内でも海産物がおいしい場所だ。悪天のときは海辺の食堂ですごすほうが、よい思い出になるだろう。



アクセス
飛行機や鉄道で稚内まで移動したうえで、稚内港からフェリーで利尻島の鴛泊港へ。登山口まではタクシーを使う。鴛泊の街から登山口まで歩く場合は、1時間30分ほどかかる。

コメント:山岳/アウトドアライター 高橋庄太郎
北海道だけどヒグマはいないし、とくに夏は北国らしいさわやかな空気が気持ちいい! 登山口のテント場
で前日泊すれば、日帰り登山+キャンプという楽しみ方もできます。

②佐渡島・金北山【新潟県】
・歩行時間:7時間
・距離:約14.6km
・撮影時期:9月
■豊かな植生と歴史文化、海岸線が望める縦走路。
佐渡島の最高峰である金北山(きんぽくさん)。金剛山、檀特山とともに佐渡の三大霊山とされ、かつては女人禁制の修験の山で「三山駆け」が行なわれていたそう。山頂には金北山神社があり、縦走路には役行者(えんのぎょうじゃ)像が置かれているなど、信仰の歴史をも感じさせる山だ。
アオネバ登山口からの登りはじめは緑が茂る豊かな原生林。佐渡島は北緯38度をまたいでいることにより、北方・南方の地域の植物が見られる希少な環境であり、さらには島の固有種も含め、約1700種ほどの植物で形成される「花の島」でもある。また、「アオネバ」の名前の由来でもある、青い粘り気のある粘土層が多く見られ、佐渡島ならではの植生・地質ともに楽しめる。
金北山への縦走路は大佐渡を貫く分水嶺で、マトネ〜金北山までの稜線がこのコースのハイライト。標高1000m前後程度であるにもかかわらず高山帯や亜高山帯の植生が見られ、北アルプスなどの高山にも劣らない雄大な景色が広がる。なかでも「真砂の峰」からの景色は絶景で、左手に国中平野、右手には外海府が望め、〝佐渡島を縦走している感〞で満たされるだろう。



アクセス
両津港からタクシーで20分。登山口には数台駐車可能な臨時駐車場もある。下山口からもタクシーを利用(両津港まで50分)。無料駐車場あり。春期限定のライナーバスもある。

コメント:編集者・ライター 阿部 静
歩きごたえのある縦走路。花の時期もいいけれど、登山者の少ない9月以降は静かな山を堪能できておすすめです。稜線の標高は1,000m前後でも風が強いので防寒対策も忘れずに!
③神津島・天上山【東京都】
・歩行時間:3時間50分
・距離:約4.7km
・撮影時期:6月
■伝説が残る、神々の話し合いの舞台。
神津島(こうづしま)は、東京湾の南海上に浮かぶ伊豆諸島のひとつ。本州にいちばん近い伊豆大島から数えて5番目の有人島で、港区にある竹芝客船ターミナルから向かうと、高速ジェットで約3時間、大型客船で約10時間かかる距離にある。
いまは「神津島」と書くが昔は「神集島」と書いたそうで、かつて伊豆諸島の神々が集まり水を配る話し合いが行なわれたという伝説が残る。ただ、話し合いといっても配分は先着順に行なわれ、朝寝坊していちばん遅く到着した利島の神は、水がほとんど残っていないことに腹を立てて暴れ回ったと伝わっている(ちょっと子どもっぽい)。
その話し合いが行なわれた場所が天上山(てんじょうさん)の山頂付近にある「不入ガ沢(はいらないがさわ)」で、いまも足を踏み入れてはいけない神聖な場所とされている。
道中にはほかにも、荒涼とした平坦地が広がる裏砂漠や表砂漠、雨後に水が溜まると現れる火口跡の千代池などが点在し、終始興味深いハイキングを約束してくれる。



アクセス
登り口は黒島登山口と白島登山口のふたつ。黒島登山口から登るほうが初心者向きとされている。いずれも港から徒歩、車、バスでアクセス可能。バスの運行状況は神津島村役場のHPで確かめてもらいたい。

コメント:山岳ライター 吉澤英晃
通年ハイキングを楽しめ、なかでも花が咲く5 ~ 6月がおすすめです。標高は低いですが、序盤は高低差280mの急登が続くので靴やウエアなど装備はしっかり準備しましょう。

④石垣島・ぶざま岳【沖縄県】
・歩行時間:3時間15分
・距離:約7.5km
・撮影時期:1月
■目的地は、山頂よりも絶景の展望台。
晴れていれば冬でも汗をたっぷりかくほど暖かいのが、沖縄南部の八重山諸島。その中心となる石垣島には登山に適した山が点在するが、そのなかでも〝穴場〞なのが、島西部に位置するぶざま岳である。
地元民ですら〝あの山に登れるの?〞というほどマイナーで、登山地図アプリでもルートが紹介されていなかったりする。だが石垣市が2017年に行なった市制施行70周年記念プロジェクト「島人ぬ宝さがし」では、ぶざま岳中腹の絶景テラス(展望台)が〝島の宝〞のひとつに選定されているのだ。
登山口から鬱蒼とした亜熱帯ジャングルの道を進み、分岐らしき場所を曲がる。そしてヤブのなかに青空が見えてくると、突然のように大きな花崗岩の上の展望台に出る。
すると、目の前には白砂とサンゴ礁でブルーのグラデーションを描く美しい海!国の名勝でもある川平湾だ。涼しく吹き付けてくる風もじつに気持ちいい。
僕はぶざま岳に3回登ったが、これまでにほかの登山者に会ったことがない。つまり、この絶景をいつもひとり占め。静かな時間が流れている。
そんなすばらしい展望台に対し、ぶざま岳の山頂そのものは、正直なところ登る価値はあまりない。ヤブに覆われ、三角点があることでなんとかそこが山頂だとわかるだけ。目印もなく、GPSで位置確認を行なわないと、多くの人は道迷いを起こすだろう。
展望台との分岐点には山頂方向のルートを遮るようにロープが引かれている。立ち入り禁止ではないが、たしかに展望台にさえ行ければ、この山は十分に楽しめるのだ。




アクセス
バスターミナルから登山口最寄りの崎枝バス停へ片道30分。バスの本数は少なく、レンタルサイクルやバイクなどを利用するのもいい。登山道となる林道への入口はわかりにくいが、舗装路の奥になる。

コメント:山岳/アウトドアライター 高橋庄太郎
“避寒”を兼ねて、冬に行きたいのが、ここ。体力はほとんど必要なく、歩くだけでは物足りないくらいラクなので、展望台ではゆっくり昼ゴハンを食べるような余裕もあります。

※この記事はPEAKS[2024年3月号 No.164]からの転載であり、記載の内容は誌面掲載時のままとなっております。
**********
▼PEAKS最新号のご購入はAmazonをチェック
SHARE
PROFILE

PEAKS 編集部
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。