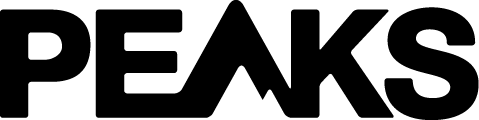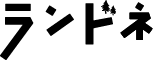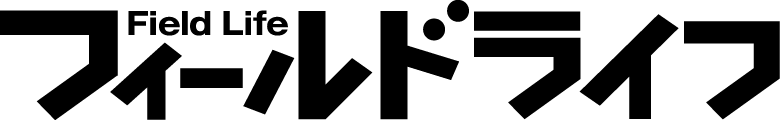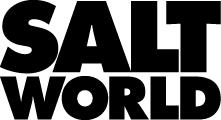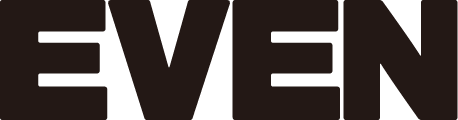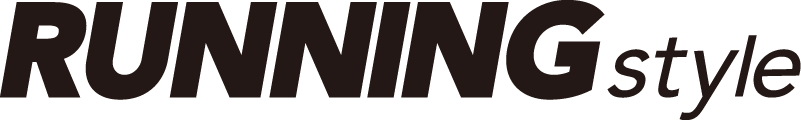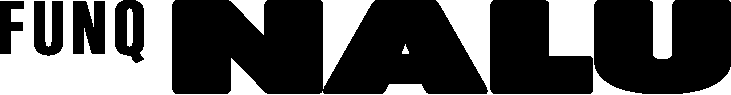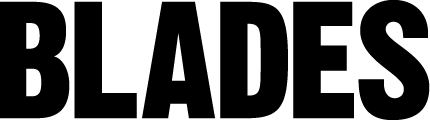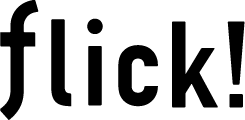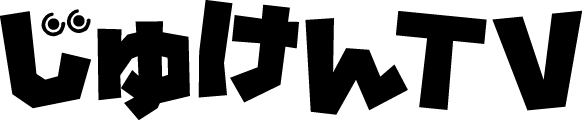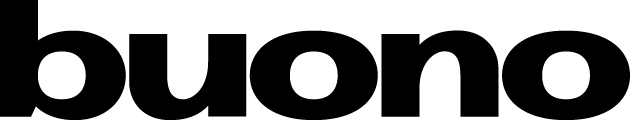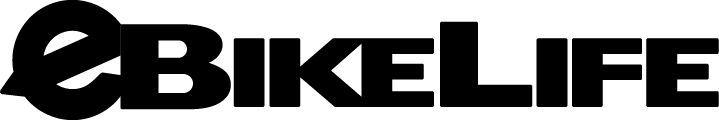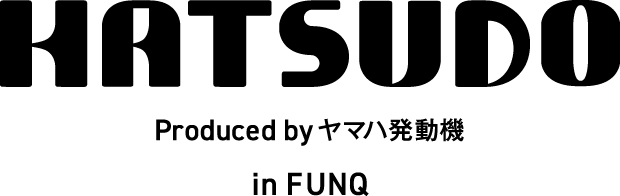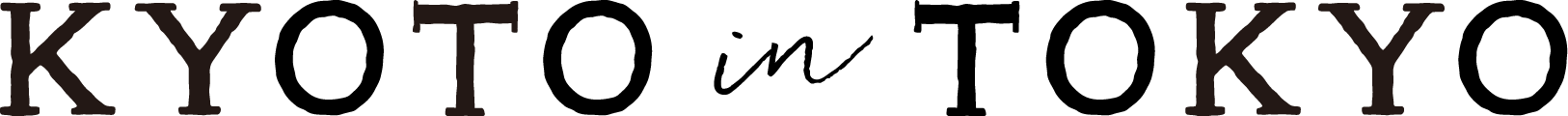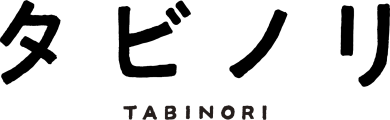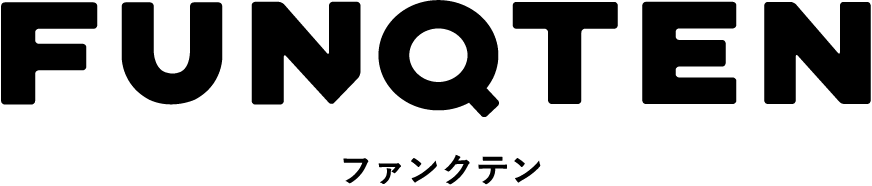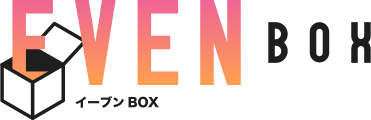【日帰り登山】歴史ロマンを感じる!4ルート|(PEAKS 2024年3月号 今年登りたい日帰りの山58)
PEAKS 編集部
- 2025年03月14日
3,000m級の山々を擁する日本は魅力的な山がたくさん。
そこで、「餅は餅屋」の言葉にちなみアウトドアを仕事としている全国の登山愛好家に今年登るべき日帰り登山におすすめの山を聞きました!
***
山の文化をたどって古に思いを馳せる。
はるか昔から多くの人に歩かれてきた歴史深い登山道を厳選。
太古の空気を感じながら、人々が紡いできた悠久の歴史に思いを馳せてみては。
①武尊山(ほたかやま)【群馬県】
・歩行時間:10時間40分
・距離:約10km
・撮影時期:6月上旬
■修験道を体感する登攀縦走。
日本武尊(やまとたけるのみこと)にその山名のいわれがある武尊山(ほたかやま)は古くから信仰の対象となっており、かつては修験の山としても登られていた。標高こそ2000m程度ではあるものの、頂稜部には8つのピークがあり、裾野を大きく広げた山容を持ち、想像以上に山懐の深さを味わえる。
ここで紹介したいのは、かつて行場として登られていた不動岳ルートである。往復10時間超の長い行程なうえに、10m規模の岩登りがあるので、体力と技術のある中級者以上におすすめしたい。積雪が消える6月上旬から紅葉の10月中旬までが適期である。
登山口となる川場谷野営場から登り、ほどなく分岐となるが、不動岳へは左手をとる。沢を越し、急坂を登ると核心の岩場が現れる。基本技術である三点確保に留意して、慎重に登ろう。大展望の不動岳からはチムニー状の岩場を下りる。足場をしっかり決めてから下ること。剣ヶ峰にも小さな岩場があり、気を抜けない。家ノ串山から山頂までは展望の稜線歩きとなる。下山は前武尊から左手をとり、不動岳は避けたい。



コラム:本格的な岩場登攀
不動岳直下の岩場はほぼ垂直で、登攀要素が強い。クサリに頼りすぎるのは非常に危険。足をうまく使い、握力を保持して登ることがポイント。右に巻くようにつけられた鎖場のほうが、難度が高い。

アクセス
マイカー利用で川場谷野営場(無料、水場なし)にアクセスするのが現実的。沼田駅から野営場までタクシー利用の際は約1時間、¥12,000。川場温泉までは路線バスが運行。温泉に前泊、宿送迎も要検討。

コメント:『山歩みち』編集長 木村和也
武尊山へは大きく4つのルートがありますが、不動岳ルートは難度がいちばん高い登山道。不安な人は北側の武尊神社か東側の武尊牧場からの登山道から登るとよいと思います。

②石割山(いしわりやま)【山梨県】
・歩行時間:6時間
・距離:約14.4km
・撮影時期:5月下旬
■巨岩を祀る石割神社の荘厳さが魅力。
巨石や奇岩を祀る磐座信仰のある山が好きで、これまで日本各地に数多く訪ねている。とくに地元の民話や神話といった地域的な歴史物語をもつ山がおもしろく、たとえば九州や四国、紀伊半島や信州などの「天岩戸」には、個人的に思い入れのある場所が多い。
そんななかで、関東屈指の「天岩戸」といわれるのが、石割山(いしわりやま)に鎮座する石割神社である。山の八合目付近に鎮座する、天岩戸伝承が息づく山だ。神社のご祭神は天あめの手た力ぢから男おの命みことといい、天照大御神が閉じた岩戸をぶん投げて〝戸隠〞に隠した怪力の神さま。転じて、現在はスポーツの神さまなどとして信仰されている。
この磐座には亀裂があり、それが「石」の字に似ていることから石割の名がついた。奥には大きく縦に割れ目があり、三回通ると運が開けるとか。そばには大きなカツラの木と御釜石が祀られ、ここから滴る水が「桂川(相模川)」の源流という。歴史や地理といった側面から地域理解を深めるには、格好の山でもあるのだ。
山頂は迫力の富士山を望む絶景が魅力で、これまた絶景の大平山、長池山を経て、スタート地点の長池親水公園の駐車場へ戻る。そのあいだずっと富士山が、ハイカーを励ましてくれる。




コラム:天岩戸伝説の地のひとつ
姉の天照大御神が弟の素戔嗚命(すさのおのみこと)の乱暴に怒り、岩戸に引き篭る。太陽が隠れた闇のなかで神々は作戦をたて、天照大御神を岩戸から戻すという日本神話。戸隠神社奥宮には、同じ天手力男命が祀られる。

アクセス
長池親水公園の駐車場を起点・終点に周回するのがおすすめ。富士急行線富士山駅から「ふじっこ号」で長池親水公園前下車、参道口まで徒歩約80分。高速バス山中湖平野バス待合所から徒歩約30分。

コメント:低山トラベラー/山旅文筆家 大内 征
石割神社駐車場にトイレあり。鳥居の登山口からいきなり急な階段が続く。石割山から大平山に向かう道は傾斜とぬかるみに注意。春の山桜と梅雨前の新緑は抜群の気持ちよさです。

③能郷白山(のうごうはくさん)【岐阜県・福井県】
・歩行時間:6時間30分
・距離:約16km
・撮影時期:10月下旬
■白山と同じく泰澄大師が開山した信仰の山。
岐阜県本巣市根尾の奥深くにそびえ、なだらかなやさしい山容をしている能郷白山(のうごうはくさん)は、越美山地の主峰であり、奥美濃の盟主。両白山地とは越美山地と加越山地の総称で、じつは「両白」とは、「白山」と「能郷白山」を表している。周囲よりも高いため、冬や春の晴れた日には濃尾平野からも白い頂を見つけやすい。
能郷白山は、白山と同様に奈良時代の僧、泰澄(たいちょう)によって開山されたと伝わる。山そのものがご神体で、山頂には能郷白山神社の奥の院がある。無雪期には最短で登れる温見峠ルートが好まれるが、本来の登拝道は能郷谷から。距離も高低差も大きい、登りごたえのある道で山頂をめざしてみよう。
登山口は、能郷白山より手前の前山に取り付く地点だが、現在は林道ゲートから小一時間歩いて向かう。登山口には徒渉があり、毎年春に地元ボランティアが仮設橋を設置してくれている。急登で標高を上げて前山へ。次々と現れるブナなどの巨樹や老木は風格がある。
前山の最高点を巻いて吊り尾根にさしかかると、いよいよ能郷白山と対峙する。白山方面の眺めも楽しみながら大きな台地状の頂上に向かおう。北端に山頂があり、やや南方に離れて奥の院が鎮座する。




コラム:歴史を守る地元グループ
能郷白山の開山祭や維持管理には、本巣市根尾の住民が尽力している。写真は現在の奥の院。台風での倒壊を教訓に強固なものに作り替え、登山者向けレスキュー用品や登頂記念札なども備えた。

アクセス
国道157号を北上して本巣市根尾の中心部を抜け、能郷白山神社前で能郷谷に向かう林道へ。林道ゲート前に詰めて約10台駐車できる。電車の場合、樽見駅から約13kmタクシー利用となる。

コメント:山ママライター マリベ
奥の院に用意された登頂記念札は、地元書道家の手書きに朱印が押された一点もの。一度に多く作れないため、ないこともあるそうです。登ったときにあるかドキドキしますね!

④高野山(こうやさん)【和歌山県】
歩行時間:3時間20分
距離:約11km
撮影時期:8月中旬
■天空の聖地で祈りの道を歩く。
弘法大師空海が開いた、真言密教の本拠地である高野山(こうやさん)。紀伊半島の深い山のなかに位置し、山麓から歩いて登るルートもいくつかあるが、ケーブル利用で山上部にアクセスすれば、手軽にその魅力に触れることができる。夏は涼しく、冬はときおり雪も積もるが、一年中楽しめる山だ。
高野山は、1000m級の山々に囲まれた盆地のような地形になっており、周囲の山を「八葉蓮華」にたとえて八葉の峰と呼ぶ。
かつて女人禁制だった時代、八葉の峰までが女性に許されたゾーン。山麓から続く道には、山内手前に女人堂が建てられ、そこが結界となっていた。それらをたどる「女人道」が、いまは人気の山上トレイルとなっている。随所で山内につながる道もあるので、途中で店に立ち寄るなど、自由度の高いプランニングができる。
中の橋からは、弘法大師御廟(こうぼうだいしごびょう)のある奥之院へ。このエリアには、独特の静謐な空気が立ち込めていて、自然と気持ちが引き締まる。御廟にお詣りしたあとは一の橋へ。長い石畳の参道には、名だたる武将の墓なども多く、飽きない。



コラム:現存唯一の不動坂女人堂
かつては「高野七口」と呼ばれる山麓からの登山道に、それぞれに女人堂が建てられていたという。大峰口、大滝口、龍神口、大門口などは建物は失われており、現在不動坂にのみお堂が残っている。

アクセス
南海難波駅から南海電鉄高野線で高野山極楽橋へ。ケーブルに乗り換え、高野山へ。山上からはバスで不動坂女人堂前下車。山上バスは、どれに乗っても女人堂前には行ける。

コメント:アウトドアライター 根岸真理
テイクアウトできる小倉屋の「笹寿司」や麩善の生麩まんじゅう「笹巻きあんぷ」などは行動食にぴったり。胡麻豆腐の名店「濱田屋」でイートインできる胡麻豆腐は絶品です。

※この記事はPEAKS[2024年3月号 No.164]からの転載であり、記載の内容は誌面掲載時のままとなっております。
**********
▼PEAKS最新号のご購入はAmazonをチェック
SHARE
PROFILE

PEAKS 編集部
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。