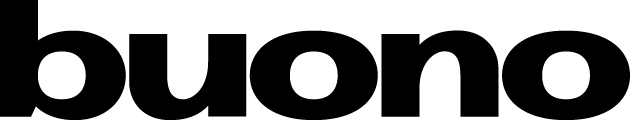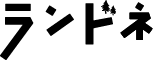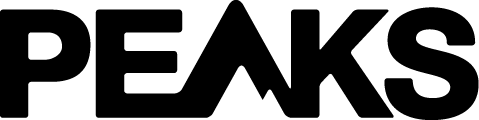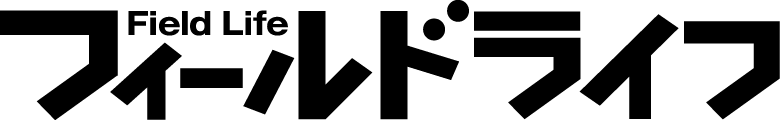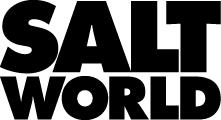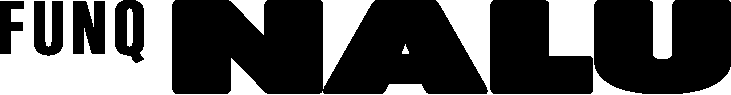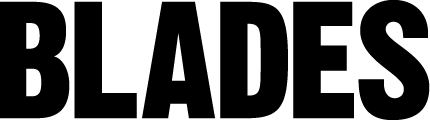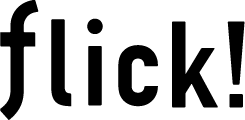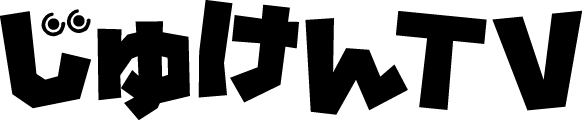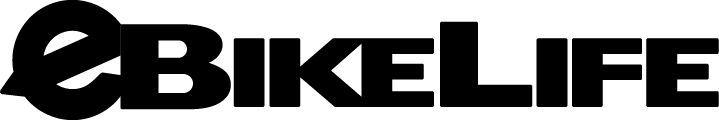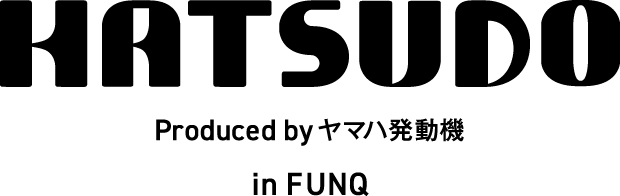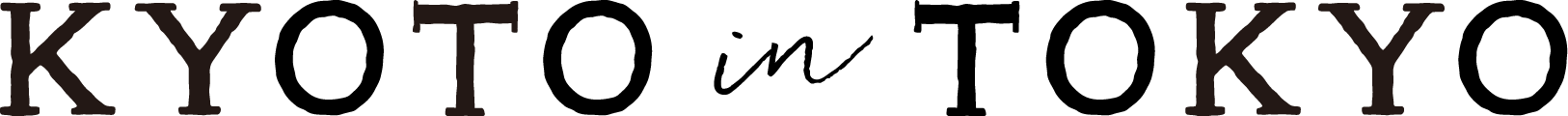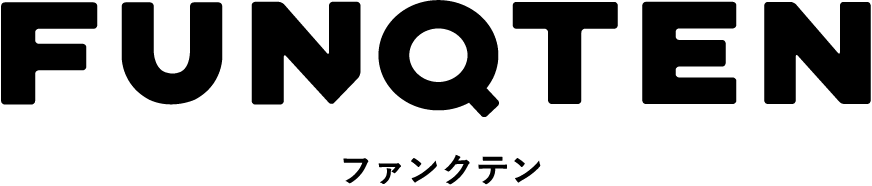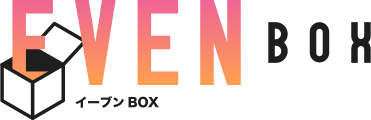老舗遺産、焼きとんの『秋田屋』を知っているか
buono 編集部
- 2016年10月25日
ランチに出る勤め人が忙しなく歩く浜松町のオフィス街で、締め切られた店内ではラジオの音だけが鳴り響いている。瑞々しい肉を洗い、切っては刺し、切っては刺し、黙々と繰り返す仕込み――。
数多ある東京の焼きとん屋の中でも屈指の老舗として知られている『秋田屋』の日常だ。
その歴史は戦前にまで遡る。秋田県横手市から初代が移住し、麻布十番の近辺で開店したのが昭和4年。当時は、今と違い串揚げ屋だったという。その後戦争が始まり、新橋の闇市を経て、現在の場所に移ったのが戦後の昭和21年頃のこと。この頃から焼きとん屋としての営業が始まった。
東京で古参の焼きとん屋の日常
13時を回った頃、芝浦から潰したての肉が店に届いた。
『秋田屋』が仕入れるホルモンは、芝浦の豚肉業者でもトップクラスのもの。電話注文の配送ではなく、必ず毎日足を運んで仕入れる。
「がつ」(胃袋)と「しろ」(大腸)が入った袋を手早く開け、ボイルし、タンの部分から軟骨を腸裂き包丁でさばいて分け、ハラミの皮を落としてタワシで丁寧に洗う。まったくもって息つく暇のない仕込みは、何より鮮度を重視し、内臓肉の臭みを取ることを徹底しているからだ。


臭みが無く上質な、焼きとんの魅力
「予め市場でボイルしたものではなく、必ず生の状態で仕入れているので、早く洗わないと臭みが残ってしまうんです」
目にも止まらない早さでハツをさばきながら、三代目の金澤義久さんが話す。決して誇るわけでもなく、当たり前のように。すべての徹底した手作業は「新鮮で美味しい焼きとんを提供する」ために、60年以上ずっと続けている普通のことなのだ。

受け継がれる一本のしあわせ
その焼きとんは全10種類。もっともクセがなく、肉々しさを感じる「かしら」(こめかみ)、ザクっとした歯ごたえの「たん」(舌)、コリコリの食感がクセになる人続出の「なんこつ」(気管)に、さっぱりとした風味を楽しめる「はつ」。そしてシャキシャキとした歯触りの「がつ」(胃袋)や、噛むほどに旨味が溢れ出てくる「てっぽー」(直腸)、淡白で弾力のある「こぶくろ」(子宮)に意外にもジューシーな変化球「ほるもん」(睾丸)といった通好みの串にはそれぞれ熱狂的なファンが多い。さらに苦手な人であっても「ここのだけは食べられる」と定評のあるレバー、そして軟骨を叩いてミンチ状に仕立てた、一人一本限定の「たたき」は言わずもがなの看板メニューである。
串打ちは1本約10秒の早業。火の通りを考えて手前は小さく真ん中が大きい“羽子板刺し”で1本約50g。仕込みは、朝10時頃から7~8人で一気にやってもオープンにギリギリ間に合うぐらいだとか。

7年前から受け継ぎ、仕込みから人に任せず、常に手と身体を動かし、スタッフを気遣う義久さんは、受け継いだ当初は「味が変わった」と言われないように、プレッシャーを感じていたと言う。
その心配が杞憂だったことは、15時半のオープン直後に目の当たりにした光景が物語っていた。平日にも関わらずシャッターを開ける前からお客が並び、人がなだれ込んで、瞬く間に満席になったのである。彼らの満面の笑みが、今日も明日もこれからも、変わらぬ味を守り続ける老舗の矜持を物語っていた。


DATA
秋田屋
住所/東京都港区浜松町2-1-2
TEL/03-3432-0020
営業/15:30~21:30、土曜15:30~20:30
休み/日・祝日、第3土曜
出典
SHARE
PROFILE

buono 編集部
使う道具や食材にこだわり、一歩進んだ料理で誰かをよろこばせたい。そんな料理ギークな男性に向けた、斬新な視点で食の楽しさを提案するフードエンターテイメントマガジン。
使う道具や食材にこだわり、一歩進んだ料理で誰かをよろこばせたい。そんな料理ギークな男性に向けた、斬新な視点で食の楽しさを提案するフードエンターテイメントマガジン。