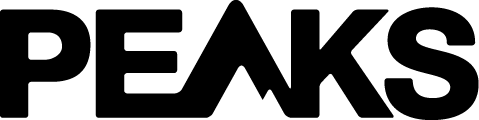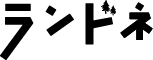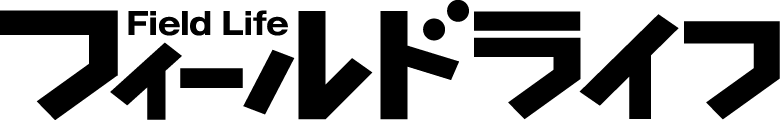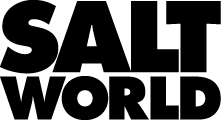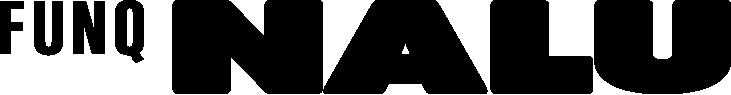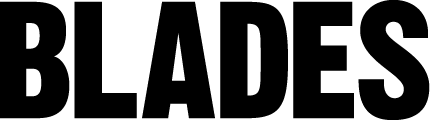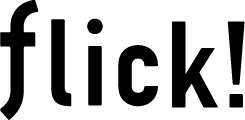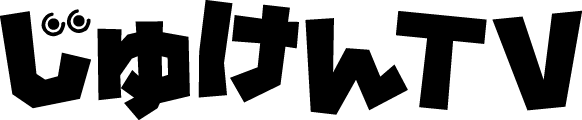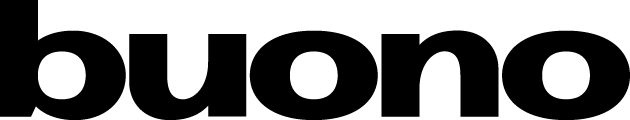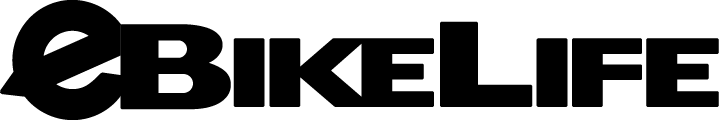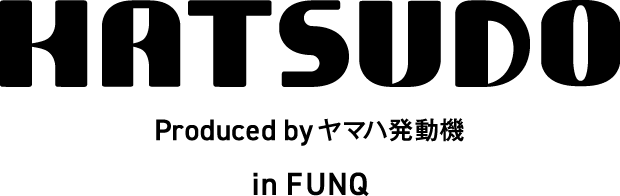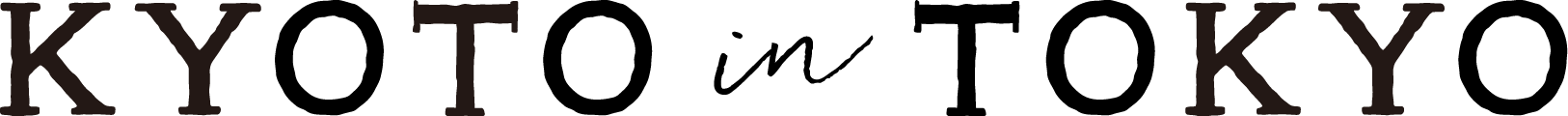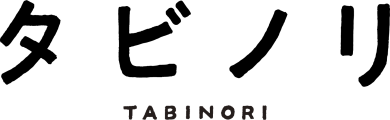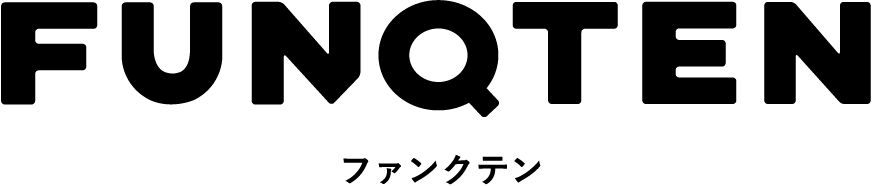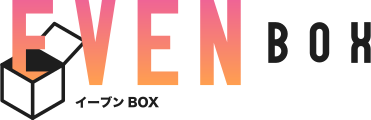現代アルパインクライミングの到達点。ジャヌー北壁の覇者、ジャクソン・マーベル来日。
森山憲一
- 2025年04月17日
INDEX
“ヒマラヤ屈指の難壁”といわれるジャヌー北壁(7,711m)を完登し、ピオレドール(登山版アカデミー賞ともいわれるフランス主催の賞)を受賞したアメリカのクライマー、ジャクソン・マーベルがこの3月に来日しトークイベントを行なった。
3月26日には東京・神保町の「The Tribe」で、続く27日には原宿の「THE NORTH FACE Mountain」で開催。1976年にジャヌー北壁を初登攀した山学同志会のメンバーも含めていずれも多くの観客がつめかけ、世界最先端のアルパインクライミングに固唾を呑んだ。
編集◉PEAKS編集部
文・写真◉森山憲一 Text & Photo by Kenichi Moriyama
インタビュー通訳◉鳴海玄希 Interpretation by Genki Narumi
世界屈指の難壁――ジャヌー北壁

マーベルがアラン・ルソー、マット・コーネルと3人で登ったジャヌー北壁は、正真正銘のヒマラヤ屈指の難壁であり、難易度でいえば、マカルー西壁やK2西壁と並ぶ、ヒマラヤの頂点に位置する課題である。彼らのクライミングは、ここ10年ほどのヒマラヤクライミングの世界では突出したパフォーマンスであることをまず知ってほしい。
もう少し具体的に説明しよう。
1976年に日本の山学同志会隊によって初登攀されたジャヌー北壁は、マーベルら以前に6回登られている。ただしそのうち4回は、北壁左端をたどる山学同志会ルート。1989年には、より難しい北壁中央部のルートをトモ・チェセンがソロで登ったと主張しているが、これはその真偽が問われているいわく付きの記録。さらに2004年には、最も傾斜の強い北壁ど真ん中の直登にロシアのチームがついに成功。ところがこのときは、フィックスロープをはじめとした物資を大量投入したやや強引な方法で登られており、登山界での評価は微妙である。
すなわち、ジャヌー北壁の真骨頂といえる岩壁中央部を文句のつけようがないかたちで登ったクライマーはこれまでいなかったともいえるのだ。
そこにチャレンジしてきた面々がまたすごい。ジョン・ロスケリー、ピエール・ベジャン、パトリック・ベルオー、アソール・ウィンプ、アンドリュー・リンドブレイド、ジャレッド・オグデン、パベル・シャバリン、マーク・シノット、エアハルト・ロレタン、ウーリー・ステック、ステファン・ジークリストなどなど……。’80年代から2000年代にかけてのオールスター揃い踏みで、彼らの強力な挑戦を北壁はことごとくはねのけてきた。これだけでもジャヌー北壁の価値がわかるというものだ。
世界中の北壁のなかで頂点に君臨する北壁。まさにこここそが ”The North Face” というべき存在なのである。

2007年に北西稜を登った際に北壁を垣間見たセルゲイ・コファノフはこのように語っている。
「ここ(北壁)を登るのならば、片道切符の旅に出かける覚悟が必要だ」
マーベルらはわずか3人、所要7日間、装備は各自バックパックひとつだけ、シェルパなどのサポートもなしで、あまりにも鮮やかにこの難壁を登り切った。ピオレドールを受賞したのは当然すぎる結果であり、筆者個人的にも、ここ20年のヒマラヤで最高のパフォーマンスだと感じている。
そのマーベルに詳しい話を聞く機会を得たので、以下に紹介しよう。
スケールの大きい冒険がしたい

──いま、いくつになるんですか。
29歳です。アメリカのユタ州出身で、1996年1月4日生まれです。
──登山はいつごろ始めたんでしょうか。
15歳のときです。地元のレストランで働いていた女性が誘ってくれました。もともと興味があったんですが、なかなかきっかけがなくて。なので彼女の誘いに飛びつきました。
──当初からアルパインクライミングに力を入れていたんですか?
いや、最初はロッククライミングをしていたんです。そのうちアイスクライミングもやるようになって、最初の3~4年はマルチピッチの岩や氷を登っていました。18歳ごろだったかな、もっと大きな山に登りたいと思うようになって、アルパインクライミングを目指すようになりました。
──アルパインクライミングはなにが魅力だったんですか。
スケールの大きさですね。もっと大きな冒険がしたい、もっとデカい山を登りたい、そういう場所で自分の可能性を試したいと思うようになったんです。
──ジャヌーについて考え始めたのはいつごろですか。
2019年にロシアのクライマーがジャヌー東壁を登ったときの写真を見たのがきっかけです。そのラインに感銘を受けて、ジャヌー北壁の存在を知り、歴史について調べ始めたんです。北壁に挑戦するというアイデアは、2020年にアランと僕との間で自然に生まれました。とりあえず見に行くだけのつもりだったんですが、トレーニングを重ねて、2021年にアランと最初の遠征を行ないました。
──トレーニングはどういうことを?
アラスカで登りまくりました。ハンターのムーンフラワーバットレスとか、デナリのスロヴァックダイレクトとか、フォーレイカーのインフィニットスパーとか、ほかにもたくさん、スピードを意識して登りました。インフィニットスパーでは65時間連続行動したりもしましたよ。
──65時間!? その間寝ずに?
10分くらいは寝たかな。歩きながら(笑)。
──なんとまあ……
ジャヌーに備えて、自分たちの限界を知りたいと思っていたんですよ。どこまで動き続けることができるか。
「これは不可能だ。アルパインスタイルで登るのは無理だろう」

──初めてジャヌー北壁を見たとき、いけると思いましたか?
いや、アランも僕も「これは不可能だ、アルパインスタイルで登るのは無理だろう」と思いましたね。トライしたとしても成功する確率は25%くらいかなと。行く前は、北壁が無理なら、ジャパニーズルート(山学同志会ルート)を登るか、北西稜のマジックピラーを登って、とにかく山頂に達することを目指そうとも話していました。でもジャヌーの麓に滞在しているうちに、どうしても北壁をやってみたくなったんです。「せっかくここまで来たのだから、やるだけやってみよう」と。見た目と同じくらい恐ろしいものなのかどうかを確認するためにもね。
──その翌年、2022年にはアランとマットのふたりでトライし、3回目となる2023年に3人で挑むことになります。このときは登頂できると思っていましたか?
じつはこのとき、個人的には少し微妙な時期だったんです。前年にパートナー(恋人)が事故に遭って、山に登っている場合かと迷っていたんですね。どこか心が定まらないところがあって、もし気分が乗らなければ登らない、ありのままの自分を受け入れようという心構えでした。そんな感じで、自分の心の状態を常に意識するようにしていました。でもジャヌーが近づくにつれてポジティブに集中できてきて、チームの雰囲気もよかったし、これは登れるんじゃないかと思えるようになってきました。
──いちばんの懸念点はどんなことでしたか。
天候です。2021年にトライしたとき、カギは天候だと感じました。標高が高いので寒すぎると難易度が上がるんです。成功には気温の高さと湿度の高さが必要だと思っていました。
──つまり、技術的には登れる自信があったんですね。
そうですね、僕たちの能力の範囲内だとは感じていました。問題は外的要因で、悪天候が予想以上に早く訪れるのではないか、壁の氷が落ちてしまうのではないかという心配がありました。気温が下がると氷が乾燥して、はがれやすくなってしまうんですよ。
──戦略として、もっともうまくいったことはどんなことですか?
G7のエア式ポータレッジです。これまでの多くのクライマーが苦労してきたのはビバークの問題だと思うんです。上部ヘッドウォールは垂直の壁が続いてビバークポイントがないですからね。でも旧来のポータレッジは重い。2kg足らずのG7は革命だと思いましたよ。それからロープシステムも工夫しました。通常のリード&フォローではなく、トップは登ったらロープをフィックスして、フォロワーはそのロープにマイクロトラクションをかけて登ることにしました。そうすることで、トップはフォロワーが登っている間に休めるうえに、ユマーリングをするわけではないので、ロープのダメージも抑えられるわけです。あとは、ヘッドウォールではバックパックを背負わずに荷揚げしました。これも有効だったと思います。

──ロープはどんなものを?
最初の年は、10mmのクライミングロープと9mmの荷揚げ用ロープを持っていきました。ある程度太くないとロープのダメージが心配だったので。でも、実際にトライをしてみて、もっと細くても大丈夫だということがわかりました。2023年に使ったのは、クライミングロープは8.9mm×60m、荷揚げ用ロープは6mmにしました。ロープの重量を大幅に減らすことができましたよ。
──ギアについても教えてください。
カムを1.5セット。0.1から1まで2個ずつで、2、3、4は1個ずつ。それから、アイススクリューを12本、ペッカーを5個、ストッパーを1セット、ピトンをいくつか持っていきました。水晶ポケットのある難しいミックスクライミングでは、ペッカーが役に立ちましたね。
──ペッカー5本でポータレッジを吊ったという記事を読んだことがあるんですが、これは事実ですか?
本当です(笑)。ポータレッジの上で動いたらペッカー1本が飛びました。最悪でしたよ(笑)。でもじつは、離れた場所にピトンとカムでバックアップをとっていたんです。なので、仮にペッカーが全部吹っ飛んでも、大スイングするだけで落ちはしない仕組みです。ピトンとカムが決まる場所はポータレッジが吊りにくかったんですよ。
──荷物の総重量はどれくらいでしたか。
正確に計っていませんが……ひとりあたり15kgくらいだったと思います。50リットルパックに収めました。
──少ないですね。
食料や燃料を切り詰めました。燃料缶は4つ、ストーブは1つ、寝袋も3人が入れるものを1つだけです。本当に必要な物だけを持っていくようにしました。
──食料はどんなものを?
ひとりあたり1日5、6本のエナジーバーと、マウンテンハウス(アメリカでポピュラーなフリーズドライ食)1日1袋。これらを7日分。マウンテンハウスは袋から出してジップロックに詰め直して持っていきました。飲みものは粉末のスポーツドリンクとコーヒー。
──食欲がなくなることはありませんでしたか?
全然。アランとマットが残したものまで僕が食べてました。でもおもしろいことに、登山後に僕は12kgも体重が落ちたのに、アランは2kgちょっとしか落ちていなかったんですよ。
僕たちはスーパークライマーではない
──ルートを通じて、もっとも印象に残っているのはどこでしょうか。
やっぱり標高7,000mからのヘッドウォールですね。とくにマットがリードしたピッチが印象的です。傾斜は垂直前後で、ところどころ氷が張っています。氷を登れるかと思いきや、壁から浮いていて使えないんですよ! なので氷から離れて岩を登ったんですが、うまい具合にピックをかけられる穴が開いていて、非常に印象的なクライミングになりました。

──岩質は?
グラナイト(花崗岩)ですね。
──氷は浮いているところが多いんでしょうか。
場所によって異なります。十分な厚さがあって壁にしっかり付いているところもありましたが、厚さ6~7cmくらいのところもあります。マットがリードしたピッチのように浮いている箇所もありましたが、この厚みでも壁にしっかり付いていているところもありました。
──ヘッドウォールを抜けると北西稜に合流しますが、そこはどうでしたか?
北西稜に出たら楽になるかと思いきや、全然そんなことはなくて、頂上直下の7,600mまで来ても、下からは無理っぽく見えたほどのピッチが出てくるんですよ。最後まで楽させてくれないじゃないか!と思わされましたね。
──ところで、個人的に聞いておきたいんですが、トモ・チェセンの単独登攀についてどう思いますか?
難しい質問ですね……。人間はできると信じたいし、夢を否定したくはない。でも、彼が本当に登ったのかと聞かれたら、僕は信じがたいと言うしかない。トモが登ったというラインは技術的にはとても難しいと思うし、ましてやそれをソロで、24時間で登るとなると、現実的にはありえないことだと思います。もしこれが本当なのだったら、間違いなく、ヒマラヤ史上最高レベルの偉業です。
──難しい質問にも答えていただいてありがとうございます。今後のことなんですが、次はどんなところをねらっているんですか。
僕らチームでやりたいことのリストを作っています。ジャヌーを終えてから、それに取り組んでいるところです。でもそれが具体的になんなのかは、あまり話したくないんですよ。だれかに先んじてしまわれるのを恐れているわけではなく、曖昧にしようとしているわけでもないんですが、成功確率が高くないことなので、結局できないかもしれない。そういうことを事前に公言して自分たちを追い込みたくないんです。
──またアランとマットの3人で組む予定なんですか?
はい。いいチームなので、またいっしょに登るのが楽しみです。僕たちは一人ひとりがスーパーな能力をもったクライマーではありませんが、相性がよくて、お互いの長所と短所を補い合うことができるチームだと思っています。チームになったときにすごい力を発揮できるんですよ。
──最後に。ジャヌー北壁を登ってピオレドールを受賞したことは、あなたの人生や登山になにか変化をもたらしましたか?
とくにありません。世界の登山界から僕たちのクライミングを祝福してもらうのは、とても光栄なことではあります。でも、僕自身に大きな変化はありません。これまでもこれからも同じですよ。

大事なのは無事に帰ってくること
登山史上に残る登攀を成し遂げたマーベルだが、気負いがない自然体が非常に印象的な人物だった。
自分を大きく見せようという衒いがまったくなく、過酷であったはずの登攀も楽しそうに語る。聞いているのはジャヌー北壁のことではなく、どこかのハイキングのことかとこちらが勘違いしそうになるほどだ。
トークイベントで語っていたことでも印象的なフレーズがあった。
「僕らにとっていちばん大事なことは、無事に帰ってくることです」
マーベルたちは、自分たちが登ったルートに「Round Trip Ticket」という名前を付けた。これは、かつてセルゲイ・コファノフがジャヌー北壁について「片道切符の旅に出かける覚悟が必要だ」と語ったことへのアンサーだ。
「おれたちは往復切符で無事に帰ってきたぞ!」
──というわけである。
- CATEGORY :
- TAG :
- BRAND :
- PEAKS
- CREDIT :
-
編集◉PEAKS編集部
文・写真◉森山憲一 Text & Photo by Kenichi Moriyama
インタビュー通訳◉鳴海玄希 Interpretation by Genki Narumi
SHARE
PROFILE

PEAKS / 山岳ライター
森山憲一
『山と溪谷』『ROCK & SNOW』『PEAKS』編集部を経て、現在はフリーランスのライター。高尾山からエベレストまで全般に詳しいが、とくに好きなジャンルはクライミングや冒険系。個人ブログ https://www.moriyamakenichi.com
『山と溪谷』『ROCK & SNOW』『PEAKS』編集部を経て、現在はフリーランスのライター。高尾山からエベレストまで全般に詳しいが、とくに好きなジャンルはクライミングや冒険系。個人ブログ https://www.moriyamakenichi.com