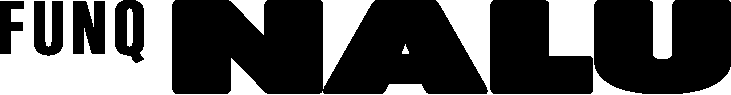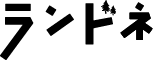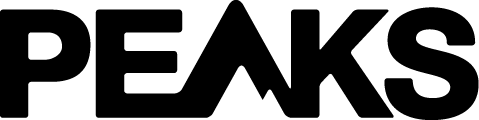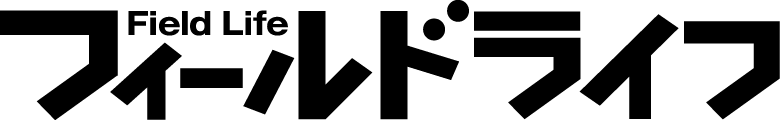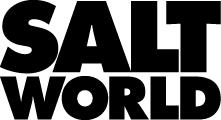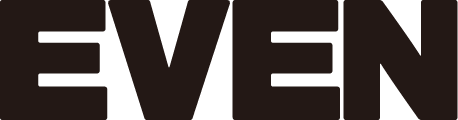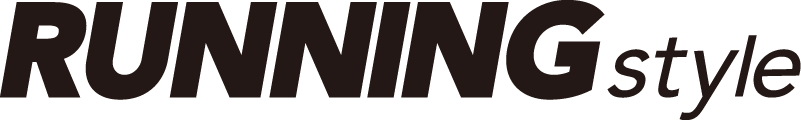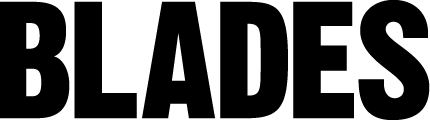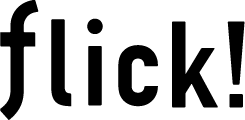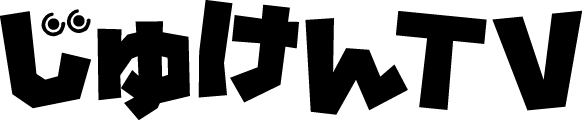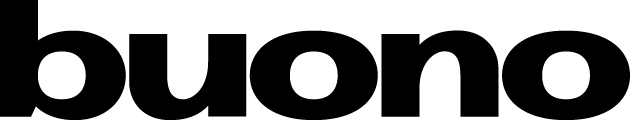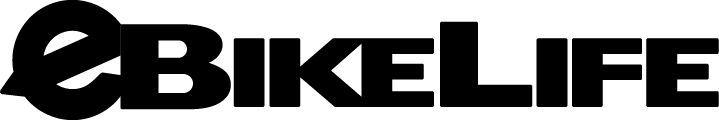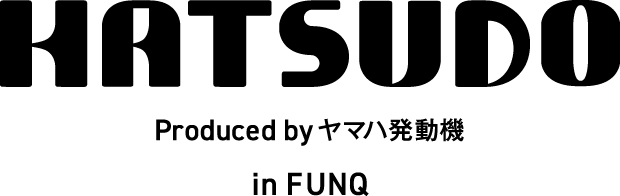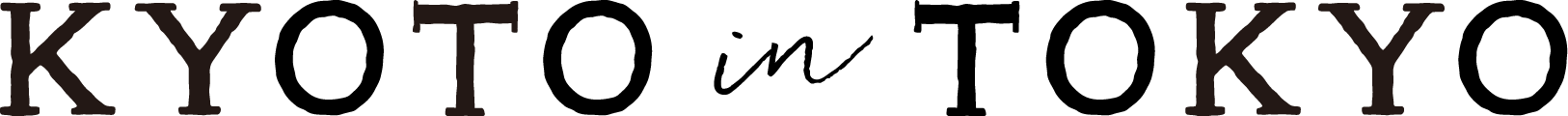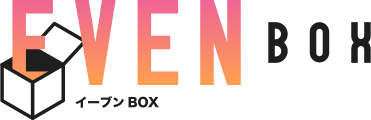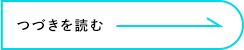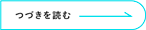東京オリンピック開催迫る! 事前に知っておきたいサーフィン5つのこと
FUNQ NALU 編集部
- 2021年07月15日
INDEX
東京オリンピックの開催がいよいよとなってきた。約一年前、開催延期という結果に涙をのんだ人も多いことだろう。しかし、夢の初開催まであと一歩のところに迫っている。ここでは史上初となるオリンピック競技としてのサーフィンイベントを迎えるにあたり、あらためて事前に知っておきたいことに目を通しておこう。
1 2
SHARE
PROFILE

FUNQ NALU 編集部
テーマは「THE ART OF SURFING」。波との出会いは一期一会。そんな儚くも美しい波を心から愛するサーファーたちの、心揺さぶる会心のフォトが満載のサーフマガジン。
テーマは「THE ART OF SURFING」。波との出会いは一期一会。そんな儚くも美しい波を心から愛するサーファーたちの、心揺さぶる会心のフォトが満載のサーフマガジン。