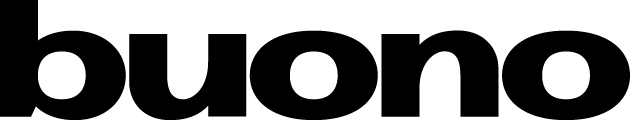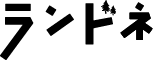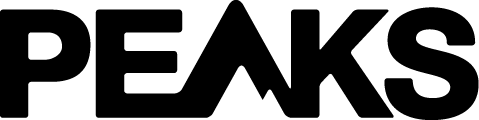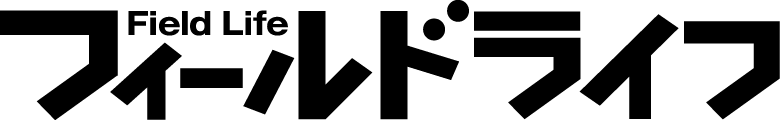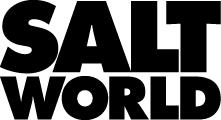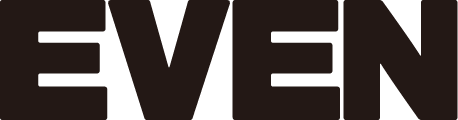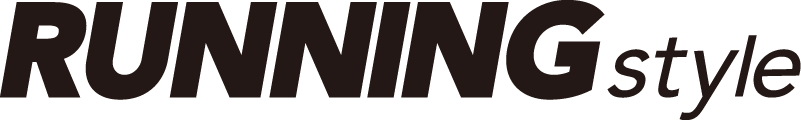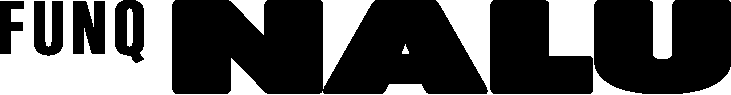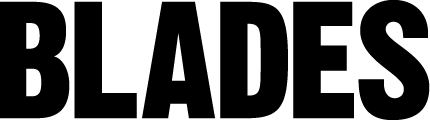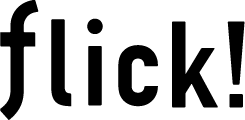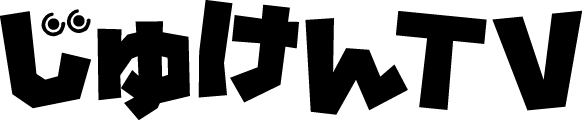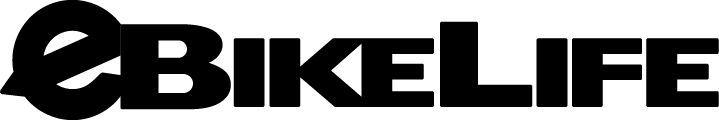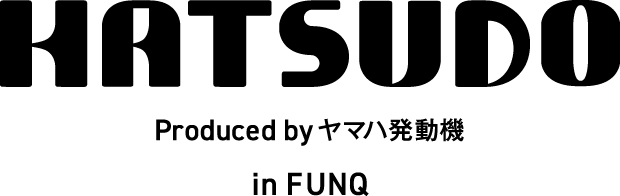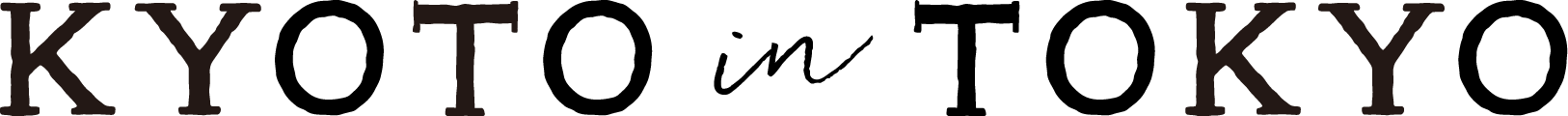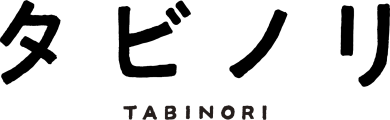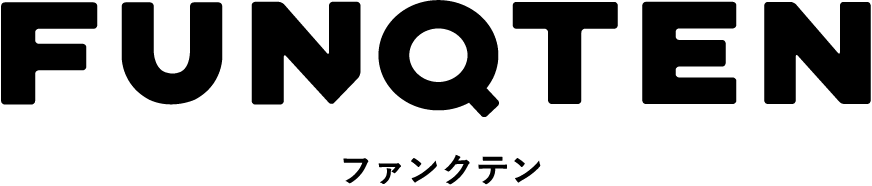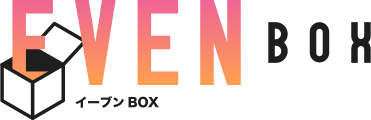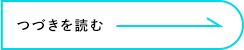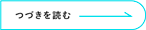低温調理、最終案内。|短時間で熟成効果のある最新メソッドを徹底解剖
buono 編集部
- 2020年10月07日
INDEX
40数年前にフランスで真空調理法として産声を上げ、時代とともに進化をし続けてきた
プロのメソッド“低温調理”
そのメソッドを科学的裏付けとともに身に付け、実践してみよう。
監修してくれたのは、料理人であり作家でもある樋口直哉氏。書籍『最高のおにぎりの作り方』(KADOKAWA)、『定番の“当たり前”を見直す 新しい料理の教科書』(マガジンハウス)など、科学的な視点から料理を分析・探究する活動に注目が集まっている。

道具とロジックで極める
“低温調理”とは、端的に言えば、食材の一部のタンパク質を変性させない温度帯(60度前後)で均一に火入れし、例えば塊肉などをやわらかく調理する技法である。
「さらに肉の場合、含まれる酵素が作用する温度帯とされる40度から60度を長く通過させることで、熟成と同じ効果が短時間で得られます。それによって、タンパク質が分解し“コク味”成分が増える。これこそ、低温調理の最大のメリットです」と樋口氏。
もはやプロだけでなく料理ギークも注目するメソッドの基礎 知識から定番肉の加熱時間、日 本未上陸の最新ツールを使った至高のレシピまで紹介。低温調理の現在地を徹底解剖する。
※掲載の温度や時間は各料理人の経験に基づくもので、食材の管理などにより調整が必要です。 また豚肉に関して、安全な加熱調理の目安は「中心温度63°C 30分」とされています。
“低温調理”イマドキの潮流
1979年にフランスの料理人ジョルジュ・プラリュ氏が生み出した低温調理は大別して2つの流れがある。ひとつは湯煎やオイルバス、スチームコンベクションオーブンを使用した“恒温調理”。もうひとつは、『アルページュ』のアラン・パッサール氏が編み出した“低温ロースト”の流れだ。以来、様々な手法で進化を遂げている。
低温ロースト系
『アストランス』のパスカル・バルボ氏が編み出したオーブンに短時間出し入れする手法は、手間と時間はかかるが失敗も少なく、塊肉のローストにはおすすめの調理法。
- 弱火のグリヤードや鉄板、鋳鉄の鍋で転がしながら低温やけどをさせるように焼く。
- オーブンに短時間、入れては休ませることを繰り返す。
恒温調理系
オイルバスとは恒温湯煎器の油版。油の中には空気がないので真空調理法の一種だが、袋に入れず食材をそのまま加熱す るのでより均一な火入れができるという主張がある。
- 湯煎
- スチームコンベクションオーブン
- オイルバス
安全基準と対策で挑むべし
低温調理のテクニックを学ぶ前に、大前提として安全基準を満たさなければならない。新鮮な食材を買い、冷蔵保存や道具の殺菌、調理前に手の洗浄など衛生面は一般的な調理と同じだが、気をつけたいのは加熱の温度帯だ。低温でも、長い時間をかけて加熱することで菌は減少する。右の厚生労働省による加熱基準も頭に入れておこう。
加熱基準
鶏肉や豚肉、牛肉にはサルモネラ菌とカンピロバクターの危険があるが、55〜60°Cの長時間加熱でリスクが減らせるので、55°C以上の温度設定が基本。魚のタンパク質はより低い温度で凝固を始めるので47°C以上にするが表面を焼けば腸炎ビブリオ菌は死滅する。
- 低温調理に向かない素材
- 豚レバー
- 挽肉
- 牛レバー
- 海老類
食中毒対策
「付けない、増やさない、やっつける」が、食中毒対策の基本。とりわけ魚は生食用を選び、 扱う時は調理専用の手袋を着用すべし。下の写真の「ニトリル手袋」は、ゴワゴワ感がなく手に密着して細かい作業ができるので樋口氏も推奨。

- TAG :
- BRAND :
- buono
- CREDIT :
-
写真=深澤慎平/加藤史人/久保田敦/西島渚
文=藤谷良介/本多美也子/河西みのり/和谷尚美/岡村一葉
監修・調理=樋口直哉
参考文献=「マギーキッチンサイエンス」(共立出版)
SHARE
PROFILE

buono 編集部
使う道具や食材にこだわり、一歩進んだ料理で誰かをよろこばせたい。そんな料理ギークな男性に向けた、斬新な視点で食の楽しさを提案するフードエンターテイメントマガジン。
使う道具や食材にこだわり、一歩進んだ料理で誰かをよろこばせたい。そんな料理ギークな男性に向けた、斬新な視点で食の楽しさを提案するフードエンターテイメントマガジン。